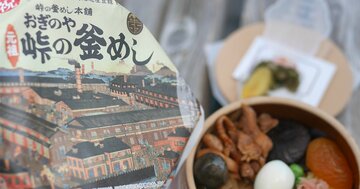つまり、1等車、2等車の富裕層は食堂車でコース料理を楽しみ、3等車の一般客は街中や駅構内の売店や自動販売機でサンドイッチなど軽食を買って乗車した。一方、日本の「駅弁」は当初から3等車の一般客を想定しており、ごく一部の上流階層を除き、広く同じものが食べられた。こうして駅弁は「国民食」となった。
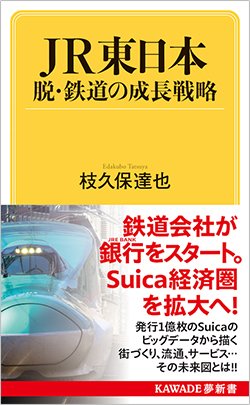 本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
だが、現代では駅弁は唯一の選択肢ではない。そんな時代に駅弁が生き残るには、これまで述べてきたように地域性を反映した弁当という文化的な価値を重視し、高付加価値商品としての地位を確立する必要がある。
駅弁業者は試行錯誤している。まねき食品は冷凍駅弁の開発、崎陽軒とのコラボ商品の開発、大阪・関西万博への出店、スイスチューリッヒ中央駅への3週間限定出店(花善、松浦商店との共同出店)などさまざまな手を打っている。今後の人口減少をふまえれば新規顧客の開拓は必至である。
スイスで販売した駅弁は食品輸送のコストもあり日本円で3000~4000円だったが、瞬く間に売り切れた。日本文化への関心の高さとともに「安すぎる日本」を象徴するエピソードだが、本質は日本市場も同じである。
大衆のための弁当でなければ市場は縮小する、しかし、高付加価値化しなければ商売として成立しない。駅弁の文化的価値と消費財としての性質をどのように両立させて発展を目指すのか、今年度末の研究報告を楽しみに待とう。