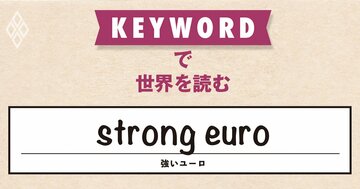Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
戦後、ポンドからドルへ基軸通貨が移る過程で、英国は通貨切り下げと外貨不足に直面し、スターリング・エリアも巨額損失を被った。インドの分割払い合意、アルゼンチンのドル要求、豪・NZの追随、産油国のドル化とペトロダラー確立――各国の対応は明暗を分けた。日本の対米一極投資にも示唆を与える。(BNPパリバ証券経済調査本部長チーフエコノミスト 河野龍太郎)
ポンド保有という実質的債務を
抱えたスターリング・エリア
戦後、ポンドからドルに基軸通貨が移行した際、最もダメージを被ったのが英国だった。戦前、主に金本位制が取られていたとはいえ、皆が国際通貨として、ポンドを喜んで保有しようとしていたのが、そうではなくなったのである。
ポンドの価値低下の結果、英国の人々の購買力は著しく低下した。そして、英国の次にダメージを食らったのが、英連邦を中心とするスターリング・エリアの国々だ。
戦間期のブロック経済の下で、ポンドを資産として積み上げたスターリング・ブロックの国々は、戦後、ドルに基軸通貨が移行する過程で、価値下落による損失を受け入れざるを得なかった。
日米同盟の影響もあって、日本では、ドル単一基軸通貨制の継続にまったく疑いを持たない人が多い。ここで、戦後、ポンドからドルへの基軸通貨の移行期にスターリング・エリアの国々がどのような対応を取ったのか、振り返っておく必要があるだろう。
まず、スターリング・ブロックとは、戦間期の1931年に、英国が金本位制から離脱した後、通貨貿易圏として確立した地域である。英連邦自治領や植民地、保護領、友好国などが含まれる。
英国はこれらの国々との貿易決済をポンド(スターリング)で行い、これらの国々に対する輸入代金を、帳簿上、「ロンドンにあるスターリング残高(sterling balance)」という形で積み上げ、まさにロンドンで集中管理する体制が生まれた。
戦後、スターリング残高は巨大な「英国の対外債務」として顕在化する。それ以前は、各国とも英国が発行する負債を英国債などの形で喜んで保有していたが、戦後はそうではなくなるのだ。
このスターリング残高の管理を含め、正式な為替・通貨管理の制度としてスタートしたのが、スターリング・ブロックの言わば後継であったスターリング・エリアであり、英連邦と一部の友好国が属する制度的通貨圏として、ブレトンウッズ体制の補完制度となった。
大戦終結直後の英国は、ブレトンウッズ体制における固定相場制の下で、1949年と1967年にポンドの大幅な切り下げを余儀なくされた。このため、スターリング残高を維持し続けたスターリング・エリアの各国は、前述した通り、大幅な損失を被った。
もはや基軸通貨でなくなったポンドを他の国々が受け取ってくれないため、英国は外貨不足(ドル不足)に苦しみ、スターリング・エリアの国々に対して、ポンドの保有を維持し、ドル転換しないことを要請した。自国内だけの制約ではなく、英連邦諸国にも交換制限を要請したのである。
1945年の米国からのドル支援の際の条件で、英国は1947年にドルへの自由交換を試みるが、瞬く間に巨額のドル流出が起こり、1カ月あまりで停止、その後も交換制限が続けられた。
ポンドの交換性を回復するのは1958年だが、スターリング・エリアに対しては、その後も交換制限を要請し、それが解消されるのは、ブレトンウッズ体制が崩壊した後である。
次ページでは、スターリング・エリアに属する各国の具体的な対応を検証していく。