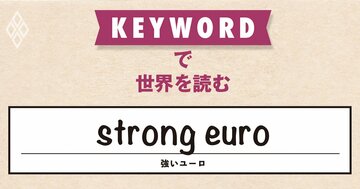Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
米国長期国債を敬遠する投資家が増え、ドル基軸体制の持続性に疑念が生じている。昨年5月のブルネルマイヤー氏らの講演は、安全資産バブルの特権と脆弱(ぜいじゃく)性を論じた。短期的な崩壊は想定しにくいが、市場期待の変化次第で、ドル一強体制は突如として揺らぐ可能性がある。(BNPパリバ証券経済調査本部長チーフエコノミスト 河野龍太郎)
米長期国債に背を向ける投資家
脆弱化するドル基軸通貨体制
米国の長期金利が下がりづらくなっている。筆者が懸念していた通り、米国の通貨覇権の継続に疑いを持つ国際投資家が、米国の長期国債の購入に慎重になっているのだ。
本稿では、経済学者のマーカス・ブルネルマイヤーとセバスチャン・メルケルが、2024年5月にケンブリッジ大学のケインズ・レクチャーで行った国際金融システムに関する講演『国際金融システムと安全資産』を紹介する。
これまで世界中の人々が「安全資産」とみなしてきたドル通貨や米国債の行方を考える上で、極めて有用な論考だと思われる。
以下が、その講演の主要ポイントである。
・安全資産(safe assets)とは、「返済能力」だけでなく、保有によって「流動性」や「心理的な安心感」をもたらす資産のことである。
リスクオフの局面では、「安全資産への逃避(flight to safety)」が世界的に生じ、その発行国に対して資金が流入する。これにより、「安全資産」発行国は財政的な政策余地が広がる一方で、「非安全資産」発行国は緊縮的な財政政策を強いられる。
・安全資産の価値は市場動向に強く依存しており、発行国は「バブル的政策(Bubble -like policy)」を取ることができる。
安全資産に対しては、リスクオフの局面において、「負のリスクプレミアム」が生じ、危機時には価値がより増す。海外から、通常よりも低い利回りで資金が流入するため、安全資産はしばしば、本源的価値を超えて高く評価されるわけである。
これは一種のバブルである。この結果、安全資産であるという信認が維持されている限り、実質的な債務返済能力を超える債務発行が可能となる。これらが「バブル的政策」の意味するところである。
・さらに、この安全資産バブルは、リスクフリー・レートを低下させるため、金融市場で行動経済学的な「サーチ・フォー・イールド(利回り追求行動)」を引き起こし、リスク資産バブルを誘発する可能性がある。
・しかし、この安全資産の価値は市場動向に強く依存するため、市場の期待が様変わりし、資本流入の突然の停止、すなわち「サドン・ストップ(sudden stop)」が訪れると、公的債務の持続性可能性問題やリスク資産バブルの崩壊など、事態は一気に反転しかねない。
・ブルネルマイヤーらは、こうした安全資産発行国の特権的構造を「Bubble mining(バブル採掘)」と呼んでいる。この構造は期待が変化すれば、一気に崩壊するという「サンスポット均衡」的な脆弱性をはらむ。
次ページでは、上記の講演を基に、ドル基軸体制の行く末を分析、予測する。