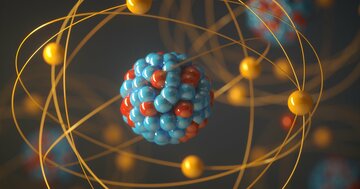以来、私の頭から、原子爆弾のことが離れなくなってしまった。高校で物理を学び、原爆の原理をいくらか知るようになってからは、「原子爆弾はいったい、どのようにしてあのような凄まじい威力を発揮するのか?そのエネルギーはどこから生じるのか?」という疑問を抱くようになった。
大学生になったある日、級友から受けた1つの誘いが、その後の私の運命を決定づけることになる。
原子力研究所で見た
神秘的な光
「僕の兄貴が茨城県・東海村にある日本原子力研究所(現・日本原子力研究開発機構)に勤めているんだ。その兄貴から、『春休みに見学に来ないか』と言われてるんだけど、君も一緒に行くかい?」
一も二もなく同行した私の目を強く惹きつけたのは、同研究所内に設置された「研究用原子炉」であった。研究用原子炉とは、その名のとおり研究目的で造られた原子炉である。実用原子炉とは異なり、発電用に使われることはない。「核分裂反応」の起こる「炉心」が水の中に入っているために外部から丸見えで、「スイミングプール型原子炉」とよばれることもある。
私たちが見学に訪れたその日、主任研究員を務めていた友人の兄君は、原子炉が「臨界」に達するプロセスを実際に見せてくれた。臨界とは「核分裂反応が連鎖的に生じ続ける状態」を指す言葉である。
原子炉が臨界に近づくにつれて、炉心近辺の水からは、じつに神秘的な、淡い青紫色の光がサーッと広がっていくのが見えた。この現象は当時、ソビエト連邦の物理学者だったパーヴェル・チェレンコフが発見したことから「チェレンコフ放射(チェレンコフ効果とも)」とよばれている。
このチェレンコフ放射による青紫色の光を目撃して、なんとも表現しようのない自然の神秘に触れたような感慨を覚えた私は、その瞬間に決意を固めたのだった。
「よし、アメリカに行って原子力工学を勉強しよう!」
テネシー大学工学部で
原子力工学を学ぶ
若者特有の突飛な思いつきと呆れられるかもしれない。だが、日本初の商業用原子力発電所である東海発電所(日本原子力発電運営)が営業運転を開始するのは1966年7月のことであり(1998年3月末で営業運転を停止後、廃炉となった)、当時の日本の原子力技術は未熟な段階だった。加えて、原子力工学科を設置している大学も限られていた。