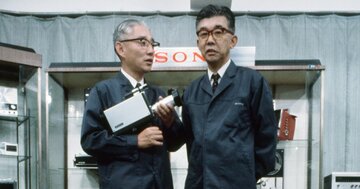次郎は「松永じいさんはどうだ。松永安左衛門だよ」と言い出した。松永は次郎の父・白洲文平の古くからの友人だった。
松永は戦前、電力会社を経営していた。そして、松永も文平も同じ神戸に店を持っており、知り合い、意気投合した。松永も文平も次郎に輪をかけたような豪放磊落な人物であった。その豪放磊落さが、分割には生きるだろうと次郎は思った。
松永は電力会社再編委員会の会長を頼まれると2つ返事で引き受けた。戦前、松永は統制経済の下、自ら経営する電力会社を国に召し上げられた過去があった。分割は、望むところだった。
松永の強引さが功を奏し
分割案が進むが……
再編委員会は正式には電気事業再編成審議会と名付けられ、松永は会長に就任した。他のメンバーは4人いたが、すべて日発の息がかかったもの。松永は全国を9ブロックに分け、各地域が発電から配電まで一括で担う会社を設立する案を提案した。
しかし、他のメンバーは地域ごとのバラツキをなくすため、9つの会社以外に調整弁として電力融通会社を作る案を提案した。
もちろん、この電力融通会社はゆくゆく日発と同じ機能を持たせるものであることを松永はわかっていた。松永は、4人の委員の意見を無視して強引に9ブロック会社案を決めてしまう。松永の強引さは懸念されていたことだが、これが功を奏する。
この結果は通産省の永山にとっても首相の吉田にとっても願ったりかなったりだった。GHQは賛成するに決まっている。しかし、次郎は1つ気がかりな点があった。それは案の中に書かれた、電力会社が受け持ちの地域以外にも発電源を持つことができるというものであった。
気になった次郎だったが、このときはまだ当事者ではなかったため、9ブロック会社案の成立を優先した。しかし、その後、これが大きな問題を生むことになる。
全国を9ブロックに分け、各地域に電力会社を作り、発電も送電も配電も一括して管轄するという松永の案は、GHQの許諾も取れ、なんとか実施されることになった。