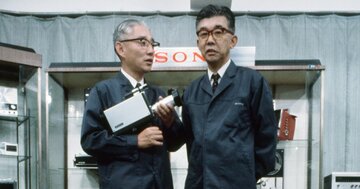次郎の懸念が形となった
只見川電源開発問題
ここで、次郎が懸念していた問題が起こる。只見川電源開発問題である。当時の只見川は豊富な水量を誇り、ダム建設にもってこいの場所だった。
次郎は、ここにダムを造るべく9ブロック分割会社が承認される以前から、根回しをしていた。国家の復興には電力が必要だ。一刻も早くダムを造って電力を供給する必要がある。次郎は外資を積極的に導入して開発しようとしていた。
只見川は9ブロックの電力会社の中では東北電力の管轄になる。しかし、松永は古い水利権の権利書を持ち出して、東京電力の権利であるとして、東北電力の勝手な開発を認めない。松永が案に忍ばせていた「電力会社が受け持ち以外の場所にも電源を持つことができる」が意味を持ってきたのだ。
この後、次郎は東北電力の会長になる。9ブロックの電力会社の社長や会長の人事は混乱を極めた。分割される日発の関係者と、もともとの9つの配電会社の関係者とバランスをとって人事をしようとする動きに対して、松永は、そんなことは無視して、適材適所で人事を決めていく。
すったもんだの挙げ句、当初予定になかった、東北電力の会長職に次郎は就くことになった。
裁判に訴えてきた東京電力への
次郎の言い分とは
次郎は只見川のダム建設に邁進した。一方、ダムの水源に只見川が欲しい東京電力も裁判に訴えて必死に抵抗した。次郎の言い分はこうである。
「一、二十数年前の水利権(中略)なんかを既得権づらして振り回すことの不合理さと馬鹿らしさ。そういう水利権が永代不変のものの様に不動のものなら、目下東京電力で許可済の二、三地点に対しては見返り資金の7億円もの割当もあって、その金は大蔵省のどこかで引き出しを待っているが、未だに工事は不着工、このままでまた二十年か三十年放って置かないと誰が保証するか。(中略)
三、只見川の開発殊に目下の問題地点本名、上田は東北電力で担当することが一番国家的に適当であること。この理由は簡単である。目下進行中の電源開発工事の総キロ数は全国で大略70万キロ。その内東北電力で担当しているものが33万6000キロ、約4割8分」(「おほそれながら」『文藝春秋』1952年10月号)