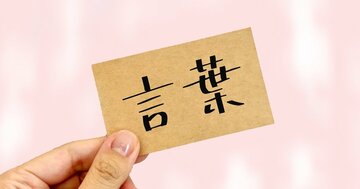この「カスハラ」ケースにおいて
考えるべき3つのポイント
こちらは「デジタル機器に不慣れな高齢者への配慮」を求めているケースです。
注文方法をスマートフォンを使ったモバイルオーダーに統一し、アプリ会員には電子クーポンも提供している「ラ・トラットリア」。しかし高齢の白川はスマートフォンの操作が苦手で、モバイルオーダーシステムを使いこなせずイライラしてしまいます。
確かに高齢の方ほど新しいデバイスやサービスへの慣れが進まない例があるものですが、「ラ・トラットリア」が決めた注文方法や特典の提供方法に対し、自分は苦手だからという理由で注文を店側にやらせるなどの振る舞いをするのは、やはり認めるべきでないはずです。
同情できる面はあるものの、白川には、自分勝手な理由で店側の時間を奪い、「高齢者は来るなということか」など威圧的な言動もあることから、これはカスタマーハラスメントに該当します。
今回のケースでは、特に以下のような点について考える必要があります。
1 「苦手」に対する配慮はどこまで行うべきか
2 白川のような客が店から離れることをどう考えるか
3 「差別」との違いは何か
店側はすべての客の「苦手」に
完璧に配慮することはできない
客も多様であり、何が苦手で何が嫌いか、何を避けたいのかは、人それぞれです。自分の好みに完璧に合い、苦手なことや嫌いなことが完全に排除されている理想の店も中にはあるでしょう。しかし店側は、すべての客に完璧に配慮することはできないわけで、様々な客の最大公約数を見極めて提供するということしかできません。
今回のケースでは、「ラ・トラットリア」は、現在と将来の来店客にとって「モバイルオーダー」は一つの最大公約数だと判断したわけです。ある客は店員を呼んで注文したい、またある客は店員を呼ぶのが苦手で紙にチェックマークを入れて渡す方法がいい、別のある客はモバイルオーダーだと明細もわかるし早くて助かる、逆に白川のようにスマホが苦手という客もいる。