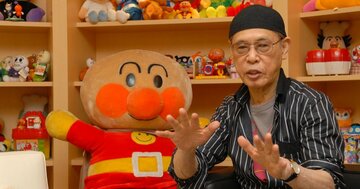だが残念ながら、対立がきれいに解決することなどめったにない。多くの場合、その後も悪戦苦闘が長引く。その最悪の例が塹壕戦だ。両者が戦闘に多くの時間と資金とエネルギーを投じるほど、降参するのが難しくなり、最終的には両者とも負けることになる。
格言のとおり「“目には目を”では、世界が盲目になってしまう」。戦争も、ストライキも、離婚も、そのパターンになることが多い。皆、相手が自分より良い状況になることを恐れて、多くの損失を被ってでも戦おうとする。別居しているパートナーが、「相手が新しい人と幸せになるのが嫌だから、絶対に別れない」と考えるように。
戦いに勝っても、戦争に負けることはある。勝てば相手に屈辱を与えた格好になり、その怒りがブーメランのように自分に返ってくる。第一次世界大戦の終わりに実現した和平は、なぜ長続きしなかったのか?それは、ドイツ国民が、戦争を終結させた条約によって、苛酷な扱いを受けたと感じていたからだ。
多くの場合、戦争終結の決定的な保証となるのは、相手の降伏ではなく、両国間で満足のいく合意に達することである。英国のベンジャミン・ディズレーリ首相がこのようなことを書いている。「人生で、チャンスをつかむべきときを知ることの次に最も重要なのは、優位な立場を放棄すべきときを知ることである」と書いている。
リンカーン大統領が味方に諭した
「敵には友好的な態度を取るべし」
アメリカ南北戦争の最中の演説で、エイブラハム・リンカーンが、南部の反乱軍をかぎりなく友好的な言葉で評した。それに対し、連邦政府に忠実な保守派の古参支持者である高齢女性が激怒した。戦争してるんですよ!と。リンカーンは彼女の反対意見にこう答えた。「敵を友にすれば、それで敵を滅ぼしたことにならないかね?」
こうした敵対的な状況への解決策――すなわち、問題をチャンスに変え、脅威を新たなチャンスに変えること――は、人に対しても有効である。敵(のはずだった相手)と協定を結び、味方につけることができる。相手がこちらに向けていた敵対的エネルギーを、共通の目標に向けることができる。それこそがコラボ戦略の本質だ。二者の違いは忘れ去られ、共通点が重視される。