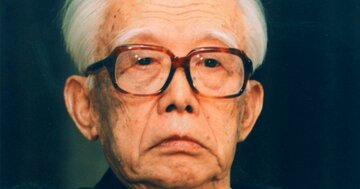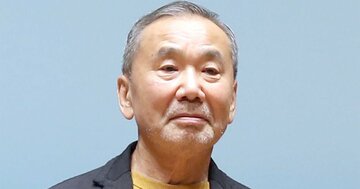GHQの指導に従わず
男女別学を維持した北関東3県
川越女子高校のルーツは、1906年設立の川越町立の川越高等女学校だ。1911年に埼玉県に移管され、戦後の学制改革で新制の川越女子高校となった。現在では、県内有数の歴史と伝統を誇る全日制普通科の女子校として名高い。
実は、埼玉県内には他にも県立の女子高校がある。浦和第一女子高校(さいたま市浦和区)、熊谷女子高校(熊谷市)、春日部女子高校(春日部市)などだ。群馬県(高崎女子、前橋女子など)と、栃木県(宇都宮女子、栃木女子など)も県立の女子高校を持っている。
戦後の教育改革では、GHQ(連合国軍総司令部)が各都道府県の教育委員会を強力に指導した。戦前からある旧制中学校(男子のみ)、旧制高等女学校(女子のみ)については、新制高校への衣替えに当たって男女共学化を推進させた。
ほとんどの都道府県は共学化に踏み切ったが、埼玉、群馬、栃木の北関東3県は、GHQの指導に従わず、新制高校になっても、男子校、女子校を維持させた。それが、約80年たっても変わっていないのだ。
県立高校の男女別学については、埼玉県内から「時代錯誤だ」「いや、男子校、女子校それぞれに存在意義がある」と賛否の議論がかまびすしい。「川女」の卒業生の間では、「男女別学維持派」が多いようだ。
川女の教育では、「学力の向上」と「人格の陶冶」がうたわれている。自主・自律の校風のもと、部活動、生徒会、学校行事に意欲的に取り組む「川女魂」の伝統が息づく。
文部科学省のスーパーサイエンスハイスクールに2006年に指定され、理系教育にも力を入れている。
川女の校内には、教会建築を思わせるような尖塔(せんとう)が目につく「明治記念館」がある。明治末に建てられた木造建築物で、女子教育の拠点としての歴史的価値を認められ、2014年に川越市の指定有形文化財に指定された。
1学年は9クラスで、360人弱だ。3学年全体で、計1050人ほど。女子のみで1000人を超えている大型高校だ。
進路指導としては、「授業が勝負、授業で勝負」だ。1・2年生は授業内容の定着を目的とした補習を、3年生は大学入試を見据えた進学課外補講を、さまざまな教科で実施している。
25年春の大学入試(25年4月入学)では、現役、浪人合わせ、京都大2人、東京科学大6人、一橋大2人、北海道、東北大各2人、埼玉大12人などの合格者を出している。
私立大には、大量の合格者を出している。例年、多いのは立教大で25年春の場合で計109人。立教大のキャンパスは豊島区西池袋にあり、東武、西武線利用で、川女からは通学しやすい点が考慮されているようだ。
早稲田大には38人、慶応大には8人、上智大には33人が合格した。