猪熊建夫
第234回
四国の南西部で、愛媛県の南部にある宇和島市。県立宇和島東高校は、辺境の地にあるが、1876年創立の学校をルーツとする国内有数の伝統校だ。その華麗なる卒業生人脈とは。

第233回
「ほうふ」高校という。山口県の中南部で、瀬戸内海に面した防府市にある県立高校だ。2027年には創立150周年を迎える、全国でも指折りの伝統校だ。その華麗なる卒業生人脈とは。

第232回
東洋英和女学院高等部は、東京・港区にある中高一貫6年制の私立女子校だ。「敬神奉仕」が学院標語で、キリスト教に基づく教育を行っている。1884年に東洋英和女学校として設立され、すでに校歴140年余を誇る。その華麗なる卒業生人脈とは。

第231回
東洋英和女学院高等部は、東京・港区にある中高一貫6年制の私立女子校だ。「敬神奉仕」が学院標語で、キリスト教に基づく教育を行っている。1884年に東洋英和女学校として設立され、すでに校歴140年余を誇る。その華麗なる卒業生人脈とは。

第230回
筑紫丘高校は福岡市南区の丘陵地にある。1学年が11学級という福岡県下一のマンモス高校だ。修猷館、福岡高校と並んで福岡「県立御三家」に数えられる。略称は「筑高(ちっこう)」。その華麗なる卒業生人脈とは。

第229回
日本海に面し、島根県の県庁所在地である松江市。県立松江北高校は旧制松江中学を前身とする伝統校で、2026年に創立150周年を迎えた。その華麗なる卒業生人脈とは。
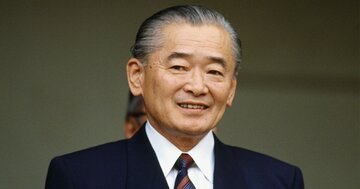
第228回
開成高校は東京・荒川区にある6年制中高一貫の私立男子校だ。1871年創立という伝統校だ。東京大学合格者ランキングで44年連続してトップを誇る日本指折りの進学校だ。
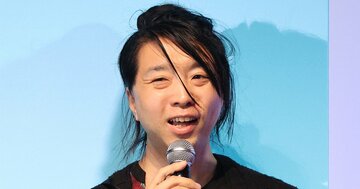
開成高校は東京・荒川区にある6年制中高一貫の私立男子校だ。1871年創立という伝統校だ。東京大学合格者ランキングで44年連続してトップを誇る日本指折りの進学校だ。

第226回
開成高校は東京・荒川区にある6年制中高一貫の私立男子校だ。1871年創立という伝統校だ。東京大学合格者ランキングで44年連続してトップを誇る日本指折りの進学校だ。

宇都宮高校は北関東で有数の進学校だ。全国の県庁所在地にあった旧制一中の栃木県版を前身とする伝統高校で、個性的な文化人や学者を多数、輩出している。

第224回
この数年、難関大学合格者を急増させている神奈川県立の横浜翠嵐高校。自由な校風のもと、横浜という開放的な街のたたずまいを映して、多くの文化人や学者が巣立っている。

第223回
「ずいりょう」高校という。名古屋市の中東部、瑞穂区の文教地帯にある愛知県立高校だ。旧制の愛知五中を前身としており、のびやかな校風だ。個性的な卒業生が巣立っている。

第222回
北海道の中西部、石狩平野の中央に位置する岩見沢市。石炭の集積地であり、陸上交通の要衝として発展した。北海道道立の岩見沢東高校は2025年4月に北海道岩見沢西高校と統合し、新たなスタートを切った。

第221回
奈良市内には1300年ほど前に造られた平城宮跡が残っている。そのすぐ近くに校地があるのが奈良県立の奈良高校だ。前身の旧制中学時代から数えると100年余の校歴がある進学校だ。その華麗なる卒業生人脈とは。

第220回
埼玉県の中部に位置し、江戸時代には川越藩の城下町として栄えた川越市。県立川越女子高校は明治時代に、県内で2番目に設立された高等女学校を前身とする伝統校だ。その華麗なる卒業生人脈とは。

第219回
甲府盆地の北西端に位置する山梨県韮崎(にらさき)市。県立韮崎高校は、学習と部活動との調和を図ることを「一人二芸」と表現しており、「文」と「武」で著名な卒業生を送り出している。その華麗なる卒業生人脈とは。

第218回
兵庫県の県都・神戸市にある県立神戸高校は、各方面で活躍する卒業生がたくさん巣立っており、ネットワークの重厚さを誇る。関西にある公立高校では、五指に入る伝統校だ。その華麗なる卒業生人脈とは。
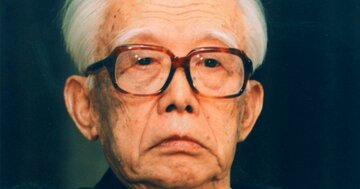
第217回
兵庫県の県都・神戸市にある県立神戸高校は、各方面で活躍する卒業生がたくさん巣立っており、ネットワークの重厚さを誇る。関西にある公立高校では、五指に入る伝統校だ。その華麗なる卒業生人脈とは。
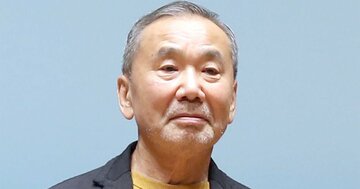
第216回
高度経済成長をけん引した北九州工業地帯。福岡県立小倉高校はその中心・北九州市小倉北区にある。明治時代に設立された旧制県立小倉中学校を前身とする伝統校だ。その華麗なる卒業生人脈とは。

第215回
駒場高校は東京都目黒区にある都立高校だ。旧制の名門・東京府立第三高等女学校を前身としており、女性の著名人を多数、輩出している。その華麗なる卒業生人脈とは。
