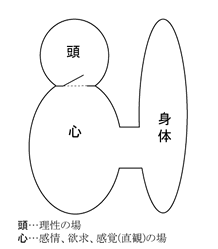「緘黙(かんもく)」とは、ある特定の場面になると、何も話せなくなる状態のことで、「場面緘黙症」とも呼ばれている。
中には、特定の場面だけでなく、家族も含めて、すべての場面において話せなくなる「全緘黙(症)」の状態になる人もいる。
こうした「緘黙症」の人たちの存在は、過去の連載(第108回参照)などでも取り上げたが、それまではまったく知られていなかったにもかかわらず、実は潜在的に多いかもしれないことがわかってきた。
しかも「大人になれば、自然に治る」と専門家から言われてきたのに、何年経っても状況は本質的に変わらない。それどころか、大人になると、学校の問題から離れ、本人の生涯にわたる大きな問題になり得ることも明らかになってきたのだ。
そんな「緘黙症シンポジウム」が、日本特殊教育学会の自主シンポジウムとして、9月1日、明星大学日野キャンパスで開かれ、会場には満席の60人以上の参加者が詰めかけた。
赤ちゃんの頃は静かな「いい子」だったが…
小学生になっても友人と話せない
シンポジウムではまず、「緘黙症」当事者で「かんもくの会」を立ち上げたHさんが講演した。
その中でHさんは、20代半ばの娘が「引きこもり」状態にある母親K子さんの事例を紹介した。K子さんの娘は、いまも働きに出ることができず、毎日自宅で過ごしていて、友人は1人もなく、家族ともまったくしゃべることができない。
娘は、赤ちゃんの頃から極端に大人しい子で、あまり泣くこともなく、知らない人に抱かれても大人しく抱かれていた。また、親の言うことは素直に聞く、手のかからない「いい子」だった。
小学校では、友人と遊んだりおしゃべりしたりするのが苦手で、休み時間は本を読んだり、1人で図書室にいたりした。
社会科見学でバスの席を決めるのに、仲のいい子同士で座れるように決めたら、1人残された。自分から声をかけることができない娘は、誰かが「一緒に座ろう」と言ってくれるのを待っていたのではないか、とK子さんは振り返る。取り残されたようでつらかったのだろう。先生が「誰と座りたいの?」と尋ねると、泣いてしまった。
国語の音読で、先生から「もっと大きな声で読みなさい」と注意され、何度やり直しさせられても、大きな声は出なかった。