池上正樹
スマートフォンゲームなどの長時間利用は「ひきこもり」の原因になる――。メディアなどでは、こんな言説が当たり前のように報じられている。だが、この問題を専門とする筆者は、スマホゲームなどがひきこもりの直接的な原因になった例を見たことがない。それどころか、ひきこもり状態にある本人にとっては、スマホに触れている時間が「社会での苦しみ」を紛らわせる貴重な時間になっている場合もある。「ゲーム・動画=悪」という誤解を解くため、かつてスマホゲームを長時間利用していたひきこもり経験者などの体験談を紹介する。
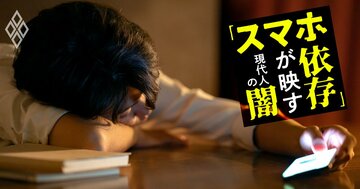
2022年3月、大阪府泉南市で中学1年生(当時)の少年が自殺した。母親の手記には、少年が同級生から「少年院帰り」などとからかわれ、担任に助けを求めたことや、教員が「誰が言ったか分かるまで学校側は指導しない」といった趣旨の発言をしたことなどが記されている。この問題の真相を究明すべく、泉南市長の附属機関「泉南市子どもの権利条例委員会」が検証を行った。しかし検証後、泉南市の山本優真市長は委員会からの報告書の受け取りを拒否した。31歳の山本市長は“全国最年少市長”として注目を集める人物だが、なぜ不可解な対応を取ったのか。

報道の影響などで、ひきこもりというと「若年男性ばかり」というイメージを持つ人も多いだろう。だが、令和の時代では必ずしもそうではない。若い女性をはじめ、恋人・配偶者・子どもがいる人など、老若男女さまざまな人がひきこもっているのが現実だ。加えて、ひきこもり当事者の中でも、コロナ禍の到来によって家族関係や精神状態が好転した人・悪化した人が二極化している。当事者が多様化する中、どんな支援が適切なのか。

元AKB48の高橋みなみさんや、髭男爵の山田ルイ53世が参加する「ひきこもり支援」イベントが厚生労働省の主催で開催された。精神科医などの専門家が主体だった従来のイベントからガラリと変わり、報道陣からは「本当に厚労省主催なのか?」と確認があったほどだ。そのイベントで語られたことをレポートする。

12月23日、ひきこもり当事者らの団体が全国初となる「ひきこもり人権宣言」を発表した。その背景には、いまだに根深く残る「ひきこもる」という行為に対する偏見がある。「引き出し屋」と呼ばれる強引な手法を用いる民間支援業者と、その様子を放映するテレビなどのメディアが今も続ける、ひきこもる本人に対する人権侵害を防がなくてはならない。
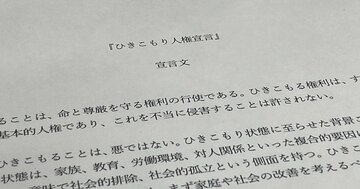
1686人の調査に基づく日本初の「ひきこもり白書」が出版された。アンケートによる定量的な分析に加えて、約46万字に上る自由記述の引用もあり質的な分析が盛り込まれている。さらに、年末年始の緊急アンケートも特別収録。コロナ禍が猛威を振るったこの1年間にひきこもり状態になった、「新たなひきこもり層」の実態にも迫っている。同書が光を当てたひきこもる人の実像を紹介したい。

ひきこもる長男とその家族の姿を描いた作家・林真理子さんの新刊『小説8050』(新潮社)が発売され、話題になっている。「ひきこもり」や、80代の親がひきこもり状態にある50代の子の生活を支える「8050問題」、さらに「学校のいじめ」をテーマとして扱い、発売前に重版が決定するなど大反響。発行部数は6月23日現在で累計11万7000部を超えた。ひきこもり者の数は全国で推計約115万人に上り、当事者親子の高齢化の課題が顕在化していっている。インタビュー前編では、著者の林真理子さんに『小説8050』が生まれるまでの経緯や小説のリアルさの秘密などについて聞いた。

ひきこもる長男とその家族の姿を描いた作家・林真理子さんの新刊『小説8050』(新潮社)が発売され、話題になっている。「ひきこもり」や、80代の親がひきこもり状態にある50代の子の生活を支える「8050問題」、さらに「学校のいじめ」をテーマとして扱い、発売前に重版が決定するなど大反響。発行部数は6月23日現在で累計11万7000部を超えた。ひきこもり者の数は全国で推計約115万人に上り、当事者親子の高齢化の課題が顕在化していっている。インタビュー後編では、著者の林真理子さんに『小説8050』を書いた今、ひきこもる人やその家族に伝えたいことや、新作に対する熱い思いの丈などを聞いた。

東京都は、行政機関や民生委員などを対象とした「ひきこもりに関する支援状況等調査」を初めて実施し、高齢者の介護や医療などを担う地域包括支援センターの92.4%(回答数256件)が、担当地区に「ひきこもりの状態」の人がいることを把握しているという衝撃的な結果をこのほど公表した。そのうち、毎月新たに「中高年ひきこもり層」を把握していると答えた機関は3.9%(回答数10件)に上った。80代の親がひきこもり状態にある50代の子の生活を支える「8050問題」の実態を初めて示したエビデンスとしても注目されそうだ。

コロナ禍に起因する解雇や雇い止め(見込みを含む)の人数は、累計10万人を超えた。2008年に起きたリーマンショック時にも派遣切りや雇い止めが社会問題となり、その憂き目に遭った結果、「大人のひきこもり」となる人々が多数生まれた。「コロナ解雇・雇い止め」の構図もそのときと同じであり、今後はリーマンショックをはるかに超える規模で新たな「ひきこもり層」が出現するだろうと筆者は予感する。

日本が、英国に次いで世界で2番目となる「孤独・孤立対策担当大臣」を任命したことをご存じだろうか?「何それ?」という人にぜひ知ってほしいことを、24年にわたって1000人超の「ひきこもり」状態にある人たちにインタビューを行ってきた筆者がお伝えしたい。

30代後半の元ひきこもり男性が2020年12月末、ようやく就職した清掃会社を退職した。適切な装備品の用意がないまま、会社が危険な新型コロナウイルスの消毒の依頼ばかり受けるようになった。そして、過剰勤務を強いられる中で終え尽きて体調を崩し、「もう無理」と会社を後にしたのだ。男性は「就労意欲があっても、会社が利益を優先して従業員の健康に配慮しない環境で働き続けるのは難しい。社会との乖離を感じた」と明かしている。

コロナ禍が猛威を振るった2020年4〜12月の間、窓口に寄せられたドメスティックバイオレンス(家庭内暴力、DV)の相談件数が過去最多になった。その中には、あまり知られていないが、妻による暴力に苦しむ夫のDV被害も含まれている。今回は、妻によるDV被害で職も趣味も失った45歳の男性が絶望した理不尽さをお伝えする。

世の中がコロナ禍に見舞われる中、この年末年始もまた、「世の中に見捨てられるのではないかとすごく不安」「このままでは1人で生きていけない」「助けてください」などといった相談が、筆者の元に数多く寄せられた。その中の一つに、30代後半の男性Aさんからの相談があった。小学校時代に遭ったいじめの後遺症に今も苦しめられているという。

11月末から12月前半にかけ、NHKがひきこもり関係の番組13本を一挙に放送した「#こもりびと」プロジェクトが大きな反響を呼んでいる。このプロジェクトでは、筆者も番組づくりの一端を担わせていただいた。そこで、まだ余韻の冷めやらぬ「#こもりびと」のプロジェクト発案者である、NHK報道局の松本卓臣チーフ・プロデューサーに、プロジェクトが生まれたいきさつなどの話を聞いた。

農林水産省の事務次官だった父親が、東京都練馬区の自宅でひきこもり状態にあった当時44歳の長男を刺殺したとして、世の中に大きな衝撃を与えた事件。その控訴審の被告人質問が12月15日に行われた。弁護団は、正当防衛に当たるとして無罪を主張。これに対して、「ある風潮」がまかり通るようになるかもしれない恐怖を語ったのが、発達障害の自助グループの代表だ。その恐怖とはいったい何か。

兵庫県豊岡市で50代の三男が、同居する90代の母親と無理心中したとみられる事件が起きた。引きこもりや「8050問題」に認知症、障害、貧困…。複合的な要因で生活が危機的状態にある「困難家族」の状況が悲劇につながった象徴的事例だ。その当事者たちが見ていた心の風景とは、どのようなものだったのか。

引きこもり状態にある本人から、助けを求める1通のメールが筆者の元に届いた。「食べ物を玄関に取りに行くのもつらい」「死ぬのが怖い」と語るその人は、「引きこもらされている」といえる状況に陥っていた。悲痛な叫びと、その実態を知っていただきたい。

引きこもり当事者の思いから生まれたアイデア「ひきこもり大学」がこのほど本になった。ひきこもり大学とは、ひきこもった本人らが自らの意思で講師となって、親や応援者などに向けて自分の経験や知恵、見識などを講義するという、従来の上下関係が逆転する不思議なキャンパスだ。

安倍政権の肝いり政策だった就職氷河期世代支援プランが2020年度からスタートした。しかし、地方自治体の担当者らに取材をしてみると、その実態は事実上の「開店休業」であることが分かった。コロナ禍による解雇や雇い止めは6万人を超えたが、コロナ時代は、リーマンショックをはるかに超える規模で、今後引きこもり層が顕在化してくるだろう。
