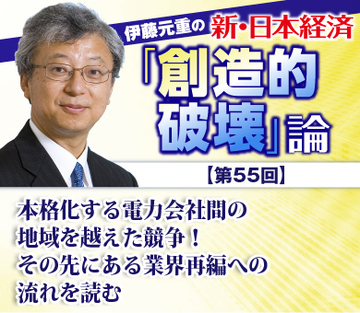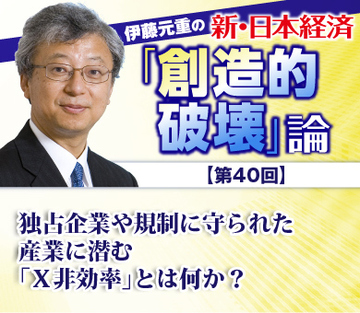総括原価方式の限界
電力料金は「総括原価方式」という規制料金となっている。正確に言えば、近年の大口小売の自由化で大口の電力利用者への電力料金は競争料金となっているが、一般の国民や商店などの小口電力は規制料金である。
総括原価方式とは、単純化して言えば、コストに一定の利益を乗せた料金を規制料金として認可するというものである。こうした料金制度を経済学では「平均費用価格形成原理」とも言う。要するに、費用に見合った料金を認可し、それ以上に料金を高くする自由を認めないということだ。
勝手に料金を上げることは認めない、という料金規制となっているのは当然だろう。電力会社は地域で独占的な地位にある。地域の住民はその電力会社から電力を購入するしかない。仮に料金を大幅に引き上げられても、他社の電力に切り替えるという自由度がないのだ。だから料金がむやみに引き上げられないように料金の上限規制がある。
総括原価方式は、料金に上限が課されるだけでなく、費用に一定の利益を乗せた料金が認められるということでもある。これは電力会社の経営を成り立たせるための措置である。
「言い値」で費用を認めていいのか
電力事業は膨大な固定費がかかるビジネスである。発電装置、送電・配電の施設など、電力供給には膨大な経費がかかる。それをきちっと料金でカバーできるように、電力供給のための平均費用に一定の利益を乗せた電力料金を認可するのだ。ちなみに平均費用とは、固定費なども含めたすべての費用で見て、単位電力供給当たりにかかる費用のことである。
費用に見合った料金を認めようというのは、何の問題もないように見えるかもしれない。ただ、ではその費用とは何かという問題が残る。電力会社が効率の悪い経営を行って費用が無用にかさんでも、それに利益を上乗せした料金が認められるのであれば、社会的に見て不要に高い料金を容認することになるからだ。
もちろん、電力会社の料金申請を審査する側(政府)も、電力会社の費用の内容を徹底的に調査して、余分な費用は認めないとの対応をとることはできる。ただ、電力供給のためのコスト査定は複雑なものである。政府といえども電力ビジネスの外部にいる人たちが正確な評価と判断ができるかどうかはわからない。