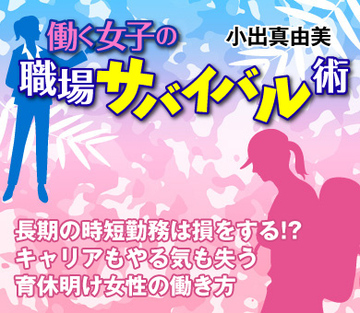2013年末、『スコールの夜』で第5回日経小説大賞を受賞した際は現役財務省キャリア官僚ということでも話題になった芦崎笙さん。同作刊行以来、『家族計画』『公器の幻影』と、すでに3作を上梓されています。つねづね「制度と現実のひずみをフィクションの力を借りて可視化したい」と話されているテーマ設定の背景や書くことに込めた思いを聞きました。
100%勝って終われるわけではない仕事のリアルを描いた
ーー日経小説大賞を受賞された『スコールの夜』は都市銀行で雇用機会均等法第一期生としてバリバリ働く主人公・吉沢環の複雑な心情がリアルに描かれていることとともに、書き手が現役キャリア官僚ということでも大変話題になりました。周囲の反応はいかがでしたか。
 日本経済新聞出版社、1500円税別
日本経済新聞出版社、1500円税別
色んな感想がありましたけれども、職場の人たちからは環の行動や気持ちが実感としてわかる、という声が多かったです。一方で、ストーリーの終わり方については賛否が分かれました。これは続編があるのかと問われたり。結局、読後感がなんとなくすっきりしないということだと思うのですが、良くも悪くも私の小説の思いはそこにあって、狙い通りとも言えます。
というのも、仕事というのは100%勝って終われるわけではないのが現実ですよね。われわれ公務員の仕事でも、利害関係者の調整が付きもので、思ったとおりの理想的な制度として仕上がることはほとんどなくて、100を目指しても80とか70の出来で着地します。でも、その歩留まりをいかに上げていけるかが頑張りどころだと思っていますし、腐らずにまた明日から頑張ろうというのが我々サラリーマンなので(笑)、その思いが出たのかな。敵を倒したり破滅したりといった分かりやすい終わり方でなく、すっきりしない中で苦労しながら悩みながら頑張っているというストーリーとして描けたのかなと思っています。
ーー2作目は、家族制度や夫婦制度のありかたを問う物語、『家族計画』でした。常に「制度と現実のひずみをフィクションの力を借りて可視化していきたい」と仰っていますが、ここで描かれたのも制度と葛藤する個人でした。
家族なり男女なりについて、その心情だけでなく制度の変容と絡めて書いてみたかったんです。
家族制度も夫婦制度も、今すごく動いていますよね。現実のほうが進んでいる面もあって、日本でも同性婚が自治体の制度として出始めたり、事実婚を法律婚と一緒に取り扱うことが最高裁の判例として出されました。夫婦別姓や、代理母のような生殖医療の話などいろんな問題が出てきて、家族や夫婦をとりまく制度が変わり始めている。今後さらに、家族や夫婦の在り方や制度がどう変化していくのか関心を持っていたので、小説を書き始めた頃からずっと書いてみたいと温めてきたテーマでした。
『家族計画』の読まれ方にはすごく幅があって、自分なりにストーリー自体ははっきり書いたつもりなんですが、男女や年齢や就労の有無、子どもの有無など、読者の方の気持ちなり立場によって受け止め方がずいぶん違いました。
ーー主人公の俊平やその家族、彼に子種だけ欲しいと頼む翔子など、登場人物の心の機微が繊細に書き込まれている印象ですが、かなり取材されたのですか。
いえ、ほかの作品も含めて参考文献など資料を読むことはあっても、取材はあまりしないですね。普段、周囲の人の思いはさまざま耳に入ってきますし。
ただ『家族計画』はできあがった段階で、某大企業で取締役を務める友人の女性に読んでもらって、意見を聞きました。随分議論して、直した部分もかなりあります。ずっと1人で書いてると受け止め方とか分からなくなりますから、非常に参考になりました。