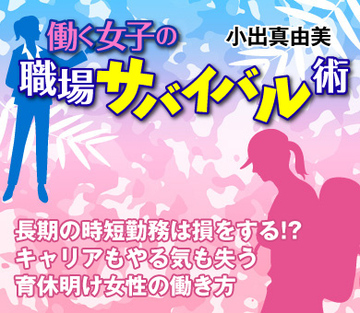ーー3作目の『公器の幻影』は、野心と正義のあいだで揺れる新聞記者・鹿島の姿を通して、マスコミの在り方を問う作品です。お仕事柄、記者というのは身近な存在なので良い面も悪い面もよくご存じですよね。
 芦崎笙(あしざき・しょう) 1983年、東京大学法学部卒業後、大蔵省(現財務省)に入省。税務署長、大使館、金融庁、内閣官房などの勤務を経て、財務省大臣官房審議官。2013年、都市銀行で初の本店管理職となった女性を主人公とした小説『スコールの夜』で第5回日経小説大賞を受賞する。近著に『家族計画』(日本経済新聞出版、2015.5)、『公器の幻影』(小学館、2015.6)。
芦崎笙(あしざき・しょう) 1983年、東京大学法学部卒業後、大蔵省(現財務省)に入省。税務署長、大使館、金融庁、内閣官房などの勤務を経て、財務省大臣官房審議官。2013年、都市銀行で初の本店管理職となった女性を主人公とした小説『スコールの夜』で第5回日経小説大賞を受賞する。近著に『家族計画』(日本経済新聞出版、2015.5)、『公器の幻影』(小学館、2015.6)。
取材を受ける機会は多いですからね。愛憎入り交じる部分はありますが、基本的には「愛」が強いです(笑)。私自身も実は記者を志望して、公務員試験と両方受けて、内定を頂いたところもあったんです。そのとき会った人が魅力的だったり縁があって、たまたま財務省のほうに入ったのですが。
ーー今日日、あまり「社会の公器」という言葉も聞かなくなりました。
確かに今や、新聞が「社会の公器」とは誰も思っていないし言わないかも(笑)。でも、中身を書く前からこの『公器の幻影』というタイトルは決めていたんです。帯にある「正義か、信条か、功名心か」というテーマも。出版社の方からも当初、このタイトルは堅いと言われたのですが、別案も提示してみたら結局こっちでいきましょうと決まりました。
ーーテーマに対する思いが詰まったタイトルですね。
主人公・鹿島のような遊軍記者をやっている昔からの知り合いからは、非常に面白いしよく描けていて、これを学生さんが読んだら就職先として再び人気が出るんじゃないかとも言ってくれました。新聞記者という仕事の厳しさや醍醐味みたいなものを好意的に描いていると思ってくれたようですね。
ーー制度と現実のひずみといえば、日本の国債や財政問題といったお仕事に近い問題も小説テーマとしてはあるような…
まあ、その場合のひずみは金儲けに直結してますよね。色んな悩みや思いや行動につながるというよりは…。それに、今の仕事に近すぎるテーマで書くことは勤めている以上ありえません。
もやもやとしたものを可視化するというフィクションの意味
ーー過去のインタビューを拝見すると、20数年働いてきたなかで溜まった澱が閾値を超えるようにして8年前から小説を書き始めたそうですね。ただでさえ本業が激務なのに小説を書くという非常に大変な作業は、その澱の浄化につながっておられるという感覚ですか。
うーん…溜まっているものを自分でもう一度見つめ直して形にするという作業は、フィクションだからこそ伝わる部分ーーつまり、もやもやとしたものを立体感のあるかたちで提示して可視化するという意味はおそらくありますよね。ただ、それを世に突きつけて何になるのか、意味があるのか、と問われると、これはフィクションを書く宿命かもしれないけど一番しんどい部分でもあります。
論文や実用書なら自分のノウハウや経験を伝授するなど、はっきりした目的があるけれども、フィクションの場合はそれがない。もちろん、かたちにしてみると様々な受け止め方や反応があって、それが励みや見返りでもありますが、出すまでは、こんなストーリーをでっちあげて(笑)社会にとって何の意味があるんだろうという感覚を常にもってますね。