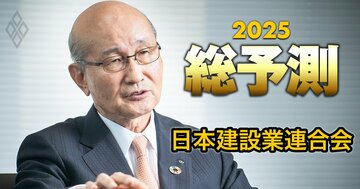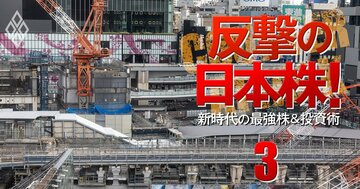Photo:Bloomberg/gettyimages
Photo:Bloomberg/gettyimages
受注時採算が急激に回復したことで、今後数年間にわたり業績拡大が期待できる建設セクター。果たして今回の景気サイクルの勝ち組はどこか。「談合」がなくなったことで経営力が問われる局面に突入しているが、業界の序列変化はあるのか。特集『5年後の業界地図2025-2030 序列・年収・就職・株価…』の#8では、大手ゼネコン4社の動向に加えて、M&Aで規模を拡大する企業や独自戦略で業績を伸ばす企業など具体名を挙げて業界の5年後を予測する。(ダイヤモンド編集部 篭島裕亮)
受注時採算が改善しており
27年度までは視界良好
頂点に君臨するスーパーゼネコン5社だけでなく、準大手や中堅企業も業績が急回復している建設セクター。外部環境の影響を受けやすい景気敏感セクターではあるが、多くのアナリストが今後2年、3年は業績拡大が続くと予想している。
大和証券の寺岡秀明チーフアナリストは「国内の建築事業が堅調だ。ゼネコン各社の受注時採算は2022年度から回復に転じ、23年度、24年度と大きく回復。抱えていた不採算案件も順次竣工を迎えるため、少なくとも27年度ごろまでは利益率が改善していく局面にある」と解説する。
株価も23年以降は下値を切り上げつつ、右肩上がりが続く。SMBC日興証券の川嶋宏樹シニアアナリストは「利益率の改善は織り込み済みだが、事前予想よりもさらにいい数字が出ている。円高やトランプ関税などの影響も相対的に小さい。当面は崩れそうにないというのがメインシナリオ」と指摘する。
川嶋氏は建築利益率の改善の要因として、(1)受注時採算改善、(2)資材高の影響縮小、(3)工事損失引当金計上の反動の3点を挙げる。
「大手50社の建設工事受注総額を見ると、製造業の設備投資がバブル期以来の水準まで拡大。特に半導体関連の投資がけん引している。空調工事など設備工事会社の不足がボトルネックになっていることも、全体の市況を押し上げている」(川嶋氏)
ただし、前述のように建設は景気の循環的な変動を受けやすい業種である。この空前の好景気の賞味期限がいつなのかは気になるところだ。
また、建設セクターは建設業就業者数の減少トレンドが続き、就業者は55歳以上が3分の1を占めている。週休2日制の導入など働き方改革が進むことで人手不足が深刻化して、労務費が高騰するリスクも指摘されている。
次ページでは建設セクターに吹く三つの追い風や各社の事業戦略、さらに見え隠れするリスクについてトップアナリストが分析。
建設セクターは戦前から頂点に君臨するスーパーゼネコン5社が圧倒的に強い一方、「談合」がなくなったことで経営力がシビアに問われる戦国時代に突入しつつある。
追い風を生かしてゼネコン大手5社に迫る企業はあるのか。また、その中での序列はどうなっているのか。ニッチ分野で躍進が期待できる企業についても具体的に名前を挙げて紹介する。