スズキ
創業者の名字
関連ニュース
#4
第二のマレリも!?自動車業界109社の倒産危険度が5軸チャートで一目瞭然!金利上昇、インフレに弱いのは?
ダイヤモンド編集部,清水理裕
自動車部品大手のマレリホールディングスが今年6月に倒産したことは、自動車業界の苦境を強く印象付けた。半導体不足など、厳しい状況は依然続く。来年、第二のマレリは現れるのか?金利上昇、インフレ耐久度といった独自の試算に加え、身の丈を超えた有利子負債を抱え込んでいないかどうかなど、五つのチェックポイントで自動車業界を総合的に評価。五角形のレーダーチャートで、その診断結果を分かりやすく見せた。なお、この記事は無料公開(要会員登録)。#3の完全版ランキングとセットで読むと、よりグラフィカルに自動車業界で危険な会社の状況をつかむことができる。

#4
業績上方修正「上振れ」株ランキング【80社】再上振れも狙える?23位SUBARU、1位は?
ダイヤモンド編集部,篭島裕亮
期初予想に対する「上方修正率」でランキング。「来期の市場予想が増益」など複数の条件を付けたが、リオープニング関連や円安の恩恵を受ける自動車など、業績モメンタムが強い企業がそろった。企業側からすると「下方修正だけは避けたい」というのが本音。期中の早い段階での上方修正は業績に対する強い自信の表明の可能性が高く、「再上振れ」も期待できるはずだ。
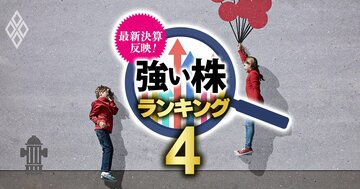
年収が高い会社ランキング2022【愛知除く中部地方・全200社完全版】
ダイヤモンド編集部,松本裕樹
上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い会社ランキング2022【愛知除く中部地方・全200社完全版】」を作成した。全200社の顔触れは?

#4
トヨタが恐れる日野自動車「最悪シナリオ」、出資引き揚げはある?再建案を大胆予測
ダイヤモンド編集部,今枝翔太郎
日野自動車では、不正の責任を取る形で生え抜きの役員が辞任したが、トヨタ自動車出身の小木曽聡社長はその座にとどまった。この処分について、「トヨタが引き続き日野の面倒を見るという意思表示」との声が上がる一方、「今後トヨタの撤退もあり得るのでは」との臆測も飛び交う。日野はこれからどのような運命をたどるのだろうか。トヨタとの関係性に焦点を当てることで、日野の再建シナリオを大胆に予測する。

ホンダの韓国LG・米GMとの提携強化が映す、自動車業界「大変革」の衝撃
真壁昭夫
ホンダは、米国のGMと韓国のLGグループとアライアンスを組んで、「100年に1度」と呼ばれる自動車産業の大変革に対応しようとしている。背景にある「CASE」のインパクトは大きい。バッテリー調達能力の向上、自動運転技術などソフトウエア開発力の強化、搭載点数の増える車載用の半導体開発のために、世界の大手自動車メーカーは合従連衡や異業種との提携を強化しなければならない。

日野自動車のエンジン不正が招く商用車再編の実現度、盟主トヨタの思惑は
佃 義夫
日野自動車はエンジン不正について調査報告会見を開き、新たに不正の範囲が拡大したことを発表した。日野自は現在、一部の製品の出荷を停止しており、業績の大幅な悪化は必至だ。

トヨタが「流儀を曲げて」つかんだ過去最高決算、自動車“三重苦”は続く
ダイヤモンド・アナリティクスチーム,濵口翔太郎
コロナ禍が落ち着き始めたことで、市況も少しずつ回復しつつある。しかしビジネス界では、コロナショックから立ち直った企業と不調から抜け出せない企業とで明暗が分かれている。そこで、上場企業が発表した直近四半期の決算における売上高を前年同期と比べ、各業界の主要企業が置かれた状況を分析した。今回はトヨタ自動車、ホンダなどの「自動車」業界5社について解説する。

スズキがインドでEV投資を先行する理由、「ポスト修体制」に最初の試練
佃 義夫
スズキのインド子会社マルチ・スズキは5月13日、約1800億円を投じて北部ハリヤナ州に新工場を建設することを発表した。3月にはグジャラート州に電気自動車(EV)と車載電池工場の新設も決めており、合計で約3500億円を投じる。

ダイハツ新型「アトレー」、仕事に遊びに使い尽くせるマルチBOX【試乗記】
CAR and DRIVER
アトレーはラゲッジスペースを“もうひとつの部屋”として使えるボクシーバン。楽しみ方はユーザーしだい。エンジンはターボ、骨太な作りはプロユースを思わせる。

静岡銀と名古屋銀の電撃提携の舞台裏、従来の合従連衡と違い「画期的」といえる理由
ダイヤモンド編集部,新井美江子
4月27日、静岡銀行と名古屋銀行が包括業務提携を結ぶと発表した。地方銀行業界では合従連衡の動きが活発化しているが、実はこの「静岡・名古屋アライアンス」は、従来の地銀の提携とは意味合いがだいぶ違う。両行が狙った最大の“果実”とは何か。静岡銀、名古屋銀の提携の舞台裏について明かす。

スズキ・新スペーシアギア、SUV感アップ!遊び心充実の超ハイトワゴン【試乗記】
CAR and DRIVER
スペーシア・シリーズは、2021年12月に一部仕様変更を行った。今回はSUVルックのギアを連れ出して、改めてこのKスーパーハイトワゴンの魅力に迫ってみた。

トヨタは増益、スバルは減益予想…軒並み四半期減収の自動車業界で分かれた「明暗」
ダイヤモンド・アナリティクスチーム,笠原里穂
コロナ禍が3年目に突入し、多くの業界や企業のビジネスをいまだに揺さぶり続けている。その対応力の差によって企業の業績は、勝ち組と負け組の格差が拡大している。そこで、上場企業が発表した直近四半期の決算における売上高を前年同期と比べ、各業界の主要企業が置かれた状況を分析した。今回はトヨタ自動車、ホンダなどの「自動車」業界5社について解説する。

スズキ新型アルト、軽快な走りでキュート&低燃費!【試乗記】
CAR and DRIVER
最新アルトは愛らしいスタイリングの持ち主。マイルドHVを設定しクラストップのWLTCモード燃費27.7km/Lを誇る。安全装備も充実した新型は要注目である。

#11
三菱商事、トヨタ、東京海上…「金利高・資源高・円安」で業績上ブレが狙える割安王道株12選
ダイヤモンド編集部,篭島裕亮
株式市場の割安セクターの代表格に「自動車」「金融」「総合商社」がある。だが、これらの業種の中には、資源高、円安、金利高という大きな追い風を受けて、業績上振れや増配継続を狙える企業も目立つ。ただの割安にとどまらない、来期以降も成長を見込める割安グロース株を探した。

#10
トヨタ社長に食い込む条件は「2つの苦悩」への理解、“章男人脈”による出資・提携の成果は?
ダイヤモンド編集部,千本木啓文
トヨタ自動車の豊田章男社長は、強力なリーダーシップで、他の自動車メーカーやIT企業などとの提携を次々と打ち出してきた。だが、トヨタの創業家出身という理由から学校でいじめられたり、社内で腫れ物に触るような扱いを受けたりした章男氏は元来、猜疑心が強い性格とみられる。他社との協業は、章男氏と提携先の経営者との信頼関係がなければ成果が出にくい。八方美人とやゆされることもあるトヨタによる “仲間づくり”の実態に迫る。

自動車部品大手に広がる信用不安、「3重苦の実態」を東京商工リサーチが解説
増田和史
自動車メーカーの業績回復が鮮明となる一方で、部品メーカーの経営悪化は深刻な状況にある。こうしたなか、自動車部品大手のマレリ(旧カルソニックカンセイ)が私的整理の一つである事業再生ADR(裁判以外の紛争解決)を前提に金融機関との調整に入るなど、コロナ禍を発端に事業環境の悪化が際立ってきた。部品メーカー各社は生き残りをかけた正念場を迎えている。

予告
トヨタ「創業家支配」の知られざる真実、世界No.1自動車メーカーを蝕む病巣の正体
ダイヤモンド編集部
トヨタ自動車が絶頂期を迎えている。半導体不足による減産にもかかわらず2022年3月期決算は過去最高益水準で着地する見込み。業績堅調とEV(電気自動車)大攻勢プランのぶち上げで時価総額40兆円を射程圏内に入れ、名実共に世界一の自動車メーカーに躍り出た。だが一方で、王者らしからぬウィークポイントが現場で一気に噴き出し始めている。車検不正、度重なる減産修正、販売店個人情報の不適切使用、ミドル人材の流出――。不始末を誘発する「組織の病巣」の正体とは。絶対王者の急所に迫る。

#13
インフレ「採算悪化」ランキング【製造業50社】2位東洋水産、ワースト1位は?
ダイヤモンド編集部,竹田孝洋
資源、エネルギー、穀物などの価格高騰は幅広い業種のコストを増加させる。今回は、原価率上昇度ランキング製造業編上位50社をお届けする。穀物価格の上昇で製造コストが上昇した食料品の会社が上位を席巻した。足元の食料品価格の値上げもこうした苦境を反映したものである。

#6
自動車7社の「コスト上昇痛手度」を分析、2位スバル、ワースト1位は?
ダイヤモンド編集部,杉本りうこ
日本の基幹産業、自動車。この業界が見舞われているのは、半導体飢饉だけではない。世界的に広がる鋼材高、素材高が、日本の自動車メーカー各社をどれだけむしばんでいるのか。メーカー別に「痛手度」を実額で公開する。

スズキ新型ワゴンR、笑顔溢れるスタイル重視のユーティリティモデル【試乗記】
CAR and DRIVER
“笑顔”のクルマが誕生した。ワゴンRスマイルはスタイル重視のユーティリティモデル。リアドアは便利なスライドタイプ。主要グレードはマイルドハイブリッドだ。
