花王は創業以来132年の長寿企業でありながら、過去最高益を6期連続で更新。増配記録は29期連続という日本一の実績を誇る好業績企業だ。だがグローバル化の進展に伴い、これまでの「殻」を破って世界での勝ちパターンをいかに築き上げるかという、大きな課題に直面している。2012年に社長に就任した澤田道隆氏は、21世紀に適合した花王の経営基盤を確立するため、改革を推し進めてきた。画期的な技術革新を契機に、グローバルでの存在感を高め、変化を先導する企業となっていくためには、「カギを握るのはESG(環境・社会・ガバナンス)経営だ」と断言する。その真意を語ってもらった。

ジェンパクト流DXの核心
ゼネラル・エレクトリック(GE)は1997年、GEキャピタルの世界各地のビジネス部門にビジネスプロセス・サービスを提供するGEキャピタル・インターナショナル・サービシズを発足させた。これがジェンパクトの始まりである。その後、金融部門を超えてGEグループ全体にサービスを広げ、2005年1月にスピンアウトを果たす。以来、GEのみならず各国のグローバル企業に向けて、最先端のデジタルソリューションを活用したトランスフォーメーション・サービスを提供してきた。「終わりなき変革と革新」をモットーとしてきたGEのDNAを受け継ぐジェンパクトに、DXの要諦を聞く。

AI監査は経営に何をもたらすのか計り知れない、そのインパクトを考察する
AIバブルの行く末を危惧する声は多いが、目的と手段を取り違えない限り、「使えるAI」は実現する。なかでもルールに基づき、秩序立ってロジカルに判断し処理する領域も多い会計監査は、AIやロボットとの相性がよい。 では、AI監査の目的とは何か。あずさ監査法人では、「社会・経営に資するインサイトを導き出す」ことだととらえている。企業活動のすべてをカバーする会計監査だけに、その効果はガバナンス向上に留まらず、課題をいち早く解決して、強みに転換することにもつながる。 それゆえ経営者には、AI監査に期待すると同時に、コミットして監査を活用していくという意識を持ってほしい。

国税庁、国土交通省、法務省……。国の行政機関の約8割に及ぶ省庁で、3700人にも上る障がい者雇用数の水増しが明らかになったのは2018年10月のこと。障がい者雇用を率先して推進する立場であるはずの行政機関において、大規模かつ長期間の不正があったことは、社会に大きな衝撃を与えた。しかし、その背景には制度そのものが抱える矛盾がある。誰もが働きやすい未来のために、今、何が求められているのだろうか。障がい者雇用研究の第一人者である中島隆信氏は、障がい者と企業の両者が抱える課題への深い洞察から「みなし雇用」の制度化を訴えている。障がい者雇用を「社会的責任」という名のコストから解放し、雇い雇われやすい関係を生みだす仕組みについて、本インタビューで明らかにする。

デジタル・トランスフォーメーション 成功の核心
このままでは、日本はデジタル後進国になりかねない——。そのような危機感から、まるで示し合わせたかのように、産官学揃って「デジタル・トランスフォーメーション」(DX)の必要性を訴え続けている。おかげでムーブメントにはなったが、真の目的である「変革」は、多くの組織で道半ばである。上場企業の執行役員2万人を読者に抱える『ダイヤモンドクォータリー』誌では、来たる9月20日に「日本企業のデジタル・トランスフォーメーションを考える」と題したカンファレンスを開催する。それに先立ち、同カンファレンスの前半に登壇される2人の変革プロフェッショナルに、DXを加速し、組織全体へと拡大し、トップの期待を上回る成果を実現するための心得、ノウハウやドゥハウについて聞く。
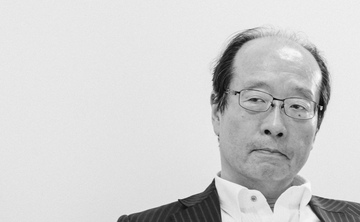
作田久男氏は、創業家以外から初めてオムロン社長に就任したサラリーマン出身の経営者である。現実を直視し本質に鋭く斬り込む行動力は、自分の生きざまを貫き続けてきた人だけが持つ、いぶし銀の迫力に富んでいる。そこには何かにおもねる忖度はない。あるのは、時代の変化を見据え、常に問い続けてきた「自分の存在価値」そのものだ。

作田久男氏は、創業家以外から初めてオムロン社長に就任したサラリーマン出身の経営者である。現実を直視し本質に鋭く斬り込む行動力は、自分の生きざまを貫き続けてきた人だけが持つ、いぶし銀の迫力に富んでいる。そこには何かにおもねる忖度はない。あるのは、時代の変化を見据え、常に問い続けてきた「自分の存在価値」そのものだ。

OODA(ウーダ)というフレームワークへの関心が高まっている。もともと、戦闘パイロットが実戦に備えるための状況認識や意思決定などのフレームワークだったが、いまでは変革やイノベーションのツールとしてビジネスや政治などにも利用されている。しかし、知識創造理論の野中氏と元陸上自衛隊の三原氏によると、OODAはあくまで個人の「状況適応能力」を開発するツールであり、サムシングニューの創造を約束するものではないという。OODAにまつわる誤解を正すとともに、いかに活用するかについて議論する。

「世界一の総合楽器メーカー」として知られるヤマハ。現在、その先頭に立っているのが、2013年に社長に就任した中田卓也氏だ。中田氏は就任早々、凝り固まった事業部制の壁を壊す一方、技術・アイデア・人脈などを融合させることで、眠れる宝を掘り起こすことに成功。ヤマハの可能性を引き出し、顧客体験を追求した新たなイノベーションを実現しつつある。

「世界一の総合楽器メーカー」として知られるヤマハ。現在、その先頭に立っているのが、2013年に社長に就任した中田卓也氏だ。中田氏は就任早々、凝り固まった事業部制の壁を壊す一方、技術・アイデア・人脈などを融合させることで、眠れる宝を掘り起こすことに成功。ヤマハの可能性を引き出し、顧客体験を追求した新たなイノベーションを実現しつつある。

よくも悪くも「集団主義的」な特徴こそ、日本人、日本企業の基本特性である。そう信じられてきたし、いまもそう考えられている。しかし、『「集団主義」という錯覚』(新曜社)を著した認知心理学者の高野陽太郎氏は、こうした「日本人イコール集団主義」という定説を真っ向から否定。日本人イコール集団主義という定説は事実ではないと主張している。高野氏の知見に触れることで、誰もが持っている思考の悪癖を認識し、その弊害や危うさを理解できるはずである。

2014年、サントリーホールディングスは、アメリカの大手スピリッツメーカー、ビーム(現ビームサントリー)を買収し、跳躍を果たした。この小が大を呑む買収のPMI(買収後の経営統合)と、新たな成長軌道を描くという大仕事を任されたのが、新浪剛史氏である。社長就任から丸4年を迎えた新浪氏に、アメリカ・ビームとの統合でも発揮された現場重視のリーダーシップ、価値観に基づく経営統合と人づくり、そして自身の経営哲学について聞いた。

AIによる「自動化」が加速している。情報工学の第一人者である喜連川優氏は、自動化を推進するだけでなく、現時点におけるAIの限界、想定外への対処などについてよくよく考える必要がある、と説く。そして、まだ未熟なAIをもっと賢くする必要があり、そのためにはデジタルデータという燃料をもっと与えなければならず、それが、自動化はもとより、デジタル・トランスフォーメーション(DX)やオープンな共創の必要条件だと言う。

福澤桃介機略縦横のリーダー
名古屋電燈のトップとして、桃介は木曽川の可能性に目をつけ、同流域に現存する33の発電所のうち7つの建設を企画し実現させた。文字通り「水力王」である。その生涯は、深山に生じた一滴が斜面を流れ下るうちに成長し、最後は海に注ぐ大河のように、ダイナミックであった。

経営哲学「京セラフィロソフィ」と独自の「アメーバ経営」をベースに事業を拡大し、一度も赤字に転落したことがない優良企業・京セラ。2017年に社長に就任した谷本秀夫氏は、デジタル時代のグローバル競争に勝ち残るため、AIやロボティクスの本格導入による「生産性倍増」やオープンな「協働開発」などスピーディに施策を打ち出し、自社の枠に囚われない“新生アメーバ経営”を展開しつつある。現代の〝経営の神様〟とも称される稲盛和夫氏が創業した会社が、新たな存在価値をどう見出し、社内外にどのような変化を起こしていきたいのか。谷本氏は穏やかな口調で、簡潔ながらも明瞭に、自信を持って語ってくれた。

経営哲学「京セラフィロソフィ」と独自の「アメーバ経営」をベースに事業を拡大し、一度も赤字に転落したことがない優良企業・京セラ。2017年に社長に就任した谷本秀夫氏は、デジタル時代のグローバル競争に勝ち残るため、AIやロボティクスの本格導入による「生産性倍増」やオープンな「協働開発」などスピーディに施策を打ち出し、自社の枠に囚われない“新生アメーバ経営”を展開しつつある。現代の〝経営の神様〟とも称される稲盛和夫氏が創業した会社が、新たな存在価値をどう見出し、社内外にどのような変化を起こしていきたいのか。谷本氏は穏やかな口調で、簡潔ながらも明瞭に、自信を持って語ってくれた。

さまざまな業界で導入が進むロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)。日本企業の現場にいまだ多く残る、複雑・少量・多様な手作業の自動化を進める「日本型RPA」が注目を集めている。日本型RPAは日本企業をどのように変えるのだろうか。

賢明なリーダーは RPAをDXに発展させる
金融業界を皮切りに、小売業や製造業など幅広い業界で「ロボティック・プロセス・オートメーション」(RPA)の導入が広がっている。ただし、RPAをコストや労働時間を削減するツールとして導入すると、そのベネフィットは限定的なものに終わってしまう。業務プロセス改革の端緒とし、デジタル・トランスフォーメーション(DX)へと発展させて、初めて大きな効果が得られる。

先端テクノロジーによる常時監査でグローバル経営管理の高度化を目指す
AIがリアルタイムですべての取引に目を光らせる常時監査が、現実のものとなりつつある。海外子会社を舞台とする不正の抑止にもつながると期待されるが、そのためにはグループ会社間で業務プロセスやシステムを統一する必要があり、買収先の自主性を尊重するという美名の下に統合を怠ってきた日本企業にとって、簡単なことではない。先端テクノロジーを活用した監査は、経営にどのような価値をもたらすのだろうか。

大企業の使命日本のDXを牽引し、次なる成長軌道を描く
デジタル・トランスフォーメーション(DX)を、IT化に留めることなく、ビジネスモデルの再構築、ビジネスプロセスの全体最適化、新規事業開発やイノベーションといった、非連続的な変革へと発展させる。また、自前主義や縦割りなど「閉ざされた」経営から抜け出し、さまざまなプレーヤーと共創し、新しい価値や競争優位を創出していく。いま日本企業には、こうした「開かれた」経営が求められている。そのためにはDXが必要十分条件である。「大企業こそDXの牽引役となるべき」と唱える東京大学大学院教授の森川博之氏と、KDDIでDXを推進してきたソリューション事業企画本部長の藤井彰人氏が、日本のDX論について意見を交わす。

