顧客接点ごとのCX(顧客体験)向上や部分最適を超えて、カスタマージャーニーを通してCXの全体最適化を図るには、部門や組織の壁を超えたシームレスなデータ共有が必要だ。そのうえで、外部データ、第三者が保有するデータなどとつなげることで、データが新たな価値を生むことになる。その要諦をSCSK執行役員の蔦谷洋輔氏に聞いた。

クラウド上のデータプラットフォームを提供するSnowflake(スノーフレイク、米国カリフォルニア州)は、すべての組織をデータ主導型にすることをミッションに掲げ、2012年の創業から10年足らずで3000社以上の顧客を獲得してきた。Snowflake日本法人のトップに、「データクラウド」の実践によるデータドリブン経営について聞いた。

新型コロナウイルスのパンデミックが契機となって、日本でも一気にデジタル化が加速し、多くの企業がデジタル・トランスフォーメーション(DX)に本腰を入れ始めている。ただし、DXは「企業変革プロジェクト」であり、デジタル化は必須ながら、それだけでは企業変革には至らない。DXの本質は、D(デジタル)ではなく、X(トランスフォーメーション)にある。では、そのトランスフォーメーションに向けて、企業はどのようにデジタル化を実践すべきなのか。100年超の老舗企業である「出光興産」と「味の素」のCDO(Chief Digital Officer:最高デジタル責任者)が、自社の具体的取り組みとポイントについて語った。

2020年7月21日、『ダイヤモンドクォータリー』誌は、ウェブセミナー「成功するDX、失敗するDX」を開催した。基調講演には、一橋大学ビジネススクール客員教授の名和高司氏が登壇し、「DXからMXへ:デジタルを駆使した経営改革」というテーマについてプレゼンテーションを行った。基調講演に続いて、アビームコンサルティング執行役員・プリンシパルの宮丸正人氏、ならびにDomoエバンジェリスト兼リードコンサルタントの守安孝多郎氏のレクチャー、そして最後は味の素代表取締役・副社長執行役員の福士博司氏と出光興産執行役員・デジタル変革室長の三枝幸夫氏を交えたパネルディスカッションが行われた。

ポストコロナの時代は大きく変わるとの見方がもっぱらだが、その具体的な姿についてはいまなお不確実で、想定できない部分が多い。ところが、明らかにバランスを欠いた議論や真偽のはっきりしない予測が各所で散見され、大量の情報の氾濫を意味する「インフォデミック」が棹差して いる。前編に引き続き、日本製造業にまつわる根拠の怪しい論説について、藤本氏に解説いただく。

ポストコロナの時代は大きく変わるとの見方がもっぱらだが、その具体的な姿についてはいまなお不確実で、想定できない部分が多い。ところが、明らかにバランスを欠いた議論や真偽のはっきりしない予測が各所で散見され、大量の情報の氾濫を意味する「インフォデミック」が棹差して いる。前編に引き続き、日本製造業にまつわる根拠の怪しい論説について、藤本氏に解説いただく。

インフルエンサーといわれる人たちが、根拠や確証に乏しい予測や主張、一知半解や半分本当の説明などを発しており、困ったことに、これらの多くが「悲観論」である。とりわけ、かれこれ十余年にわたり、日本製造業の弱体化、ものづくりの衰退について指摘されてきた。それが本当なのか。ものづくり経営研究の第一人者・藤本隆宏氏が、こうした怪しい論説について反論を試みる。

インフルエンサーといわれる人たちが、根拠や確証に乏しい予測や主張、一知半解や半分本当の説明などを発しており、困ったことに、これらの多くが「悲観論」である。とりわけ、かれこれ十余年にわたり、日本製造業の弱体化、ものづくりの衰退について指摘されてきた。それが本当なのか。ものづくり経営研究の第一人者・藤本隆宏氏が、こうした怪しい論説について反論を試みる。

創業111年目の味の素が大きく生まれ変わろうとしている。アミノ酸という独自のコア技術を持つ自社の原点に立ち返り、人類の「食と健康の課題解決」という壮大な“パーパス”に挑戦しようというものだ。コロナショックという緊急事態の中で動き出したパーパスドリブン企業に生まれ変わる改革への決意を、西井社長に聞いた。

創業111年目の味の素が大きく生まれ変わろうとしている。アミノ酸という独自のコア技術を持つ自社の原点に立ち返り、人類の「食と健康の課題解決」という壮大な〝パーパス〟に挑戦しようというものだ。コロナショックという緊急事態の中で動き出したパーパスドリブン企業に生まれ変わる改革への決意を、西井社長に聞いた。

日本企業は、グローバル化を果たしたといわれる。たしかに製品はグローバル化したが、経営と人材のグローバル化はいまだ道半ばである。ダイバーシティは、業績のみならず、組織のイノベーション能力、リスク対応力、レジリエンス(再起力)との相関性が高く、資本市場の注目度は年々高くなっている。小林氏は、この「資本市場からの 圧力」なくして日本企業は変われないと指摘する。

データドリブン経営の実現へ。CFOが担うDX時代の価値創出
Cスイート(最高○○責任者)の中でも、CFOほど守備範囲が拡大した存在はない。従来の経理財務業務は自動化が進む一方、CEOのパートナーとして事業に積極的に関与し、リスクを管理する。加えて、昨今ではDX(デジタル・トランスフォーメーション)の牽引役まで求められる。そんな悩み多きCFOが切実に必要としているのが、意思決定をサポートする情報だ。 ERPがその一助となるのは確かだが、第三者の目を通した経営情報という点では、監査法人によるデジタル監査に期待が集まる。事業活動に伴うさまざまなデータを内と外とで共有・活用することで、新たな価値は生まれるのか。テクノロジーの進化が企業と監査法人の関係を再定義する可能性について、2人のリーダーに聞いた。

ダイバーシティ・アンド・インクルージョン(多様性と包摂)は近年、イノベーション経営や持続的成長戦略の文脈で語られることが増えている。その先進企業であるアドビの女性リーダーに、推進の要諦は何かを聞いた。

障がい者に働く場を用意し、彼らの社会参加を大きく後押しした産業人というと、古くは渋澤栄一であり、戦後では、「オムロン太陽の家」を創立したオムロン創業者の立石一真、これに共鳴したソニー創業者の井深大らが知られているが、もう一人、忘れてならない人物がいる。宅急便という画期的なサービスを発明した小倉昌男である。彼は、善意と優しさで運営されていた障がい者が働く職場に「経営」を導入し、彼らに正当な報酬といっそうの働きがい、そして何より「働く喜び」をもたらした。本稿では、沼上幹著『小倉昌男』(PHP研究所)「第1部 第Ⅵ章 長いお別れ|5 新たな課題への挑戦:ヤマト福祉財団」をインタビュー形式に翻案し、小倉昌男のもう一つのイノベーションのみならず、産業人の社会的使命について、あらためて考察する。

スマートフォンなどのデバイスには同社の電子部品が欠かせないといわれる村田製作所。極めて模倣困難なビジネスモデルを武器に、アップルやサムスンなどのリードユーザーを相手に自社製品の価値を認めさせ、「世界スピードのものづくり」を担っている。そんな村田製作所も20年前には“大企業病”という深刻な病に陥っていた時期があった。その危機をどう乗り越え、会社を生まれ変わらせたのか。

スマートフォンなどのデバイスには同社の電子部品が欠かせないといわれる村田製作所。極めて模倣困難なビジネスモデルを武器に、アップルやサムスンなどのリードユーザーを相手に自社製品の価値を認めさせ、「世界スピードのものづくり」を担っている。そんな村田製作所も20年前には“大企業病”という深刻な病に陥っていた時期があった。その危機をどう乗り越え、会社を生まれ変わらせたのか。

グローバルのユニコーン企業と協働・共創する「ジャパンプラットフォーム」が目指す世界
大企業とスタートアップとの協業やオープンイノベーションは、もはやマストであり、しかも新たに身につけなければならない組織能力である。しかし、日本では成功例が少ない。ウイン・ウインの関係がうまく築けない、同床異夢のまま進んでいく、スタートアップを対等なパートナーとして扱わない(ついつい下請け扱いしてしまう)、それゆえ自社のコア事業やコア技術に引き寄せてしまうなど、古くて新しい課題である「パートナリング(partnering)能力」が欠けているからだ。こうした現状を鑑み、新規事業開発やイノベーションのパートナーシップを徹底的に支援するプロジェクトが立ち上がった。日系コンサルティング会社のアビームコンサルティングは、シンガポールの政府系ベンチャーキャピタル(VC)、バーテックス・ベンチャー・ホールディングスのVCファンドに出資し、日本を超えてさまざまな国のスタートアップとの共創空間「ジャパンコンソーシアム」を設立した。バーテックス会長のテオ・ミン・キアン氏、同ファンドのゲートウェイとして日系投資家を束ねるリサ・パートナーズのシンガポール現地法人取締役会長のチュア・テック・ヒム氏、アビームコンサルティング執行役員の宮丸正人氏のキーパーソン3人に、彼らが組成したベンチャーファンドとジャパンコンソーシアムのあらまし、そしてスタートアップとの協業やオープンイノベーションの成功要因などについて聞く。
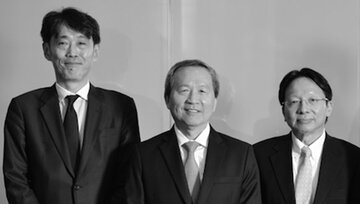
不正の検知から、予測と防止へ。ここまで来たAI監査の実力
組織が誕生したその瞬間から人類を悩ませてきた不正問題は、新しいステージに入った。事業のグローバル化や大規模化に伴い、より巧妙で大胆な不正行為が、いまこの瞬間も組織を蝕んでいるおそれがある。進化する脅威に立ち向かうためには、革新的なテクノロジーを活用したダイナミックなアプローチが欠かせない。連載第2回となる今回は、AI監査による不正検知と防止の最前線を追う。

人財サービス会社・アデコの特例子会社、アデコビジネスサポートで働く障がい者はおよそ160人。そのうちの80人が、求職者のヒアリングや企業とのマッチングや営業サポート業務といった、アデコのコア業務に携わっている。障がい者が担えるのは単純作業を主体としたバックオフィス業務だけである。そんな先入観を覆す取り組みを進める意図とは何なのだろうか。そして、その成果とは──。アデコの代表取締役社長である川崎健一郎氏に話を聞いた。

ビジネスジャーゴン、たとえば流行り言葉や英略語などに惑わされてはいけない──。これまでもずっといわれてきたことだが、こうした悪弊から逃れるには、やはり思考様式そのものを改めるしかない。一橋大学の沼上教授が、ビジネスリーダーに求められる深い思考をもたらす方法、多くの人たちに見られる思考の癖やその問題点について問い直す。

