目まぐるしく変化する社会と市場のはざまで、日本の製造業はこの先どのような成長戦略を描いていけばよいのか。その重要なヒントとなるのが、「ダイナミック・ケイパビリティ」(自己変革能力)だ。著書『ダイナミック・ケイパビリティの戦略経営論』でも知られる慶應義塾大学教授の菊澤研宗氏と、アビームコンサルティングで多くの製造業の支援に当たってきた橘知志氏に、“ダイナミック・ケイパビリティ”の注目点や実践のためのヒントを聞いた。

グループ長期経営方針「VISION 2025」の基本ストラテジーの一つとして「テクノロジーを活用し、不動産業そのものをイノベーション」することを掲げる三井不動産。「モビリティ構想」では、人やコンテンツの移動に着目し、従来の不動産業の垣根を超えた体験価値の創出を目指す。不動産大手が取り組むMaaS(Mobility as a Service=サービスとしてのモビリティ)とはどのようなものか。三井不動産ビジネスイノベーション推進部の須永尚氏に、製造業を中心に企業変革やグローバル化の支援を行ってきたアビームコンサルティングの古川俊太郎氏が、その意義を問う。

変化の振れ幅が大きい時代だからこそ、変えるべきものは何で、変えるべきでないものは何か。その見極めが経営者には求められる。アビームコンサルティング代表取締役社長の鴨居達哉氏と一橋ビジネススクール教授の楠木建氏の対談は、その論点から始まった。そして、企業経営のみならず、世の中全体の思考の流れを短期から長期へと引き戻すために、経営者はその変革の先頭に立つべきであり、それに伴ってコンサルティングファームに期待される役割も変化しているという議論へと発展していった。

2021年4月、NECは企業のDXを支援するデータドリブンDX事業部を新設した。活用するのは、NEC発のAIスタートアップが開発した世界初のAI自動化技術「dotData」だ。データサイエンティスト不要のこの技術は、現場人材をDXの主役にすることで新たなインテリジェンスを生み出すだけでなく、仕事のやり方や働き方、カルチャーさえも変えてしまうほどの力を秘めているという。

現在、世界中のリーダーたちが「DX」とともに推し進めているもう一つの改革、それは「サステナブル・トランスフォーメーション」(SX)である。そのSXにおける日本のリーダー企業こそ、植物由来の業務用素材を提供する食品メーカー「不二製油グループ本社」だ。同社は世界の機関投資家から最も信頼されているESG投資の評価機関CDPから世界で10社しかないトリプルA企業に認定されているが、こうした世界的高評価を生み出しているのが、常に高みを目指すサステナブル調達によって進化を続ける同社のグローバルサプライチェーンである。「ESGを稼ぐ力に変え、成長力につなげることが私のミッションだ」と語る酒井幹夫社長に、世界水準のESG経営による自己変革、SXがつむぎ出すシナリオについて語ってもらった。

ここ最近、日本的経営の特徴でもあったサステナブル経営やマルチステークホルダー論が唱えられているが、その根底には、分解・分析して一元的に説明する西洋合理主義的な思考法がある。振り返ると、1990年代半ば、欧米型経営への危うさや不実の疑いから、部分と全体を合一する「生命論」や「複雑系」に眼差しが向けられた。この時、並行して注目されたのが「西田幾多郎」である。そしていま、「西田哲学」に関心を示すビジネスリーダーたちが現れている。そこで、『西田幾多郎全集』(岩波書店)の編集委員の一人であり、京都大学エグゼクティブ・リーダーシップ・プログラムで西田哲学を教えている藤田正勝氏に、エグゼクティブや初学者に向けた解説をお願いした。

海外に比べて周回遅れといわれる日本のデジタル変革は、圧倒的な人財不足が大きな原因の一つとされている。国際競争力を取り戻すためにスマートインダストリーへの転換が急務とされる中、その担い手となるデジタル人財を企業はいかに集め、育てるべきか。人財サービス大手、アデコの代表取締役社長で、同社グループのIT・エンジニアリング系人財サービス会社、VSNの代表取締役社長を兼任する川崎健一郎氏に聞いた。

コロナ禍によって、多くの企業がサプライチェーンの寸断という大きな問題に直面した。そこであらためて浮き彫りになったのが、サプライチェーンDXという経営課題だ。この課題解決に向け、日本企業はどう取り組むべきか。世界最大規模の企業間取引プラットフォームを運営するオープンテキスト(本社カナダ)の2人に聞いた。

新型コロナウイルスの世界的拡大によって、あらゆる企業にサプライチェーン改革が求められている。ただしその際、経済合理性の追求だけでなく、SDGs/ESGといった社会課題解決の視点を考慮に入れなければならない。そのためには、デジタル化とデータドリブンのアプローチによる「デジタル・サプライチェーン・マネジメント」が不可欠であり、これは時代の要請でもある。

セキュリティ脅威が複雑化・高度化し、いっぽうで働き方が多様化する中で、境界防御のセキュリティ対策では、もはや十分な効果を得ることはできない。ゼロトラストを前提に、従来の対策を見直す必要がある。こうした考え方を10年以上前の創業時から貫いてきたのが、ゼットスケーラーだ。クラウドベースの同社のセキュリティソリューションに、時代が追い付いてきたともいえそうだ。

第3次AIブームを巻き起こしたディープラーニングは、多くの分野で導入されてきた。しかし、その真価を引き出せている企業はまだ一握りといえる。そんな中、ディープラーニングの課題を解決し、“現場で使えるAI”として注目されるのが、「スパースモデリング」だ。ディープラーニングと何が決定的に違うのか。世界でも稀な、スパースモデリング実装の先駆者であるHACARUSの藤原健真CEOに話を聞いた。

リスク多発時代の新たな経営ミッション「デジタルリスクマネジメント」
コロナ禍を契機に、日本でもリモートワーク普及やDXが急加速した。デジタルテクノロジーの恩恵ばかりが注目されるが、そのリスクを適切に管理できている企業は少ない。事実、この1年を振り返ってみても、デジタルリスクに起因する重大インシデントが多数発生し、企業価値を大きく毀損した企業もある。多くの企業が見落としている「デジタルリスクの脅威」とは何か。それらとどう向き合い、対処すべきか。デジタルの力を正しく引き出すために不可欠な「デジタルリスクマネジメント」について、KPMGコンサルティングの専門家に話を聞いた。

資生堂は、2021年から新たな中長期経営戦略の初年度に入った。その指揮を執るのが、2014年4月に社長に就任した魚谷雅彦氏である。変革のリーダーという仕事は、想像以上に困難が付きまとう。それは、矛盾や相克といった「両義性」を抱えた問題、つまり改革のジレンマである。しかし、魚谷氏によると、こうしたコンフリクトこそ価値創造や創意工夫の源泉であるという。矛盾や相克、同床異夢を建設的に融和し、そこから価値を生み出すのが、魚谷氏の言うところの「信頼」という無形資産である。

ここ数年、主要なアメリカ企業が参加するビジネス・ラウンドテーブル、世界経済フォーラムなどは「マルチステークホルダー主義」の支持を表明し、指標による管理を推奨し始めた。日本では、産業界や資本市場関係者、はてはマスメディアも手放しで、これを支持・称賛している。だがその果てには、経営の思考停止を招きかねない。日本発のマルチステークホルダー論である近江商人の「三方よし」は、自分の頭で考え、実践することを求め、それゆえ自在性に富んでいる。

地政学的リスクが高まる中、有事の際、調達や納期の遅れを最小限に留める対策が喫緊の課題となっている。これは、グローバルに事業展開している企業だけでなく、ドメスティック企業も例外ではない。なぜなら、あらゆる分野のロジスティクス/サプライチェーンがグローバルに広がっているからだ。グローバルロジスティクス研究の第一人者、東京大学大学院工学系研究科准教授の柴崎隆一氏に聞く。

サイバーテロや情報流出、システムの機能不全など、「情報セキュリティ」の重要性は高まる一方である。しかし日本では、いまだ優先順位の低い経営課題に留まっている。情報セキュリティの研究者であり実践者でもある高倉弘喜氏にそのポイントを聞く。
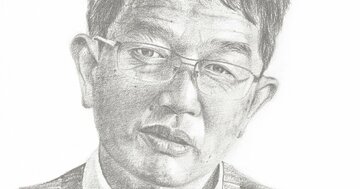
企業倫理は、以前から議論されてきた課題だが、最近では、先覚的なビジネスリーダーたちがその重要性を指摘するようになった。こうした新しい現実に対応するには、コンプライアンスやハラスメントに関する研修以上に、まず「それは倫理的といえるのか」という唯一最善解のない問いを深く考える知的修練、たとえばゼロベース思考やクリティカルシンキング、EQ(心の知能指数)の向上などが効果的である。本インタビューでは、技術の進歩、資本主義や企業組織にまつわるジレンマやトリレンマについて、倫理学の視点から考え直す。

日本でもM&A件数は増えているものの、欧米ほど戦略的に活用できているとは言いがたい。事実、コロナ禍にあって、日本は縮み指向だが、欧米とりわけヨーロッパでは、変革を加速し、新しい成長軌道を描こうと大幅に増加している。本インタビューでは、M&A業界の重鎮である渡辺章博氏に、あらためてM&Aの戦略性や有効性について聞く。そこでは、中堅・中小企業を含めた日本産業界におけるM&Aの伸び代の大きさが示された。

健康志向や本物志向に応えるハム・ソーセージ・ベーコンなどを製造する信州ハム(長野県上田市)。20年以上使い続けた生産管理システムの更新を迫られた同社は、現場のニーズにかなったシステムを構築するため、ITベンダーに頼らず内製化に挑んだ。その結果、生産現場の作業効率の改善だけでなく、各工程における歩留まりの「見える化」、意思決定のスピードアップなど、さまざまな成果が得られた。

ローコード開発に対応したデータベースソフト「FileMaker」(ファイルメーカー)や、ワークフロー自動化プラットフォーム「Claris Connect」(クラリス・コネクト)などを提供するClaris International。2019年8月に社名をFileMakerから創業当初のClarisに戻し、由来するラテン語のように、“輝く”(Claus)未来へ顧客企業とともに歩む決意を新たにした。アジャイルな経営が企業に与えるインパクトについて、ブラッド・フライターグCEOに聞いた。

