バリューチェーン終点の消費者からネットワーク中心の生活者へ
トヨタ自動車の「Woven City」やJR東日本の「品川開発プロジェクト」など、スマートシティ構想があらためて脚光を浴びている。その背景には、デジタルの進展と社会課題の解決に向けた強い要請がある。都市のデジタル・トランスフォーメーション(DX)を進め、スマートシティ開発を成功させるポイントは何か。戦略系コンサルティングファームのアーサー・ディ・リトル・ジャパンの3氏に聞いた。

菅義偉総理大臣の「2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにする」という宣言以後、日本産業界は大きく脱CO₂へと傾斜した。脱CO₂に拍車がかかっていくことは歓迎すべきだが、とかくエネルギー分野には、さまざまなトレードオフや見解の相違を伴う、一筋縄ではいかない多元的で複雑な議論がつきまとう。JERA社長の小野田聡氏へのインタビューを通じて、こうした唯一最善解のない地球環境問題に対処するために事業や経営を改革していく「グリーン・トランスフォーメーション」(GX)について考えてみたい。

シマノは「自転車業界のインテル」といわれる。PCのプロセッサーの大半がインテル製であるように、ギアなどの自転車の中核部品の多くがシマノ製だからである。事実、世界各国でつくられている自転車の部品メーカーとして高いシェアを誇る、押しも押されもせぬリーディングカンパニーである。現社長である島野容三氏に、ものづくりにおける強いこだわりとともに、次の100年への転換点となる現在地とデジタル技術の進化を踏まえたうえで、超デジタル、すなわち新しいアナログ世界への挑戦についても語ってもらった。それは、これからの日本企業のあり方を示唆すると同時に、忘れ物を再発見することでもある。

DXの重要性が声高に叫ばれ、中でもソフトウエア開発は企業の戦略実現のためのキーストーンに位置づけられる。その際、何より優先されるのが開発のスピードであり、その名の通り、「アジャイル(俊敏な)開発」という手法が急速に普及している。ただし、少人数のチームが主体となるため、大規模開発には向かないとされてきた。真相はどうなのか。世界的経営学者の野中郁次郎氏とTDCソフト執行役員の上條英樹氏が対話を繰り広げた。
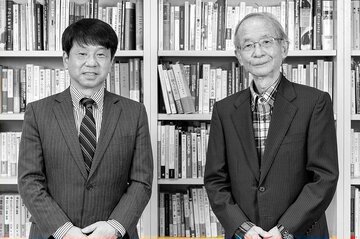
パンデミックが問い直すリーダーシップのあり方
COVID-19(新型コロナウイルス感染症)のパンデミック(世界的大流行)は、わずか数カ月の間に、リーダーシップのあり方を根本的に問い直した。世界のあらゆる国や組織、個人がコロナ禍の影響を受け、先行きの不透明さが増す中で、経営とリーダーシップをどのように再定義すべきか。KPMGの2人のリーダーに聞いた。

サプライチェーン改革の「新しい現実」
新型コロナウイルスのパンデミックが契機となり、サプライチェーンの見直しが企業経営の最優先課題の一つに浮上してきた。これと軌を一にして、開発途上国における児童労働、不平等貿易、脱炭素といったSDGs(持続可能な開発目標)の達成や、新たな地政学的リスクへの対応などもよりいっそう意識されるようになった。企業はこうした「新しい現実」を踏まえたサプライチェーン改革に取り組まなければならない。経営者のためのクイックレッスンを3人の専門家に仰ぐ。

「非財務情報開示」は誰のためか
新型コロナウイルス感染症の拡大により、業績を大幅に悪化させたり、ビジネスモデルの転換を迫られたりする企業が相次いだ。そこであらためて浮き彫りになったのは、財務情報から予測できる企業価値には限界があるということ。だが一方で、矢継ぎ早に導入される非財務情報開示のフレームワークや投資家からの要請に、企業からは「開示疲れ」を指摘する声も聞こえる。金融庁で企業情報開示の強化に取り組む園田周氏と、あずさ監査法人 開示高度化推進室を率いる関口智和氏のインタビューから、誰のため、何のための非財務情報開示なのか、その本質を探る。

デジタルとアナログのベストミックス
日本でもデジタル・トランスフォーメーション(DX)が声高に叫ばれてきたが、今回のコロナ危機でデジタルシフトはさらに加速した。その一方で、企業間のデジタル格差が広がっているという指摘もある。デジタルによってビジネスのトランスフォーメーションを実現する企業には、どのような特徴があるのか。それを示したKPMGのCIO調査をもとに、早くから製薬業界のDXをリードしてきたアステラス製薬にデジタル戦略のポイントを聞いた。

サステナビリティ経営へのトランスフォーメーション
世界経済フォーラムは、地球の持続可能性、人類の平等性を取り戻すことを目的に、「グレート・リセット」というイニシアティブを立ち上げた。これに呼応するかのように、以前より環境問題に敏感なヨーロッパはもとより、アメリカ、日本、中国なども脱炭素に大きく舵を切り始めた。この新しい現実では、「サステナビリティ」の流れは不可逆であるばかりか、従来の企業経営の考え方、ビジネスのやり方、ゲームルールの変更を迫られる。サステナビリティ経営へと舵を切るうえでの実践知について、2人の専門家に聞く。

パーパスを基軸として強靱な組織を構築せよ
世界のCEOを対象に行った「KPMGグローバルCEO調査2020」では、新型コロナウイルス感染症を機に、経営者がパーパス(存在意義)の重要性を再認識していることが明らかになった。KPMGジャパンの森俊哉チェアマンは、変化の激しい混迷の時代にこそ、パーパスを基軸としてレジリエント(強靱)な組織を構築すべきだと話す。

農業はいま、国内では従事者の高齢化と後継者不足、世界では人口爆発による食料不足といった課題に直面している。そうした中、クボタが課題解決に向けて挑むのが「スマート農業」である。データ収集、AIやロボットなどの活用で、クボタはどのように勘や経験に頼らない効率的な農業を実現するのか。イノベーションを牽引する社長の北尾裕一氏に、目指す「未来の農業」を尋ねた。

ベイシアグループは、作業服で快進撃を続けるワークマン、ホームセンター首位のカインズ、ショッピングセンターのベイシアなど28社から成るユニークな流通企業グループである。その中核企業であるカインズは、時代の節目ごとにみずからをトランスフォームすることで業界のゲームチェンジャーとなり、いまや「IT小売企業」への転身を果たした。風雲急を告げる小売業界で勝ち残るための戦略を、グループトップの土屋裕雅会長に聞いた。
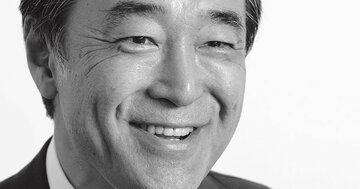
ベイシアグループは、作業服で快進撃を続けるワークマン、ホームセンター首位のカインズ、ショッピングセンターのベイシアなど28社から成るユニークな流通企業グループである。その中核企業であるカインズは、時代の節目ごとにみずからをトランスフォームすることで業界のゲームチェンジャーとなり、いまや「IT小売企業」への転身を果たした。風雲急を告げる小売業界で勝ち残るための戦略を、グループトップの土屋裕雅会長に聞いた。
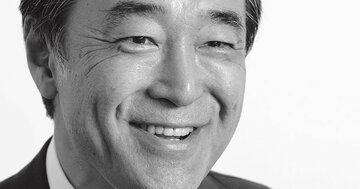
渋沢栄一といえば、「近代日本資本主義の父」と呼ばれ、企業の目的が利潤の追求にあるとしても、 その根底には道徳が不可欠とする「道徳経済合一主義」を提唱し、日本に「合本主義」(株式会社 制度)を導入したことで知られる。こうした渋沢の一連の行動は、鹿島茂氏によれば、パリ万博 使節団に参加し、当時のフランスで支配的だった「サン=シモン主義」に感化されたからだという。 このサン=シモン主義こそ渋沢の核心であり、ひいては日本的経営の再発見につながるものである。
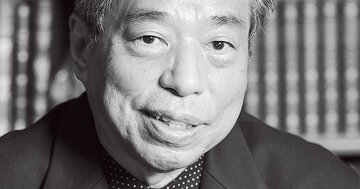
渋沢栄一といえば、「近代日本資本主義の父」と呼ばれ、企業の目的が利潤の追求にあるとしても、 その根底には道徳が不可欠とする「道徳経済合一主義」を提唱し、日本に「合本主義」(株式会社 制度)を導入したことで知られる。こうした渋沢の一連の行動は、鹿島茂氏によれば、パリ万博 使節団に参加し、当時のフランスで支配的だった「サン=シモン主義」に感化されたからだという。 このサン=シモン主義こそ渋沢の核心であり、ひいては日本的経営の再発見につながるものである。
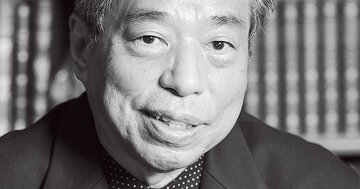
9月27日に開催された『DIAMOND Quarterly』創刊4周年記念フォーラム。特別講演には、ソニー・プレイステーションの生みの親として知られるサイバーアイ・エンタテインメント代表取締役社長兼CEOの久夛良木健氏が登壇した。コロナ禍でデジタル化が加速する中、日本のデジタルトランスフォーメーションは世界からすでに周回遅れだと指摘。その背景にある、日本企業が抱えるイノベーションのジレンマについて、みずからのソニー時代の経験も交えて語った。以下は、その特別講演のサマリーである。

2020年9月29日、『ダイヤモンドクォータリー』誌は、創刊4周年記念フォーラム「前例なき未来に向けて『日本のデジタル経営』を構想する」を開催した。基調講演には、東京大学教授の藤本隆宏氏が登壇し、「サービス化・デジタル化・感染症・米中摩擦時代の開かれた『ものづくり』戦略」という演題でプレゼンテーションを行った。これに続いて、レイヤーズ・コンサルティングの杉野尚志氏、オートメーション・エニウェア・ジャパンの由井希佳氏、デロイト トーマツ グループの松江英夫氏、そして最後に「プレステの父」と呼ばれる元ソニー・コンピュータエンタテインメントCEOの久夛良木健氏が、それぞれにレクチャーを披露した。以下は、藤本教授の基調講演のサマリーである。

スティーブ・ジョブズが、30余年にわたり、曹洞宗僧侶、乙川弘文氏から禅を学んでいたことから、座禅や瞑想から派生した「マインドフルネス」が注目されるようになり、シリコンバレー発の起業家たちや進歩的な経営者に広がっていく。山田匡通氏は、高校生の時から参禅しており、現在は「マインドフィットネス」というビジネスリーダー向けの禅を指導している。山田氏によれば、自分と他人とを隔てる垣根が次第に低くなり、自分と他人、さらには自分と周囲とが一つの世界に近づいていくことこそ禅の本質であるという。 マインドフルネスという形で、日本に逆輸入された禅について、ビジネスリーダーであり、また禅師でもある山田氏にレクチャーを仰ぐ。

「2020年度、世界で評価される時価総額1兆円企業になる」と安藤宏基CEOが宣言したのは、2016年5月の決算説明会での席上だった。そして4年後の2020年6月、ついに時価総額1兆円、8月には100億ドルを突破。「10ビリオンダラーカンパニー」として、グローバルメジャーの仲間入りを果たした。しかし、それに安んずる日清食品ではない。すでに次のステージへの準備も整えている。グループ理念でもある「EARTH FOOD CREATOR」(地球食を創造する人)として、植物由来の食材と包材への全量切り替え、個人の嗜好や健康ニーズに適合したパーソナルフードにも照準を合わせ、日本発グローバルブランドのさらなる進化に挑戦している。

CXというと、一般的には「顧客経験」の質を高めることだが、一橋大学の名和高司氏はCX1.0、CX2.0、CX3.0に区別し、CX3.0については「カスタマー・トランスフォーメーション」と表現し、消費者や生活者の啓蒙による価値観や購買行動の転換であり、必然的に顧客戦略やマーケティング活動にも転換が求められるという。同様の考え方は、ソーシャルマーケティング、コーズ・リレーティッド・マーケティング、フィリップ・コトラーの言うマーケティング3.0などがあるが、いまやマーケティングという領域を超えて、企業の気球存亡の秋【とき】であり、だからこそ先行者には果実が待っている。

