マーケット全般(152) サブカテゴリ
第2回
2010年以降の金融市場における最大の懸案であった欧州債務問題については、今年、ECBの大きな決断によって、光明が見え始めた。ECBは、7月にゼロ金利政策に踏み切った後、9月には新たな国債買い入れプログラムを発表した。
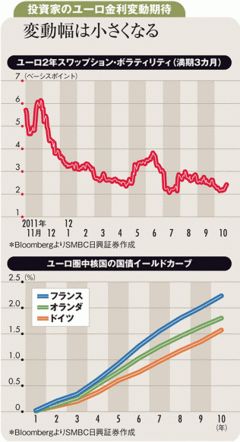
第249回
中国は13億人を超える人々が住む社会なので、連日のように大きな事件が起きる。10月7日までの8連休に高速道路の事故で死亡した人はなんと794人に及んだ。昨年7月に高速鉄道で40人が亡くなったが、中国ではそれに匹敵する大きな事件が頻繁に発生しており、マスメディアを賑わせている。

第44回
10月の市場はやや明るさを取り戻した。ユーロ圏では、ECBが南欧国債の無制限買い入れの意向を表明し、市場の底割れリスクが後退した。中国は直近のGDP成長率が8%を割り込んだが、これを底とする見方が少なくない。米経済は、雇用はいま一つながら、住宅や小売りに明るい変化が見られる。
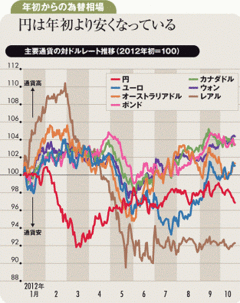
第248回
米国で雇用の「2極分化」が顕著になっている。ニューヨーク連銀のエコノミストが今月発表した論文は、米国における業種を、ハイスキル、アッパー・ミドルスキル、ローワー・ミドルスキル、ローワースキルに分類して、1980年から2010年までの変化を分析している。

第247回
民間の年間平均給与の推移を見てみよう(国税庁調べ)。バブル経済前夜の1986年は362.6万円だったが、バブルピーク期の90年には425.2万円に上昇した。その後、経済は下降線をたどるが、平均給与は97年に過去最高の467.3万円を記録。そこから下落トレンドに入り、昨年は409万円だった。

第1回
1カ月前、政策面で原油や金など国際商品の市況を押し上げる材料が相次いだ。中国政府による公共投資計画の承認、ECBによる南欧国債の買い取り表明、FRBによるQE3の発表と、市場参加者の平均的な想定よりも積極的な政策対応が行われた。
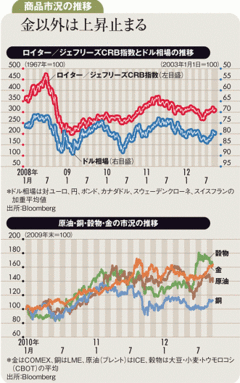
第246回
中国の経済誌「第一財経周刊」10月8日号は、今年のブランドイメージランキングを掲載した。中国で企業に勤める男女3143人に行った調査結果だ。内容から判断すると、調査時期は、日本政府が尖閣諸島を国有化する前だったのではないかと思われる。

第1回
今年に入って日銀は資産買い入れ等基金による長期国債買い入れを25兆円増やした。これにより短中期国債の需給がタイトになり、3年物国債利回りは政策金利と並ぶ水準に張り付いた。また、円高傾向が止まらないことなどを背景に、日銀による同様の政策が長期化するとの思惑が広がり、3年超の国債利回りが低下している。
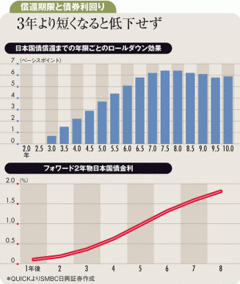
第245回
安倍晋三氏が自民党総裁に選ばれた。次の臨時国会中にもし解散となれば自民党政権が復活し、同氏が総理大臣となる可能性は高い。安倍氏は9月15日の日本テレビの番組で「世界では金融政策が重要な政策の柱になっている。

第244回
「重大な懸念」。バーナンキFRB議長は、8月末の講演で米国の労働市場の改善が遅いことに対する心配を、最大限の言葉で表した。9月13日のFOMCでFRBは、MBSをオープンエンド方式で毎月400億ドル購入する大規模資産購入策を決定した。

第43回
今後数カ月、世界経済に薄明かりが差すと期待する。夏にかけて市場は冷え込んだ。米経済指標は春先までの堅調さを失い、欧州では南欧重債務国問題がこじれ、中国など新興国景気は減速した。

第243回
日本政府が9月11日に尖閣諸島国有化を決定する数日前まで上海にいた。上海の街中では反日的ムードは全く感じられなかった。中国の代表的な経済雑誌「財経」(9月3日号)も社説で冷静な議論を示していた。

第242回
ここ3カ月ほどの間に、英国、米国、メキシコ、ブラジル等を回り、今は中国に来ている。どの国の政治もそれぞれ問題を抱えている。しかし、それらよりも日本の国会の混迷ぶりは深刻である。「衆参ねじれ現象」により国会の機能が著しく低下している。

第241回
米フォーブス誌(9月10日号)は「100人の最もパワフルな女性」を掲載、ブラジルのジルマ・ルセフ大統領をトップに選んだ。

第240回
ブラジルのリオデジャネイロに行った。季節は真冬だが、寒くはない。ビジネス街から車で15~20分程度のコパカバーナ海岸では水着姿の人が多く歩いている。

第239回
8月上旬にメキシコ市を訪れた。メキシコの他の地域では死者が多数発生する麻薬抗争が起きているが、メキシコ人の間ではメキシコ市は安全とみられていて、国内観光客は増加している。

第238回
米国では昨夏に与野党の対立で政府の債務上限引き上げが難航、歳入不足による政府機関閉鎖の恐れが一時高まり、金融市場は動揺した。今年の秋もそのリスクは存在したが、7月31日に、議会の共和党、民主党幹部が来年3月まで政府支出を継続することで合意した。

第42回
ドル円が80円付近から底堅い動きを見せるようになるのは秋からだろう。米金融緩和下のドル円は、米中期金利の動向に沿って動く傾向がある。米中期金利は数年先までの景気や金融政策の行方を織り込むシグナル。
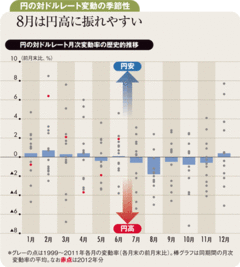
第237回
中国人にとっての「文化的で歴史的な遺産がある国」の第1位は英国だという。そういった印象にロンドンオリンピックが加わったため、中国から英国への観光客は一段と増加している。

第236回
7月12日の金融政策決定会合で、日銀は資金供給オペの札割れ対策は発表したものの、追加緩和策には踏み込まなかった。バーナンキFRB議長は7月17日の米議会証言で、労働市場の停滞やデフレリスクが顕在化した場合の四つの追加緩和策を提示したものの、今はその導入に慎重な態度を示した。
