外交・安全保障(11) サブカテゴリ
第29回
中国軍艦によるレーダー照射問題は、両国の軍に対する文民統制のあり方に疑問を投げかけている。中国側では、人民解放軍の突出をうかがわせ、日本側の対応は政治的な未熟さを感じさせる。
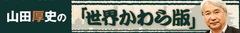
第310回
日本のレーダー照射報道を受け、中国の世論は戦争でもしないと収まらないという雰囲気が濃厚になっている。厳しい環境汚染にあえぐ中国市民は日本の技術を必要としているのに、中日関係もまた深い濃霧で前方が見えない。

第11回
チャイナ・セブンと呼ばれる中国共産党の最高指導部の顔触れが決まった。保守派が大勢を占めると言われるが、習新政権の後半5年に当たる第二期に政治改革に踏み切る可能性は高いと見る。

第10回
中国共産党の第18回党大会が終わり、習近平・李克強新体制がスタートした。東京大学大学院・高原明生教授に、大国の自信と国内の不安定化の双方が増す中国にあって、新政権はどのような性格を持ち、いかなる課題を抱え、対外政策はどう変わるのかについて聞いた。

第19回
地域貿易協定は経済分野での協力を目指したものであるが、現実的には多くが政治外交的な意図を含んだものであり、経済を超えて政治や社会などに幅広い影響を及ぼす存在だ。日本が取り組んでいるTPPもその例外ではない。経済問題に限定したナイーブな捉え方をしてはいけない。

第9回
11月8日、中国共産党全国代表大会が開幕し、習近平新体制が誕生する。新体制はどこに向かうのか。国内的には現状を打破し、政治改革を進める一方、対外的には強硬路線を採る可能性が高い。

第20回
領土問題は双方に言い分があり、白黒を明確につけにくい。大事なことは領土という古傷を新たな紛争の芽にするのではなく、過去を乗り越える「解け合い」の足がかりにする知恵だ。
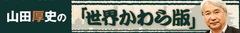
第45回
安倍氏の新総裁就任に際して、1つ気になることがある。それは、安倍氏が5年前の首相辞任について「当時は病気で政権を離れるしかなかったが、2年前に新薬が開発されすっかり良くなりました」と説明していることだ。

第8回
日中双方が一歩も譲らず、硬直化する尖閣問題をどう解きほぐしていけばいいのか。『日中危機はなぜ起こるのか』の著書もある、米ブルッキングス研究所の外交政策上級研究員、北東アジア政策研究センター所長のリチャード・ブッシュ氏に、今回の尖閣問題に関して聞いた。

第124回
築40年を迎えた日中関係を建築物にたとえるなら、至急、新たな耐震補強工事を行うことが必要だ。その中で、トヨタ系2社が、被害を受けた同社の車の所有者に申し出たサービスは注目に値する。

第7回
尖閣列島をめぐる対立で、両国の関係は最悪とも言ってよい状況にある。日本きっての知中派である宮本雄二・宮本アジア研究所代表は、個別の領土がらみ問題で双方の国益全体まで損なうのは正しい外交のあり方ではないと説く。

第6回
日中間の危機的状況をどうすればいいのか。互いにいがみ合い、対立を深めていけば、東アジア全体が「紛争地帯」となり、せっかく築きあげた繁栄も崩れ去ってしまう。短期的、長期的に、この問題をどう捉え、どのような打開策が考えられるのだろうか。

第83回
G7の存在感が薄くなる一方、新興国を含むG20は機能していない。米中G2体制もリーダーシップ面で問題があり、結果、現在は主導国なき世界「Gゼロ」の時代となっている――そんな国際社会の現状を説く気鋭の政治学者に、「ポストGゼロ時代」の世界と日本について聞く。

第5回
東京都の尖閣諸島買い取り構想等を契機に領有権問題で日中両国の緊張が高まるなか、中国国内では反日行動が全国的に広がっている。日中の領有権問題については中立的な立場を明確にするアメリカは、今回の日中両国間での領有権問題をどう捉えているのか。
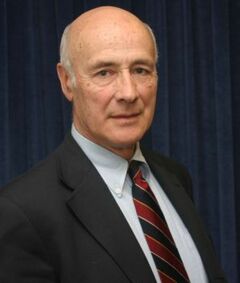
第4回
1978年の改革・開放路線以降、中国経済は奇跡的な成長を遂げてきた。その発展経路を振り返り、同国が中所得国の罠に陥ることなく先進国入りするための課題は何か、緊張他高まる中で日中はどのような経済関係を構築していくべきかを考える。

第62回
もうかれこれ半世紀近く前の話になるが、大学の原書購読の時間に、高坂正堯先生に、地政学を教えていただいた記憶がある。領土問題を巡る昨今の報道を眺めているうちに、先生の教えを思い出した。

第3回
日本の野田政権による尖閣諸島の国有化は、日本国民からすれば「所有者が変わるだけ」の国内的手続きとクールに認識できるだろうが、中国側、特に尖閣諸島をめぐる実情を知らされていない中国人民からすれば「侵略」と映り、政府は「核心的利益」を侵されたと認識する。

第2回
国交正常化から40年たち、日本にとって中国は脅威とは言えないまでも、「不安な存在」となった。中国の海洋進出が活発化するなかで事故による危機発生の可能性も高まっている。日米同盟の強化と同時に、日中間の多層的な危機管理メカニズムの構築が急務である。

第82回
尖閣諸島周辺海域ではいまだ中国の海洋監視船・漁業監視船が活動を続けており、緊張は去っていない。中国は今後どう出てくるのか。米シンクタンク戦略国際問題研究所のシニア・フェローで、中国の外交・安全保障を専門とするボニー・グレイザー氏に聞いた。

第1回
中国との国交樹立が実現したのは、時の総理・田中角栄、外務大臣・大平正芳のリーダーシップに負うところが大きい。日中国交正常化交渉を振り返りながら、いまに何を引き継ぐべきかを考えてみよう。
