週刊ダイヤモンド編集部
第111回
少し円安になってきたとはいえ、国内造船業が厳しい状況にあることは変わらない。かつて50年近く新造船の建造量で世界のトップだった日本は、今や韓国や中国に追い抜かれている。ところが、旧態依然の過当競争が続けられているイメージが強い造船業界で、関係者が熱い視線を送る夢のある遠大な構想が動き出した。

第803回
中国では今、「李克強経済学」という言葉がはやっているという。日本のはやりに倣っていえば、「李コノミクス」である。中国の1~3月期実質成長率は予想を下回る7.7%となった。4月のHSBC製造業PMI(購買担当者景気指数)も、前月比1.1ポイント減の50.5とさえない。

第861回
道路の真上に超高層ビル建設!期待高まる再開発促進の切り札
道路の真上に超高層ビルを建てる──。日本で初となる画期的な土地利用方法が不動産業界で話題を呼んでいる。大阪市が3月に承認した阪神百貨店梅田本店と新阪急ビルの建て替え計画。実はこの二つのビルは幅員約20メートルの市道を挟んで立っており、計画では市道を高さ5・5メートルのトンネル状にして残し、一つの超高層ビルに建て替えるというものだ。

13/05/11号
企業が“本気”のリストラに乗り出した。大企業で退職勧奨プログラムを受けさせられる社員が増え、ミドル世代(30代後半~54歳)の再就職市場が活性化している。もはや、政府も行政も企業も守ってくれないのだ。あなたは、「仕事消失時代」に生き残ることができるか?

第111回
安倍晋三首相のロシア訪問を前に、LNG(液化天然ガス)をめぐって動きが入り乱れている。天然ガスを東アジアに売り込みたいロシア各社と、ロシアからの供給拡大をもくろむ日本の商社の思惑が交錯。商社間の競争も熾烈化して対立の構図が浮き彫りになり、肝心の安価なLNG輸入計画にも影を落としている。
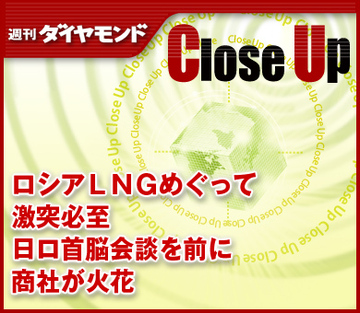
2013/04/29
富士通が半導体事業から“撤退準備完了”――。大手電機メーカーの富士通が、半導体のマイコン(マイクロコントローラ)事業を、米半導体メーカーのスパンションに売却するための最終調整に入ったことが分かった。条件がまとまり次第、発表する。

第114回
斜陽産業とされる繊維を中心とした化学メーカーながら独自のビジネスモデルで安定的な高収益構造を築きつつある東レ。その確立には、成長の立役者である炭素繊維などで次なる一手が必要だ。
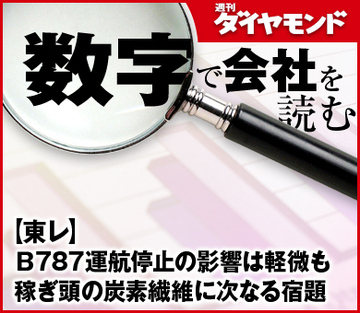
第860回
これもまた、日本銀行が打ち出した新たな金融緩和の効果なのか。とある格付け会社が、不動産投資信託(J-REIT。以下、リート)からの“人気”を独り占めしている。日本格付研究所(JCR)がそれだ。
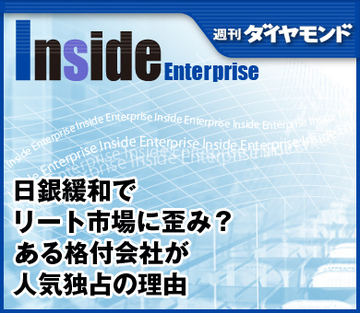
第859回
コスモスイニシアを買収した大和ハウス拡大戦略の背景
3月に発表された大京の穴吹工務店買収に続き、またもやマンションデベロッパーの再編劇が起きた。大和ハウス工業が、コスモスイニシア(旧リクルートコスモス)の第三者割当増資を95億円で引き受け、子会社化することを決定したのだ。

第802回
経済財政政策の基本方針「骨太の方針」策定に向けて、全省庁が6月をメドに盛り込む内容を練っている。そんな中、三菱重工業や日立製作所、東芝といった重電メーカーが経済産業省に足を運び、悩みを打ち明けた。

第110回
エレクトロニクス事業の不振が続く中、2012年度は5期ぶりの最終黒字の達成を見込むソニー。営業損益、最終損益共に巨額赤字を計上した11年度からの“V字回復”のようにも見えるが、内実は資産売却による利益のかさ上げがほとんどだ。本業が苦しい状況は変わっていない。

第858回
西武ホールディングスの再上場問題で、大株主のサーベラス・グループが、完全に牙を剥いた。株式公開買い付け(TOB)による取得目標の上限を36.4%から44.7%に引き上げ、推薦する取締役を3人から8人に増やし、加えて監査役を2人送り込むことで、実質的な経営権掌握を図るものだ。

第857回
海外顧客へのトップ営業に倣え!みずほの弱点リテール強化の秘策
みずほフィナンシャルグループが、弱点とされてきた国内部門のリテール強化の秘策を繰り出した。傘下のみずほ銀行の支店長に重点顧客1万2000先、つまり1支店当たり30先前後をリストアップさせ、融資はもちろん、事業承継や後継者選び、オーナー個人の資産運用などのよき相談相手となって取引の深掘りを図ろうとしているのである。
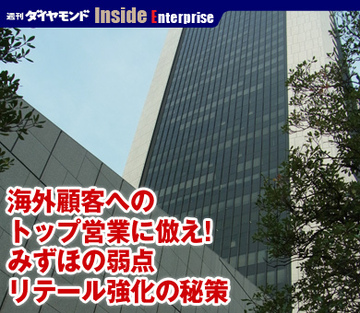
第856回
スプリント買収に厄介な伏兵それでも余裕のソフトバンク
IT'S ALL COMING TOGETHER(これまでの集大成となる)──。米衛星放送会社ディッシュ・ネットワークのホームページ画面に広がったこの文字。横には米3位の携帯電話事業者スプリント・ネクステルのロゴが並ぶ。ディッシュが通信事業参入への仕上げとすべくスプリント買収提案をぶち上げたのだ。これを見たソフトバンク関係者は「またずいぶんと勝手だな」と吐き捨てた。

第855回
大手の中で一人、定価を高めに設定してきた牛丼の老舗「吉野家」が、遂に値下げに踏み切った。牛丼市場は吉野家に加えて、ゼンショーの運営する「すき家」、「松屋」の三強がほとんどを握っている。吉野家の牛丼並盛りは他社よりも100円高かったが、4月18日から、280円に値下げし、三社の価格が揃った。
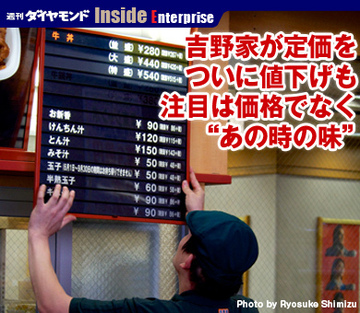
13/4/27
有料老人ホームなどを凌ぐ勢いで、「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」と呼ばれる賃貸住宅の戸数が急増している。介護施設とサ高住のどちらが老後の住まいにふさわしいか。玉石混交とされるサ高住物件をどう選べばいいか。高齢者の住まいと介護を徹底調査した。
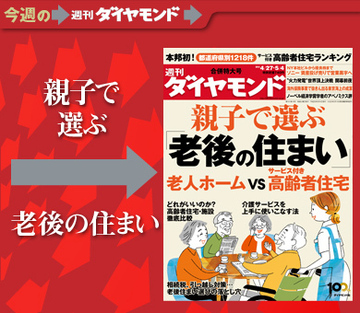
第113回
懸案だった防衛省などへの過大請求問題に決着がつき、再出発を期する三菱電機。一見、実現不可能であろう高い成長目標を引き続き掲げる山西健一郎社長の真意は、どこにあるのか。
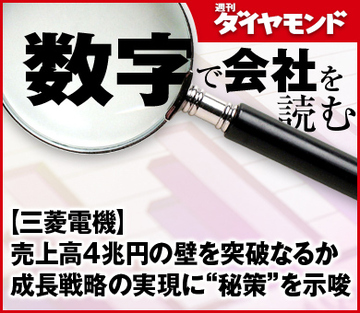
第110回
超緩和策の目的はインフレ率2%だが、達成すれば長期金利は上がるはず。だが日銀はそのために国債を大量購入、長期金利を低く抑え込む。矛盾を抱えた政策に潜むリスクを検証する。

第109回
「戦力の逐次投入はしない」。黒田東彦・日本銀行総裁の下で決まった「超弩級」の金融緩和策は、株式や為替、国債の市場に激しい熱気をもたらし、同時に大きな動揺を与え始めた。デフレ脱却に邁進する日銀に対し、金融機関や企業、個人はどう反応し、その先に何を見据えているのか。緩和策が発表された4日以降の動きを追った。

第801回
国交省の“強権発動”が追い風建設業界にも及ぶ賃上げの動き
復興需要が盛り上がりを見せる一方、労務費や資材費の高騰に泣いていたゼネコン業界が大喜びする施策が登場した。国土交通省、農林水産省の両省が4月から公共工事の労務単価を引き上げることを決めたのだ。
