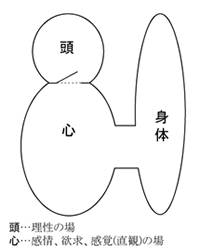――朝、きちんと起きられずに、遅刻してしまう。
――「今日休みます」という電話一本かけられない。
――復職しても長続きせず、また出社できなくなる。
「自己コントロール」がきちんとできることが一人前の大人の条件であるという観念からすれば、上記のような「うつ」によく見られる状態は「自己コントロール」ができていない意志薄弱なものと捉えられてしまいがちです。
しかし、前連載第1回でも述べたように、「うつ」に陥った人々は、ほとんどの場合、発症前までは人並み以上の意志力を備え、強力に「自己コントロール」をかけて進んできた人たちだったのです。
「うつ」に倒れる人々が後を絶たない現在の状況は、このように肥大化した「自己コントロール」の病に対して、人間の内なる自然が起こした一種の「異議申し立て」であると見ることができます。
しかし今日では、「自己コントロール」こそ成功の鍵であり、それを身につけることが人間の成長であり幸せになるための条件だ、という信仰が私たちに浸透し、しつけや教育がそれを拡大再生産し、社会では組織がこれを巧みに利用して人々を隷属させる仕組みが作られてしまっています。
さらに皮肉なことに、そのような意味を負った「うつ」を抱える人々が救いを求める医療までもが、そこに「コントロール」を上乗せして「うつ」が駆逐できるかのような誤った幻想にとりつかれてしまっています。
そこで今回は、人間とはそもそも「自己コントロール」しなければならないような存在なのかという問題について考えてみたいと思います。
ベースにあるのは性悪説的人間観
「自己コントロール」を奨励するような言説は、裏返してみれば「人間というものは、ありのままでは邪悪で怠惰な存在である」という性悪説的人間観をベースにしたものであることがわかります。
この人間観は、厄介なことに、それが誤りであることが検証できない構造になっていて、そのために、多くの人々に疑いもなく脈々と受け継がれてきたものだと考えられます。
このような人間観の誤りがなぜ検証できないのか、次のような喩え話を使って考えてみましょう。
あるクラスに転校生が来ることになりました。しかし、どこからか「今度来る転校生は、かなりのワルらしいぜ」という噂が広まり、それは担任の先生の耳にまで入っていました。