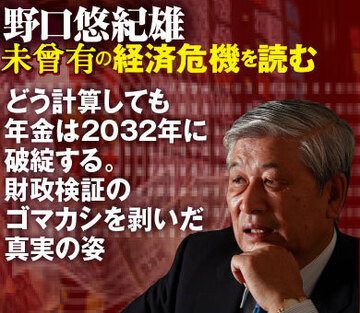野口悠紀雄
第4回
国民経済計算における家計貯蓄率は、1981年の18%超から2008年の2.3%まで、顕著に下落した。では、家計黒字率の変化は、人口の年齢構成の変化とどのような関係があるのだろうか?
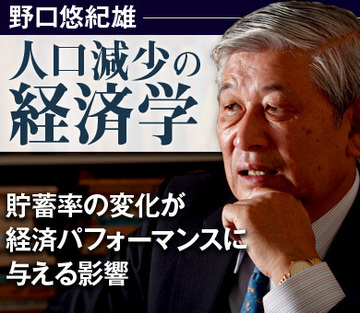
第3回
人口要因が経済活動に大きな影響を与えるのは間違いないが、それだけですべて予測できるわけではない。それは、人口的要因が貯蓄率や資産保有状況に与える影響はかなり顕著だが、資産運用は市場条件にも大きく依存することからもわかる。
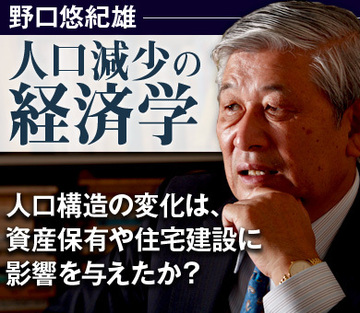
第2回
近年、「家計貯蓄率が低下した」とよく言われることがある。しかし、それは国民経済計算における貯蓄率であり、「所得のうち消費に回さない分」という日常的な感覚の「貯蓄率」は、それほど低下したわけではないことに注意すべきだ。
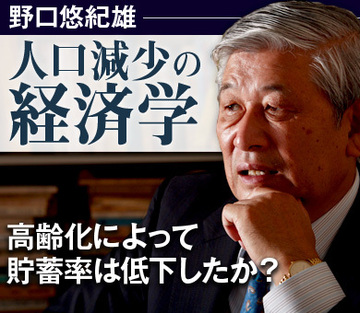
第1回
人口構造の変化と経済パフォーマンスとの関連が、注目を集めている。最近では、日本経済の長期的な不調は、人口減少と密接に結びついているという議論がなされている。
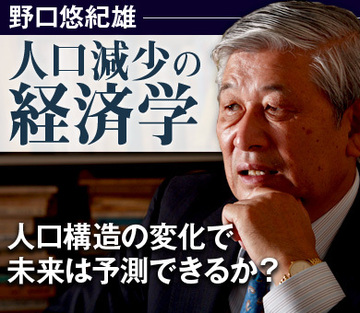
第88回
我が国の年金財政の逼迫は、高齢化が予想を超えて進展したために生じたと思われがちだが、そうではない。「20%の保険料率が必要な制度を4%で運営できる」と誤解して、制度が設計されたことしまったことに基本的な原因があるのだ。
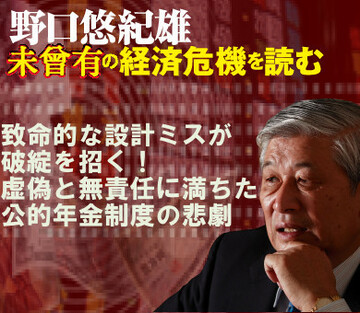
第87回
しばしば「高齢化の進展が年金財政を悪化させた」といわれるが、積立方式の場合、相対的高齢化(世代別人口数の相対的な変化)は年金財政に無関係だ。現在の保険料は60年代末のほぼ3倍だが、これは人口構造の見込み違いでは説明がつかない。
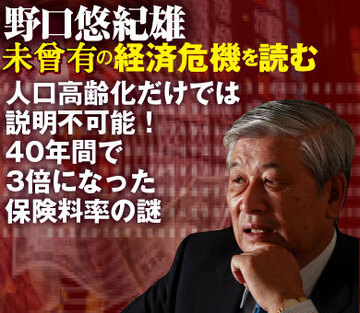
第86回
日本の人口構造が大きな問題を抱えているのは間違いない事実であり、年金をめぐる議論は、「人口高齢化が進めば年金財政は悪化する」ということを自明の理として受け入れている。しかし、それは、自明の理ではない。
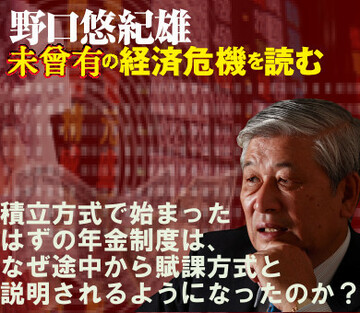
第85回
給与所得だけを対象とする在職老齢年金制度は、公平の原則に反する。高齢者の労働市場をゆがめ、さらに所得の種類によって大きな格差が存在することは非常に大きな問題だ。
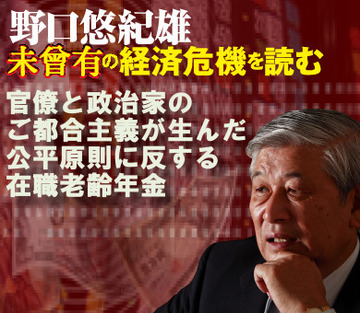
第84回
これまで「在職老齢年金制度の下では、働くと年金が減ることから、高齢者の就業意欲がそがれる(高齢者の労働供給が減少する)」ことを述べてきた。今回は、この問題についてさらに詳しく議論しよう。
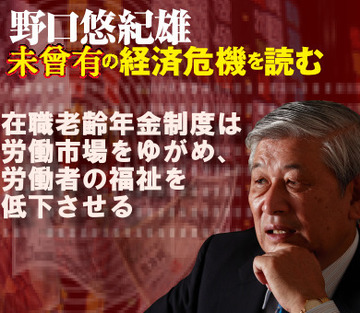
第83回
「年金受給年齢になったら必ず年金をもらえる」と考えている人が多いのではないかと思う。ところが、働き続ける限り「保険料を払い、年金はもらえない」という事態に陥る可能性が強い。これは、「在職老齢年金」という制度があるためである。

第82回
基礎年金に対する国庫負担率は、従来の3分の1から2分の1に引き上げられた。決められた際、「恒久財源を確保して行なう」とされたが、自民党、民主党政権は財源手当を行ってきておらず、年金の積立金を用いる案が浮上しているようだ。
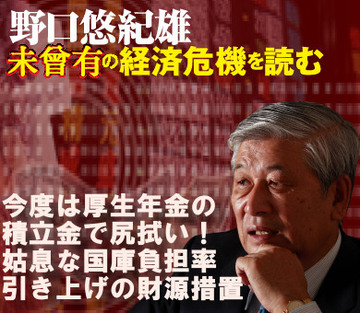
第81回
2009年度における国民年金保険料の納付率は、ついに6割を割り込んで50%台に突入した。国民年金は、風前の灯であるように思われる。しかし、まことに不思議なことに、国民年金の収支状況は納付率が低下するほど改善すると思われるのである。
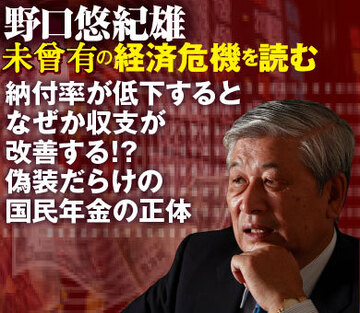
第80回
未納者・未加入者数は、03年度(平成15年度)の490万人がピークで、それ以降は減少している。しかし、納付率は改善していない。「本来保険料を支払うべき人の6割程度しか支払っていない」という異常な事態が生じる原因は、どこにあるのだろうか?
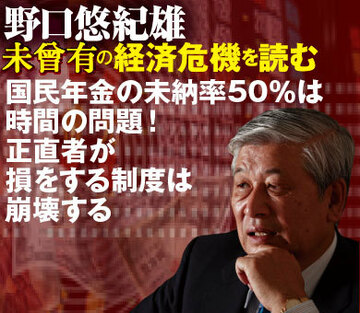
第79回
国民年金の保険料未納の尻ぬぐいは、被用者年金が過大な負担を負うことにより行なわれていると述べてきた。09年の制度改正で、国庫負担率は2分の1に引き上げられたが、これは被用者年金では補えない分の未納対策だったのではないか。
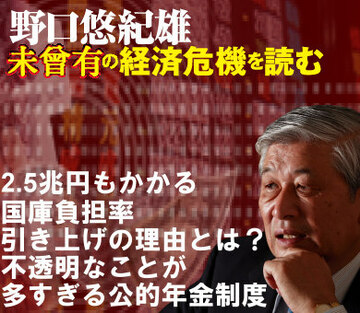
第78回
「納付率が6割程度でしかないのに国民年金が破綻しない」理由は、「すべての年金制度で費用を負担する仕組みになっている」からとされている。しかし真の問題は、負担が不公平に配分されているのではないかということだ。
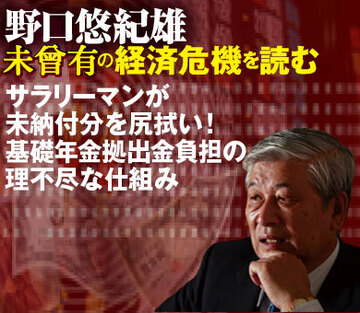
第77回
国民年金保険料の納付率は、信じられないようなレベルまで低下している。2010年3月末での納付率は、59.4%だった。半分近くの人が保険料を支払わない状態で、国民年金制度が維持できるのは、いったいなぜなのだろうか?
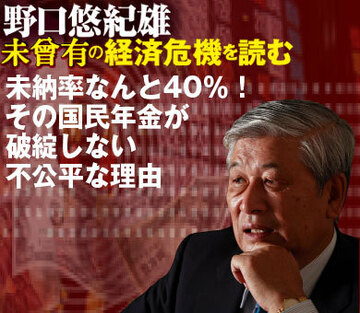
第76回
公的年金の役割は「長生きしすぎることへの保険」だと述べたが、そう考えれば「なぜ効率の悪い公的年金が必要なのか」という疑問が生まれる。しかし、実際の改革にはその考えが反映されていないと言わざるを得ない。
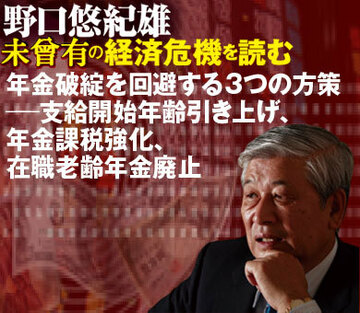
第75回
人口が減少する社会では、国庫負担があったとしても、賦課方式年金は個人年金に収益率の点で追いつかないことを述べた。では、人口減少社会では公的年金の役割はないのだろうか?
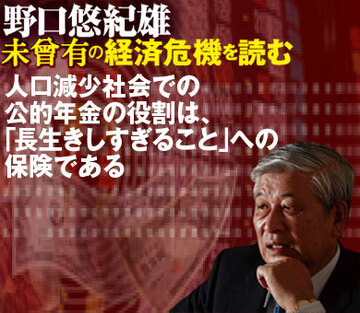
第74回
日本の人口が減少しているなかで、財政検証で想定されている保険料率や国庫負担率では、所得代替率が50%の年金を長期にわたって継続することはできない。では、これを維持するために、国庫負担率と保険料率をどう設定すべきか。
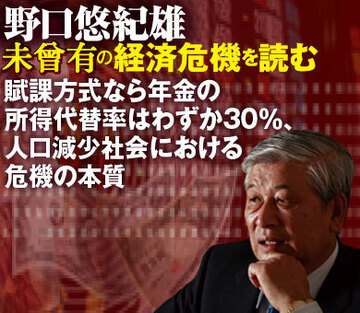
第73回
厚生年金は、今後30年の間に、保険料納付者が8割に減り、他方で受給者が2割以上増えるという事態に陥る。しかし、日本の年金制度は適切に対処しているとは考えられない。それは財政検証にいくつかのカラクリがあるからだ。