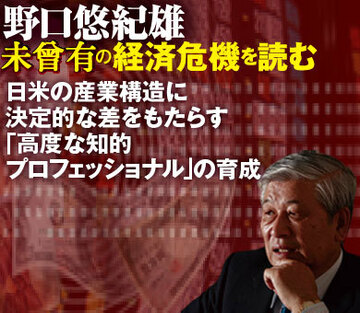野口悠紀雄
第74回
日本の人口が減少しているなかで、財政検証で想定されている保険料率や国庫負担率では、所得代替率が50%の年金を長期にわたって継続することはできない。では、これを維持するために、国庫負担率と保険料率をどう設定すべきか。
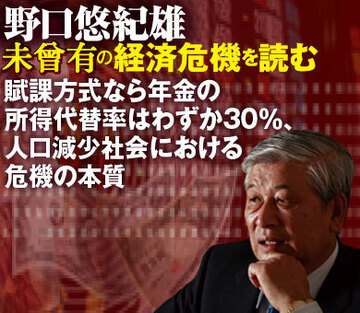
第73回
厚生年金は、今後30年の間に、保険料納付者が8割に減り、他方で受給者が2割以上増えるという事態に陥る。しかし、日本の年金制度は適切に対処しているとは考えられない。それは財政検証にいくつかのカラクリがあるからだ。
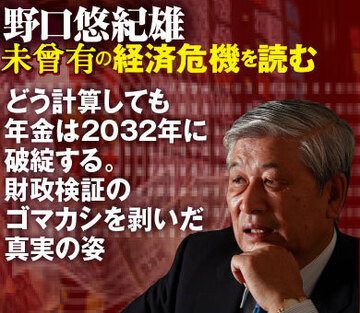
第72回
これまで厚生年金収支のシミュレーション計算を行い、2030年頃までには財政破綻するとの結論を導いた。しかし、これは賃金上昇率1%と物価上昇率2.5%と仮定したものだ。では、これらを0%にした場合、どうなるのだろうか。
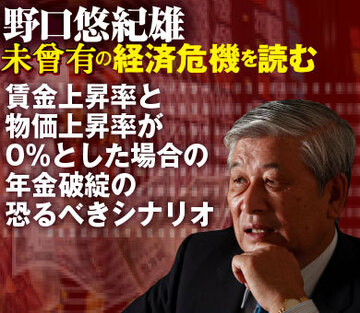
第71回
厚生年金は深刻な財政問題を抱えている。現在の制度を継続して何の対策も講じなければ、20年以内に積立金が枯渇し、年金給付ができない状態に陥る可能性が高い。では、厚生年金制度を清算し、新しい制度をつくることは可能だろうか?
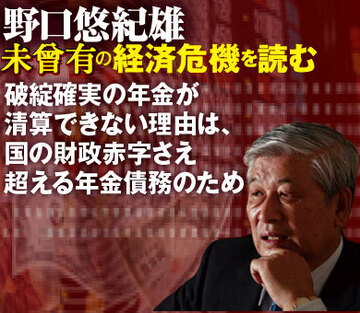
第70回
これまで、現行制度を継続すれば年金財政が破たんすることを述べてきた。それは「現役世代の給与に対して年金給付が高すぎる」とも言える。では、賃金が下落する場合に財政検証通りの給付を続ければ、所得代替率はどのような水準になるのか。
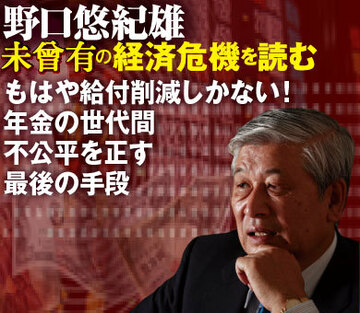
第69回
これまで連載で述べてきたように、「100年安心年金」の経済想定は、現実と比べてあまりに楽観的で非現実的な仮定を置いている。実際はどれほど危機的状況なのか、今回は本格的なシミュレーションを行なってみることとしよう。
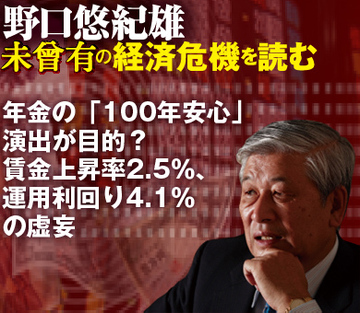
第68回
厚生年金の試算にあたり、厚生労働省の財政検証は「賃金が毎年2.5%上昇する」と想定している。しかしこれは非常に現実離れした想定だ。そこで、賃金は毎年0.5%低下すると仮定すると、厚生年金制度は16年後に破綻することがわかる。
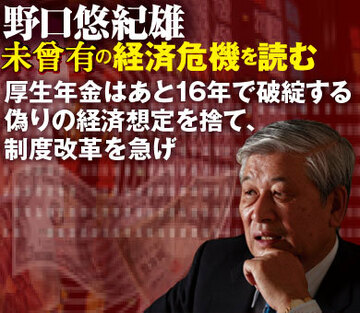
第67回
厚生年金の将来の財政状況は、「財政検証」として今後100年間は積立金はなくならないと推計されている。しかしこれは、経済的な前提条件に強く依存しているため、経済状況の悪化によっては年金財政が破綻する可能性が大いにありうる。
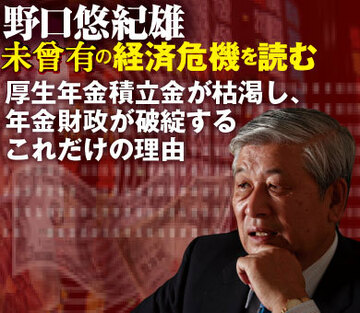
第66回
「企業の利益が増えないので、給与を圧縮せざるをえない」ということが言われる。しかし実際には、利益の動向と給与の動向は逆方向に動いていることが多い。したがって「デフレ・スパイラル論」は、実際のデータに否定される。
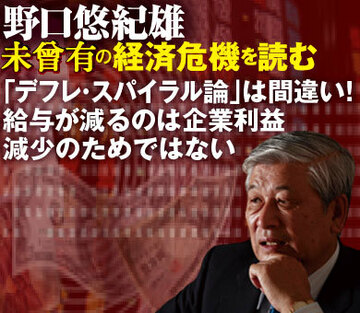
第65回
経済危機によって年金制度は大きな打撃を受けた。ところが、年金は長期的な制度なので問題が存在していても、すぐには顕在化せず、対応は遅れがちになる。しかも、対応が遅れるほど問題が進行するので解決は難しい。
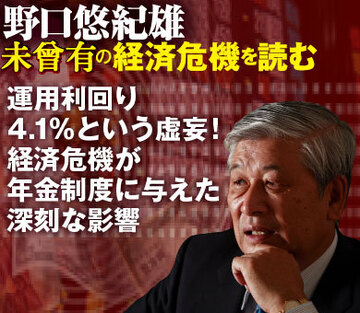
第64回
中国で不動産バブルが生じている。しかし、1980年代の日本で不動産バブルが崩壊したように、中国も早晩そうした事態に直面するだろう。では、これを適切にコントロールすることができるだろうか。

第63回
「円高はデフレを加速するので問題だ」と言われることがある。はたして、そうだろうか?原理的にはありうるが、事態はそれほど単純ではない。消費者物価は、為替レート以外の様々要因に影響されるからである。
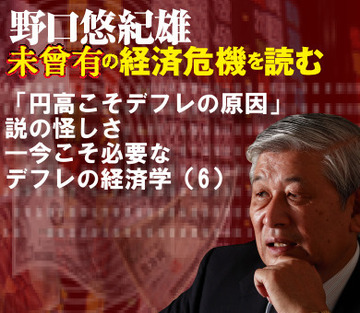
第62回
政府は公共事業を次々に廃止し、景気対策として定額給付金などの移転支出を増加させている。しかし実際は、公共事業が有効需要を増大させていたのに対し、移転支出を増やしても有効需要が増えるとは限らない。
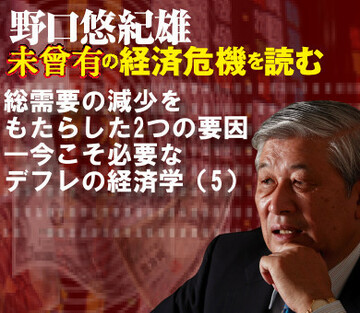
第61回
「デフレ」に関しては、いくつもの誤解がある。日本経済が過去15年もの間、長期停滞から脱却できなかったのは、こうした誤った考えが支配的だったからだ。今回は、ごく普通に見られる典型的な誤りについて述べよう。
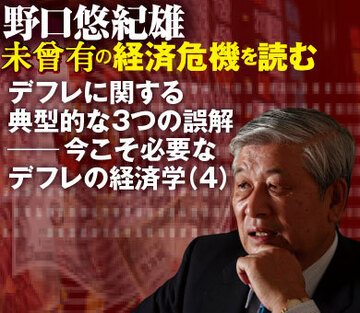
第60回
今回の経済危機で生じた問題は、外生的な需要の減少によって引き起こされた問題であるので、対応が可能である。ただし、金融政策にでは対処できない。それはなぜか。そして、どんな対策なら対処できるのだろうか。
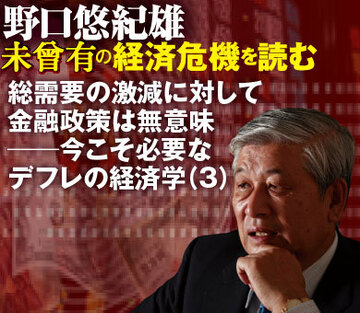
第59回
「デフレの基本的な原因は、新興国からの安い工業製品の輸入だ」といわれるが、それならば世界の先進国すべてがデフレに悩まされているはずだ。しかしなぜ、日本においてだけデフレが深刻な問題になっているのだろうか。
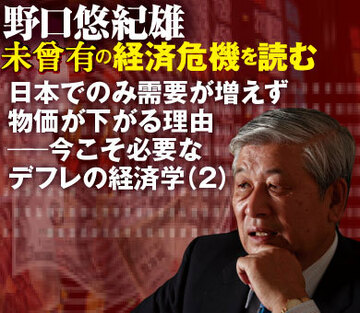
第58回
「現在の日本経済最大の問題はデフレ」とする考えが浸透しているが、これには明示的な経済モデルが示されているわけではなく、感覚的な議論だ。そこで今回から数回にわたり、デフレの経済モデルを明確にしていきたい。
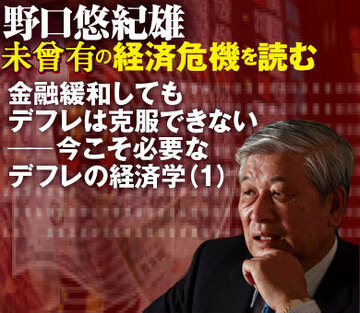
第57回
トヨタや日立などの日本の大企業とアップル、IBMといったアメリカの大企業における1人当たりの時価総額を比較した場合、アメリカが日本を大きく上回っている。両者の間に、なぜこのような差が生じてしまうのか?
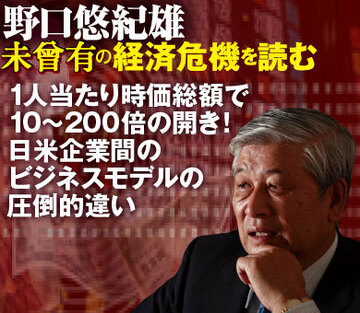
第56回
世界の実質GDPの対前年成長率がマイナス成長から抜け出し、2010年3.9%、2011年4.3%とプラス成長に転じると予測されている。しかし、日本の回復は他国に比べて、はかばかしくなさそうだ。一体なぜなのだろうか。
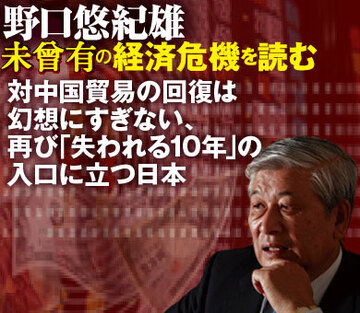
第55回
金融危機を契機に、製造業の利益の落ち込みが激しい。製造業が大きな比重を占める日本としては、この産業構造を今後変えなければならない。その際、製造業の比率がかなり低くなっているアメリカの状況は重要なモデルだ。