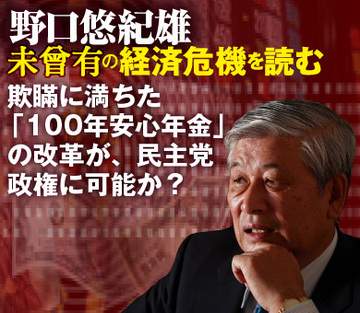野口悠紀雄
第54回
経済危機による利益の落ち込みは全産業で見られたが、非製造業では売上の減少にほぼ比例して利益が落ちたのに対して、製造業では売上の減少率に比べて利益の減少率が大きかった。それは一体、なぜなのだろうか。
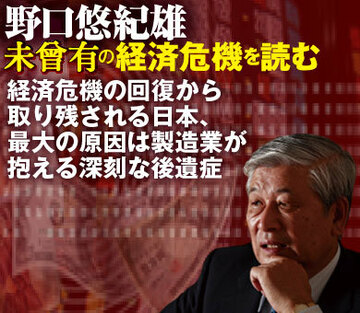
第53回
経済危機によって、日本企業の利益は極めて低い水準に落ち込んだ。利益率低下の原因は、「デフレから脱却できないから」といった議論が一般的になされているが、そうではない。大きな原因は、企業の構造にある。
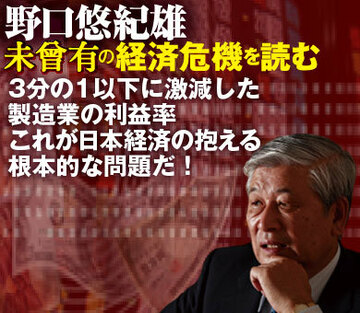
第52回
2010年はどのような年になるだろうか?それは、2010年度予算案を見るとよくわかる。この予算案に対する評価を一言でいえば、「戦略不在」ということだ。「混迷と矛盾と無責任の寄せ集め」と言ってもよい。
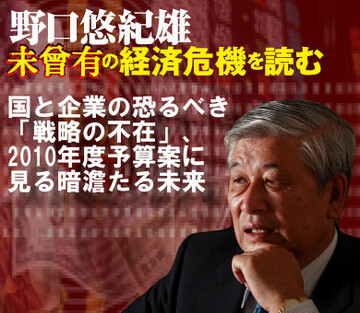
第51回
JPモルガン・チェースが金融危機をくぐり抜けたのに対して、リーマン・ブラザーズは破綻し、シティグループ、メリルリンチも大きな損害を受けた。なぜ、金融機関によるこのような差は生じたのだろうか?
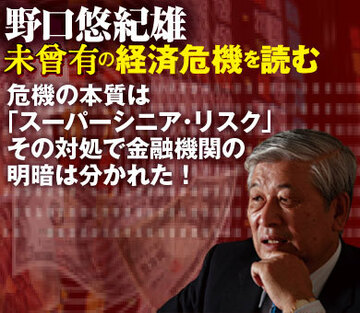
第50回
シティグループとウェルズ・ファーゴが公的資金の返済計画を発表したことにより、アメリカ金融大手6社すべてが政府の支援を離脱する見通しとなった。一方日本は、経済危機によって製造業が受けた被害は未だ深刻だ。
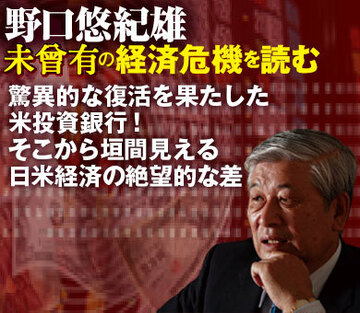
第49回
先日7~9月期のGDP第2時速報値が発表され、実質GDPの前期比年率伸び率が第1次速報値4.8%増から1.3%増に改定された。この大きな改定は、第1次速報値に基づいて取引を行なった人に多大な損害を与えかねない。
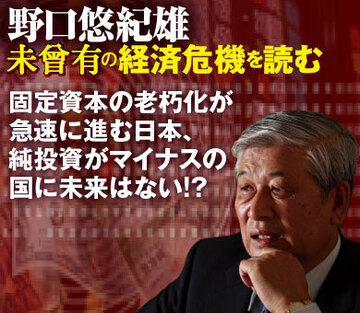
第48回
11月末に為替レートが円高に動き、為替介入や金融緩和などの必要性が論じられた。しかし名目レートだけ見ていると、判断を誤る危険がある。実質実効レートでは、14年前と比較すると、現状はまだまだ円安なのである。
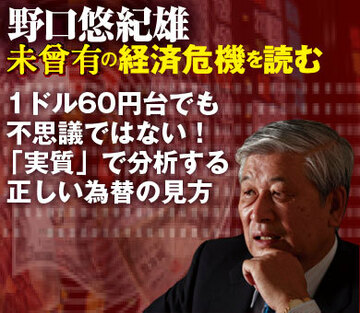
第47回
消費者物価の下落が続き、政府は「デフレ宣言」を出し、「一層の金融緩和が必要」などの主張が多く見られる。しかし、日本で現在起きていることは、金融緩和が不十分なために起きている「デフレ」ではない。
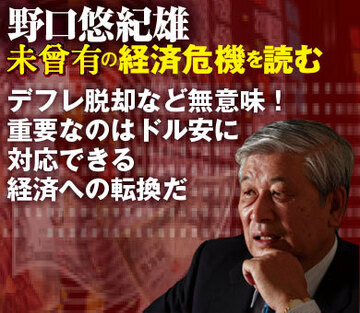
第46回
今年になってからの政府の自動車購入支援策の恩恵で、自動車産業は一息ついている。しかし、支援策がいずれは終了し、輸出が縮小していることを考えると、自動車産業の将来はけっして楽観できない。
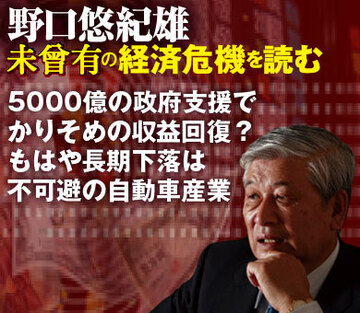
第45回
消費者物価が09年になって下落した。この状況は一般にデフレと言われ、「デフレが続く限り経済活動は活発化しないので、ここから脱却する必要がある」と主張されることが多い。しかし、こうした見解は誤りである。
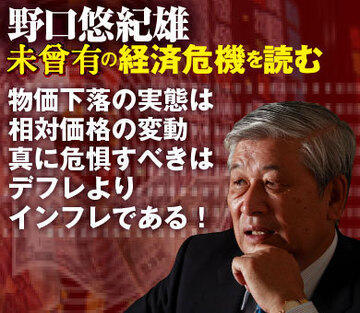
第44回
日本の資金循環構造において1990年代以降の最も大きな変化は、企業の借入残高が減少し、国債残高が増大したことだ。つまり「民から官」へと変化したのだ。今回は、過去15年間に起きた資金の流れを概観してみよう。
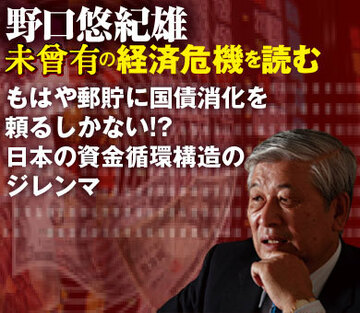
第43回
経済変数が激しく変動しているときは、対前年同期比で指標(成長率)を見ると、錯覚に陥りやすい。なぜなら、比較の対象とされている1年前の数字は、正常なものではなく、かなり落ち込んだ数字だからだ。
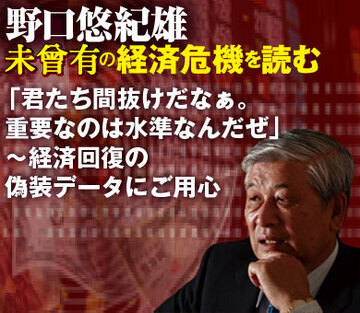
第42回
未曾有の経済危機のなかで、グーグル、IBMなどの先端的IT企業が高い利益を記録している。グーグルは広告業であり、広告業の収入は景気動向に敏感なはずだ。それにも関わらず、なぜ好調なのだろうか?
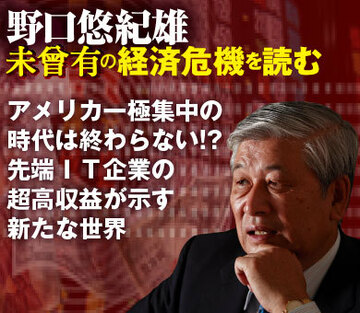
第41回
日本経済は、アメリカとの国際収支の動向で左右される度合いが大きい。さらに現在、投機資金がアメリカから引き上げ、ドル安が生じており、この傾向が続けば、日本の輸出産業に大きな影響を及ぼさざるをえない。
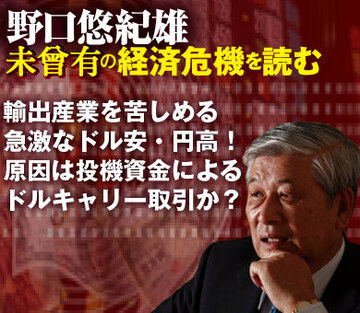
第40回
世界経済危機の影響で、日本の輸出額はピーク時の半分と急激に落ち込んだ。その後、回復に向かっているが、本格的な回復にはほど遠い。今回は、日本の輸出の現状を詳しく分析し、今後動向を考えていきたい。
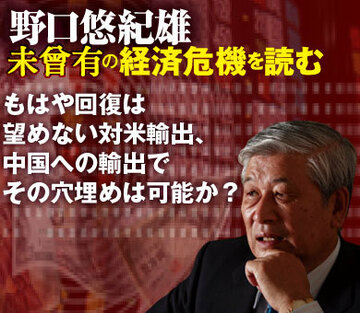
第39回
金融危機への対処はほぼ半分進んだ。しかし日本経済は回復の見込みがない。金融は徐々に回復するようだが、製造業はそうもいかないようだ。つまり、今回の危機で最も大きな打撃を受けたのは、日本ということになる。
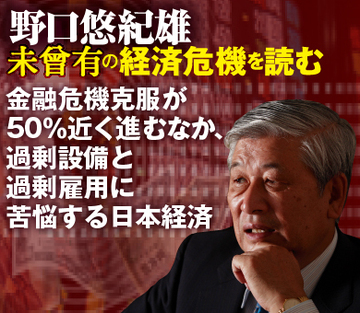
第38回
将来の世界経済が中国の行方に大きく依存することが否定できない今となっては、その実態を掴むことが急務だ。今回は、中国経済の統計データの入手方法やその見方についてせ説明していこう。
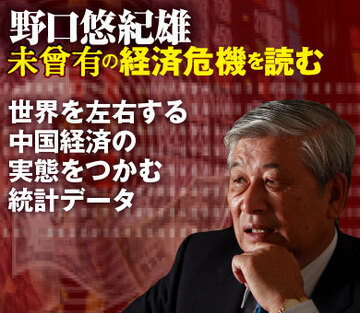
第37回
イギリスの経済統計は、実に使いやすくできている。ただし、慣れるまでは非常に使いにくいと感じるかもしれない。そこで今回は、イギリス経済統計のシステムに慣れるために、使い方を具体例で説明することとしよう。
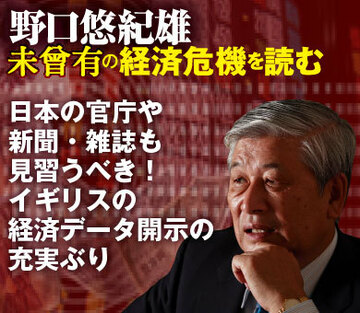
第36回
ウェブにおける経済データの提供方式が最近変わってきた。これまでの固定的な表では、必ずしも利用者の目的に添ったデータは得られなかったが、自分用にカスタマイズした統計表が作成できるよう変化してきたのだ。
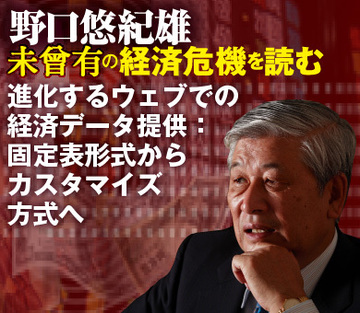
第35回
「100年安心年金」と呼ばれる年金制度。しかし、給付水準が約束されたと思っていたらそれは勘違いに過ぎない。約束されているのは保険料負担だけである。安心できるのは、制度運用者の政府で、国民ではないのだ。