
小川たまか
日本ラグビー協会理事、新リーグ審査委員長を昨年退任した法学者の谷口真由美さんが、自身の経験を新刊『おっさんの掟 「大阪のおばちゃん」が見た日本ラグビー協会「失敗の本質」』(小学館新書)としてまとめた。谷口さんに、その実情などを聞いた。

時には大きな炎上のきっかけとなるジェンダーにまつわる問題。2022年を迎えるにあたって、2021年の「ジェンダー」関連ニュースを振り返ってみたい。

東京・有楽町の映画館で予定されていた、特別上映「キム・ギドクとは何者だったのか」の中止が発表された。キム・ギドク監督は昨年、新型コロナウイルス感染症で死去。その死は一部のファンに衝撃を与えたが、一方で性暴力の告発を受け、韓国映画界から「追放」された人物でもあった。日本での特別上映について、ツイッター上で強い批判の声が上がっていた。

2021年3月6日に、名古屋入国管理局の施設で、スリランカ人のウィシュマ・サンダマリさん(当時33歳)が亡くなった。遺族や支援者が真相解明を求める一方で、ネット上では心ない虚偽の内容も出回っている。一体なぜ、死者が出た事実の背景を知るための行動が、一部から批判されるのだろうか。

性暴力が報じられるとネット上では二次加害(セカンドレイプ)にあたるコメントが書き込まれることが多く、男性の性被害の場合はさらに理解のない中傷にさらされがちだ。無理解や偏見は変えていかなければならない。

ジャーナリストの伊藤詩織さんが、元・東京大学大学院特任准教授の大澤昇平氏を訴えた民事訴訟で、東京地裁は大澤氏に損害賠償の支払いを命じた。しかし大澤氏はその後も「勝訴しました」「7:3で俺が大勝」などとツイートし、見る人をあぜんとさせている。

今年から公立学校で試験的にスタートしている「生命(いのち)の安全教育」。性犯罪・性暴力の被害者にも加害者にもならないための教育であり、中身は「性の安全教育」だが、そのように名付けられていない。識者は、2000年代の性教育バッシングの影響が今も残ると指摘する。

カメラが貴重品だった時代とは違い、現代では多くの人が撮影機能のついたスマートフォンを持ち歩いている。盗撮事案は増加の一途をめぐり、ネット上で拡散される被害も後を絶たない。この状況に歯止めをかけるものはあるのだろうか。

今国会で成立する見通しのストーカー規制法改正案。成立すればGPSでの監視行為を規制対象に盛り込むこととなる。一方で、被害当事者や支援者は、不足の論点を訴えている。

東京オリンピック・パラリンピック組織委員会・森喜朗前会長の女性蔑視発言で、ジェンダー問題が注目されているが、発言を差別的と捉える人と、そうではない人の認識の差が顕著になっている。80年代から「男女共同参画」などの動きがあったにもかかわらず、なぜ日本はジェンダーに関して遅れているのか。そのヒントは、2000年代の「バックラッシュ(反動)」にある。モンタナ州立大学社会学・人類学部准教授の山口智美さんに話を聞いた。

性犯罪の報道では、証拠や具体的な証言が伏せられることがある。被害者への配慮などからだが、伏せられることで読者が違和感を覚え、「性犯罪は証拠もないのに有罪になる」といった誤解を生むことがある。性犯罪の被害者への偏見が残る社会で、報道「しない」ことによる二次被害を考えたい。
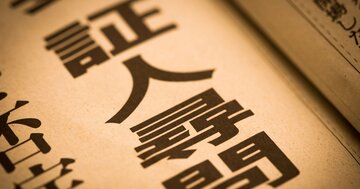
毎年11月12日から25日までは「女性に対する暴力をなくす運動」期間とされている。コロナを機に増えていると言われるDVの相談や、あるいは性暴力被害について、適切な情報を必要な人に届ける必要がある。

酒気帯び運転で逮捕された元TOKIOメンバー、性犯罪の再犯事件を起こした元ヒステリック・ブルーのギタリストと、有名人による再犯事件が相次いだ。これまで多くの受刑者や出所者と面会し、その社会復帰や再犯防止活動を見てきた月刊誌『創』の編集長・篠田博之氏に話を聞いた。

長期政権がついに終わる。安倍政権が「女性活躍」を打ち出す一方で、ジェンダーギャップ指数は下がり続け、昨年は121位。当然ながら、G7の最下位で、世界との差を見せつけられた。安倍政権がうたった「女性活躍」について、女性記者たちはどう思っているのかアンケートをした。すると、ここ数年で「世論のボトムアップ」により報道が変化してきていることが見えてきた。

世界的なコロナ禍で、国外との行き来が以前より難しくなっている。海外で暮らす日本人たちは、どのように過ごし、どんなことを考えているのだろう。今回はドイツに暮らす女性にオンラインでインタビューした。

今月始め、人気俳優の新井浩文容疑者が強制性交の疑いで逮捕されるなど、性犯罪に注目が集まっている。2017年の性犯罪刑法改正は、強姦罪が強制性交等罪となるなど110年ぶりの大幅改正だった。しかしさらなる問題点も指摘されている。性犯罪の不起訴が多い理由はどこにあるのか。

中央大学の学園祭で、学生主催によるイベント「AVの教科書化に物申す!」が行われた。AV俳優3人とAVメーカー社長、産婦人科医が登壇したイベントの内容は……。

「人を性的に傷つけないための教育」を受けたことがある人はどれほどいるだろうか。実際に性犯罪加害者は世の中にいる。加害者にならないための予防教育は、果たして可能なのか。

2020年の東京五輪は、決定の瞬間こそ大きな興奮に包まれたものの、その後諸問題が相次いで顕在化したこともあり、足もとでは興奮が薄れつつあるように見える。東京五輪の「盛り下がりムード」を食い止めることはできるのか。

足もとでは「毒親」に関する報告例が、以前にも増して増えている。子どもに愛情を注いでいるつもりでも、逆に子どもの心を痛めつけてしまう「毒親」とは、どんな人々なのか。自分に「毒親」の資質はないかも、気になるところだ。
