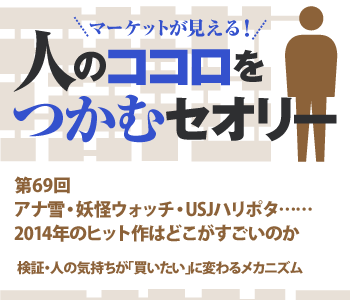藤田康人
第88回
マーケティング業界では今、「カスタマーセントリック」(顧客中心主義)が熱く語られている。日本企業が再び世界のマーケットで優位に立つには、劇的に変わりつつある外部環境に対応するためにも、「カスタマーセントリック」のアプローチ手法に徹することが急務である
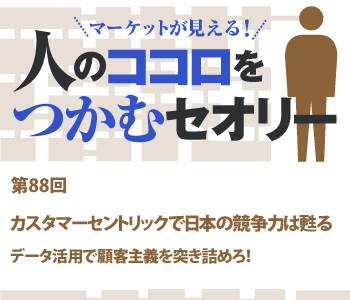
第87回
聞き手が思わず引き込まれるプレゼンテーションは、どこが違うのか。良いプレゼンテーションの要素は、マーケティングにおけるコミュニケーションの設計においても盛り込むべき要素である。消費者に対して企業やマーケターが心を配るべきこととは。
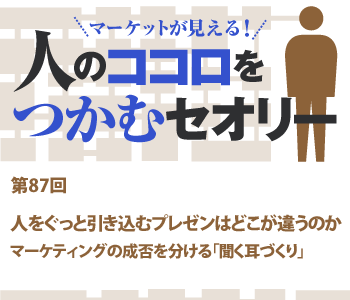
第86回
情報量が爆発的に増えた今、企業が発信する情報は消費者に3つのパターンでスルーされてしまう。「その情報を受け取ると、何かを得する」と思ってもらえるにはどうすればよいのだろうか。
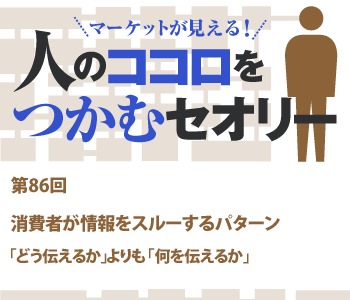
第85回
マーケティングがうまくいかない企業の多くは、それが「コミュニケーションの手法やテクニック」」に終始している場合が多いという。世界の潮流はすでに、さまざまなステークホルダーの関係をマネジメントする戦略的ビジネス・プロセスの統合というステージに移行している。
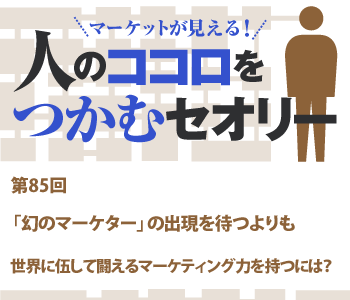
第84回
ドラマ『恋仲』がじわじわと視聴率を上げている背景には、ネットでの情報拡散効果があるらしい。視聴者が『恋仲』のパロディを撮影・投稿した動画が反響を呼ぶなど、その拡散の仕方も新しい。なぜ、ここまでネットで盛り上がるのか。その仕組みを検証する。
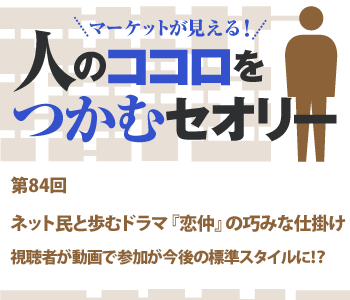
第83回
腸内細菌が、認知症やうつにも関連することが最近の研究で分かってきた。食品への機能性表示が解禁された今年、市場は「○○に効く」サプリや健食でにぎわっている。規制緩和に乗るだけでなく、腸内環境改善に資する新マーケットの開拓に挑んでいきたいものだ。
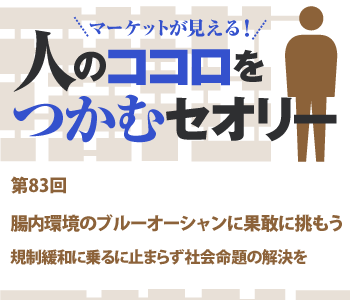
第82回
NIKE行ったキャンペーン「RE2PECT」が、カンヌのインテグレーテッド部門でグランプリに輝いた。世界平和を訴えるクリエイティブが大賞を総なめにする中、人の心を動かす内容に徹したクリエイティブの受賞に、著者はマーケターとしての信条を新たにする。
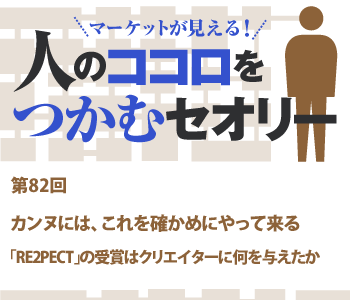
第81回
今年のカンヌライオンズでは、以前にも増して人間性を重視した作品に評価が集まった。人間性を前面に押し出す以外にも、人を動かすクリエイティブはあるのに、と違和感を覚える筆者。しかし、この「人間性」こそ、今、世界で多くの人が心底求めているものだった。
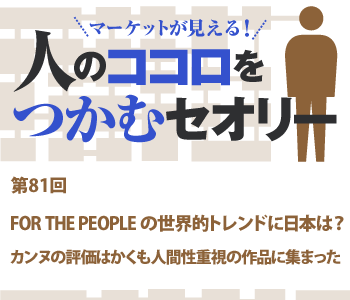
第80回
アップルやサイバーエージェント、LINEなどのインターネット企業が、ストリーミングによる定額制音楽配信サービスに乗り出した。これは、アクセス権に対価を払うモデルが一般化する序幕なのか。コンテンツビジネスは今後どうなる?

第79回
今年の春の早慶戦(慶早戦)は、学生の作成した「挑発ポスター」が話題となって、大いに盛り上がった。手作りの数枚のポスターがものすごい勢いで拡散し、多くの人びとの気持ちをつかんだ構造をマーケティングの切り口から検証してみよう。

第78回
日本を訪れる中国人観光客の“爆買い”は、依然勢いが衰えず、日本製の温水洗浄便座の人気ぶりなどが大きく報じられている。自社製品も“爆買い”して欲しいという企業は、どんな対策に打って出ればよいのだろう。
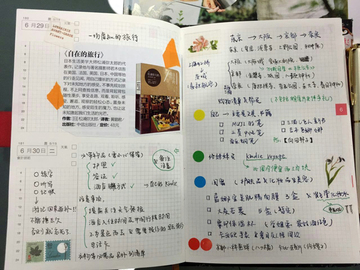
第77回
消費者が広告を避ける傾向にある中、既存商品の新しいを価値を伝えるには…? 女性の変身願望というインサイトを、メイク落としのプロモーションで実現した著者の手法を紹介する。

第76回
デジタル写真全盛で、写真は記録として撮り溜めるものと化してしまった今日、フィルム式カメラで撮った写真集めた古いアルバムを見た著者。そこからありありと昔の記憶がよみがえる実感をつかんだという。デジタル写真をオンラインで整理できるフォトブックを使って、写真を編集してみたら……。

第75回
「○○に効く」といった機能性表示が解禁されることで、健康食品などの売り上げが拡大するのではという期待が持たれているが、どうだろうか。著者が10年前に仕掛けた食物繊維入り食品のプロモーションの際に分かったことを振り返り、検証してみる。

第74回
映画『シンデレラ』公開に合わせ、有名ブランドがガラスの靴を再現するなどの動きが活発だ。ワコールは「ガラスの靴」の持つ文脈を自社のキャンペーンに引用。「ガラスの靴」といえば、消費者はどんなイメージを想起するだろうか……。

第73回
顧客企業の仮説に判を押すためだけに行う市場調査が、今日も存在する。また一方では、スーパーの売り場の効率化と市場調査が混同されている。企業は、自社の思い込みに後ろ盾を作ることなく、「ゼロ次仮説」で直接消費者に聴く姿勢を持たなくてはならない。

第72回
バレンタインデーの「義理チョコ」に、男女双方から不要論が持ち上がっている。諸外国では、バレンタインデーは、男性から女性に愛情を伝える日。日本でもそろそろ、チョコを配る儀式から、若者が恋愛行動を起こすような仕掛けを楽しむ日にしてみてはどうだろうか
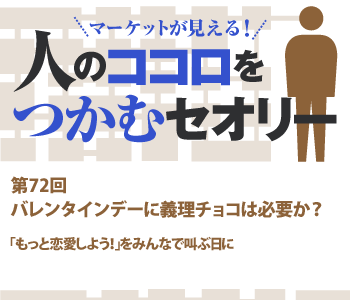
第71回
2014年の訪日外国人観光客は1341万4000人、消費金額は2兆305億円に上り、これらはいずれも過去最高を記録した。景気が低迷する中、企業にとって彼らは大変貴重なお客様だ。インバウンド消費への対応が経済復活の柱の一つとなるだろう。
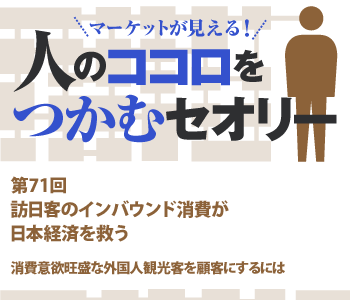
第70回
食品への異物混入が相次いで報道されるなか、製造元が混入の事実を知り得る前にソーシャルメディアで「証拠写真」が出回るケースが生じている。こうした思わぬ形で「事実公表」がなされる事態に、企業はブランドをどう守ればよいのか。新たなリスクマネジメントの課題である。
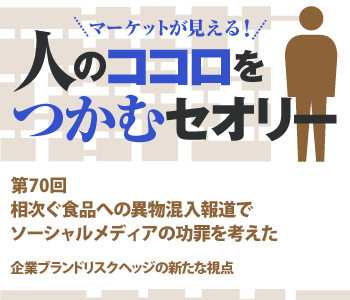
第69回
アナ雪・妖怪ウォッチ・USJハリポタ…今年のヒット作品に共通するファクターを著者が分析。モノが売れない時代に売れる商品を生むには何が必要なのか。人の気持ちが「買いたい」に変わるポイントを検証してみる。