山口 博
大相撲5月場所で新大関貴景勝が休場、再出場、再休場を繰り返した。極限まで頑張ったと評価する声もあるが、私には全くそうは思えない。玉砕することは、持続的成長のために百害あって一利なしだ。

ドラマ「わたし、定時で帰ります。」では、吉高由里子演じるヒロインが、働き方改革のモデルを示して、仕事観、結婚観、人間関係、ブラック企業などの問題に直面しながら解決していく。しかし、現実には、ドラマのように理想通りに実現できるのだろうか。

有給休暇取得が義務付けられたところ案の定、有給休暇取得に奨励金を出す企業が現れた。給与や賞与で労働の対価を支払う半面、労働しないことに手当を支払うこの奨励金は、使い方を間違えれば会社を壊すことになりかねない。
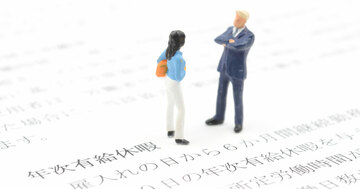
経団連が一括採用を廃止し、通年採用の方針を打ち出した。通年採用の実現は、企業と学生のミスマッチを解消するだろう。加えて、もう1つの、とても大きな効果をもたらすに違いない。

働き方改革関連法案が施行された今ほど、多様なメンバーを巻き込むボトムアップのリーダーシップが必要とされている時はない。しかし、トップダウンの呪縛から逃れられないリーダーやメンバーがいる。

イチローの引退会見で、イチロー節がさく裂した。その中には、ビジネスパーソンが用いるコミュニケーションとは真逆の、しかし、見習った方がよいポイントが含まれている。

統一地方選挙が始まる。4年前の前回は、行政の長の3人に1人が無投票当選していた。無投票当選は、民主主義を実現する目的とは逆行する問題規定だ。実は同様の問題がビジネスシーンのあちこちにあるのだ。

働き方改革の対応策として、深夜や休日のメール禁止というルールが設けられるケースがある。このルールは結局、夕方や金曜、月曜朝一番のメールを増やすだけだから、時間外労働の抑制、ストレス緩和には限界がある。一律のルールではなく、メールを受信する側のスキル向上が不可欠なのだ。

就活・転職で「自分が成長できる会社」かどうかを見極める5つの観点
今春の新入社員は、自らの成長が期待できるかどうかで企業を選択していることがわかった。しかし、それを見極めることは容易ではない。過去の演習経験から、見極めのために最も効果の高い5つの観点を紹介したい。

嵐が活動休止を発表した。記者会見では「無責任じゃないか」という質問も飛び出し、その質問自体が袋叩きにあっている。これは、組織に果たす責任と自分の裁量の両立の問題だ。

厚生労働省の「毎月勤労統計」で長年不適切な調査が行われ、雇用保険など計500億円余りもの支給不足があった問題が発覚した。裁量労働適用者の労働時間調査、障害者雇用水増し問題に続くトンデモない事態だ。

ターミナル駅前の大書店の店員が全員マスクをして対応している場面に遭遇した。声も聞こえない、表情もよくわからない。わが国を代表する書店のその対応は、日本の来客対応が変わりつつある兆しなのではないか。

JALの副操縦士から、乗務前にアルコールが検知され、実刑判決が言い渡された。これを受けてJALは懇親会・忘年会での飲酒自粛を通知した。全面禁止は問題解決に役立つのか。

平昌五輪カーリング女子日本代表の試合中の掛け声「そだねー」が、今年の新語・流行語大賞に選ばれた。「そだねー」という極めて素朴な言葉に、いったいなぜ人を引き付けるパワーがあるのか。

第110回
蓮舫議員と桜田五輪相の国会での問答が海外メディアを含めて取り沙汰されている。この、いわば珍問答が違和感を与えるのは何なのか。桜田五輪相の資質の問題以外にあるように思えてならない。

旧財閥系企業グループの1社であるA社の、東京・大手町にある本社受付を訪問した時のこと。数人の担当者が並ぶ大きな規模の、調度も荘厳な受付カウンターだったが、受付スタッフのひどい対応に目が点になった。

熊本市議会で「のど飴」を口にしながら発言しようとした議員が、出席停止処分を受けるという騒ぎが起きた。海外メディアからは、議会が処分したことは、日本の融通の利かなさの証しだとして批判を受けている。「のど飴」をなめながら会議や仕事をすることは是なのか、非なのか。

労災認定された5人のうちの3人が裁量労働の社員だった三菱電機が、長時間労働を是正するために、裁量労働制を全廃した。しかし、裁量労働制を全廃すれば過労死がなくなるとは、私には思えない。

メールのタイトルに【重要】【要返信】と書かれているメールを立て続けに受信した。こうしたメールは、相手にストレスを与えるだけで、返信率を高めない。管理徹底は効果を上げず、人も育てないので、やめた方がよい。

日本体操協会のパワハラ問題が紛糾している。指導を受けていた選手は、コーチはパワハラをしていないと言い、日本体操協会の幹部をパワハラで訴えた。しかし、実際にコーチの選手への暴行映像は存在する。このややこしい問題、どのように考えればよいのだろうか。
