
宿輪純一
第62回
日本の決済インフラはリアルタイム(即時)振り込みを始め、利便性・効率性・安全性の決済の3つのポイントで現在でも世界最高水準であり、海外と比べて進んでいる。さらに決済改革は継続中で、さらに機能が向上し世界最高峰に近づいている。

第61回
中央銀行が資産を大量に購入するなどして官製市場となり、市場機能が止まり経済に悪影響が出ることを海外では“JAPANAIZATION(ジャパナイゼーション、日本化)”と呼んでいる。先日、米国出張でFRBやIMFを始め金融機関等のエコノミストと意見交換をして驚いたのは、日本以上に日本の金融政策に厳しい見方をしていたことだ。

第60回
先日ワシントンのFRB本部、IMFや世界銀行のエコノミストと面談してきたが、そこで気がついたのは、原油価格の動きをかなり重視しており、物価の基本として見ていることだった。原油価格を重要なインフレの先行指標としているのである。

第59回
1997年5月のアジア通貨危機では、IMFの対応が後手に回る中、日本は財務省・日銀を中心として、アジアにおける金融先進国としてイニシアティブを取り、ASEAN+3(日本・中国・韓国)の金融協力を構築してきた。それからちょうど20年の今年、GWに横浜で、ADB総会とともにASEAN+3の総会が開催される。日本もホストカントリーとして会議を主催し、リードする。
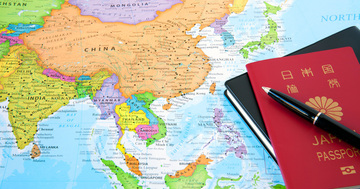
第58回
先月、ニューヨークとワシントンに出張してきた。FRBやIMFを始めとした主要な経済・金融関係者約20人との面談を実施してきた。そこで感じたのは日本国内では分からない、トランプノミクスによって米国経済に対するマインドの方向感が“楽観的”へと変化したことであった。

第57回
JETROという組織を知っているだろうか。経産省所管の独立行政法人で、日本の貿易の振興を主目的とする。筆者が特に注目しているのは、その「中小企業の輸出や進出等の海外展開の支援」であり、また彼らの営業能力の高さである。

第56回
日銀は昨年9月、長短金利操作(イールドカーブコントロール)を開始した。これは長期金利(10年物国債金利)を「0%程度」で推移させることを目標としたものだ。しかし金融市場というものは予想外のことが起こるものである。

第55回
経済の歴史は政治的だと感じることが多い。特に欧州の経済統合・ユーロについてはそうだ。理論では各国は経済的に同レベルであることが基本だが、最近の移民問題にしても、南欧危機を見てもわかるように現実はそうではない。欧州統合は、そもそも政治的な動きなのである。

第54回
英国のEU完全撤退表明でポンドが上がる理由
英国のメイ首相のEU完全撤退表明後、英ポンドは大幅高になった。この動きには違和感を持った人も多いのではないか。今回の表明に際しては、離脱交渉について上下両院(貴族院と庶民院)の承認を求めるとした。ここが英ポンド大幅高のポイントである。

第53回
本連載や宿輪ゼミにおける為替相場の分析・予想については、その後、当局や金融機関から内容についての照会を多数受けた。そこで今回は、今年当面の主要通貨の動きを予想してみたい。

第52回
財務省と日本銀行が組んだ量的金融緩和=国債購入政策がまさに限界に来ている。2017年の金融政策は、日本の長期金利(10年物国債金利)のプラス0.1%をめぐる攻防が焦点になるだろう。今回はその理由を解説しよう。

第51回
金融庁が金融機関の監督・検査姿勢を大きく転換、森信親長官の名を冠した「森ドクトリン」が注目を集めている。その対象は銀行、とくに影響が大きいのは地方銀行だ。この転換は貸出が減少し、国債金利の低下で収益が厳しい地銀の経営に与える影響が極めて大きい。

第50回
2017年の世界経済は見通しが難しい。それは今回ご説明するトランプノミクスの実現(米国)、EU離脱の行方(英国)、黄信号の経済(中国)、限界の金融政策(日本)といった4つの経済的課題があり、それぞれに予断を許さないからである。

第49回
英国のEU離脱、南欧の財政悪化など環境が複雑な欧州経済だが、よく見ると、昔から変わらない基本的な経済的な構造がいつも見えてくる。この構造を知っていると欧州経済に対してより理解が深まることになる。

第48回
トランプ大統領誕生で「トランプショック」が発生し、金融市場は乱高下した。遡れば今年6月23日には英国での国民投票で英国のEU離脱が、これも大方の“予想”を裏切って決まり市場は荒れた。どうしてこのようなことが起こるのか。

第47回
中国人民元(CNY/RMB)の対ドルの下落が止まらないが、この今回の下落は、当面続くと考えている。今回はその根拠を解説しよう。とくに10月に入ってからの下落が大きいのには理由がある。

第46回
最近ではフィンテックという言葉を見ても目新しさを感じなくなってきたが、現段階で実用化されたものは少ないのではないか。実は、銀行をはじめとした金融業の発展の一側面は、まさにIT導入の歴史であり、最近の「いわゆるフィンテック」に限ったことではない。

第45回
現在、ドル安円高傾向で推移している為替相場であるが、今後、年末から来年にかけては逆にドル高円安方向に動くと予想する。今回は、その予想の分析プロセス・事由等を説明しよう。

第44回
日銀の「新手法」が銀行経営を改善しインフレ率を上昇させる仕組み
日本銀行は金融政策を変更し「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」とした。長短金利操作とは、日銀はイールドカーブ・コントロールと言っているが、要は、今回は短期金利をそのままに、長期金利を上げるよう操作する。これは銀行経営を改善しインフレ率を上昇さるだろう。

第43回
現在、金融市場において最も注目されているトピックは、米国の中央銀行:連邦準備制度理事会の利上げである。それは、為替・株式をはじめ、金融市場、そして世界経済に対する影響が極めて大きいからだ。筆者はFRBの利上げは12月と予想している。それを詳しく解説したい。
