
鈴木明彦
安倍首相は6月10日、2%の物価目標は達成していないが、本当の目的はたとえば完全雇用を目指すことであり、その意味で目標は達成している、と述べた。この発言は、消費増税の地ならしと考えてよさそうだ。一方、金融政策の正常化は先送りされそうだが、バブルを防ぐためにも逃げてはいけない課題だ。いずれ出てくるデフレ脱却宣言が最後のチャンスとなろう。周到な準備が必要だ。

米中貿易戦争では米国が有利であり、中国はいずれ妥協せざるを得ないという論調が多い。米国に中国を叩いてもらいたいと内心思っている日本人も少なくないだろう。しかし、希望的観測にすがっていては判断を誤る。「踏み絵」を迫られる日本が選ぶべき道とは。

3月の景気動向指数の基調判断が「悪化」に変更され、「緩やかに回復」の政府の公式見解とは違う判断になった。最新の景気動向指数で改めて判断すると、15~16年も「悪化」だ。

毎月勤労統計など政府統計の不正問題が注目されている。確かに、統計が信頼できなければ景気判断もおぼつかず、経済政策の運営は困難になる。しかし、政府の景気判断がしっくりこないのは統計不正が原因ではなく、「素直な判断」ができていないからだ。

世界経済の変調や米国の利上げ停止で金融正常化が遠くなっただけでなく次の景気後退に打つ手がないといわれている日本銀行だが、長期金利の変動幅を柔軟にした枠組みのもと「追加緩和」に踏み出している。

長くデフレが問題視されてきたが、消費者は企業が販売価格は変えないで量を減らしたり質を落としたりする「見えない値上げ」を感じている。これが広がれば成長を妨げる恐れがある。

政府の景気判断に従えば、来年1月には「戦後最長の景気拡大」を達成することになる。それが既定路線になっているが、しかし在庫循環や景気動向指数の動きから判断すれば、景気後退はすでに始まっている。

日本銀行の「政策修正」の意図を忖度すれば、「脱デフレ」の金融政策を終わらせようと動いていることがわかる。長期金利の上昇余地を作っただけでなく「マイナス金利」をやめる布石も打ったと考えられる。

「量」の拡大から、高付加価値の製品やサービスを生み出す「質」の向上で経済成長するのは成熟化の現れだが、賃金は増えなくなった。改良型の質の向上ではその分を価格に転嫁するのが難しいことが一因だ。
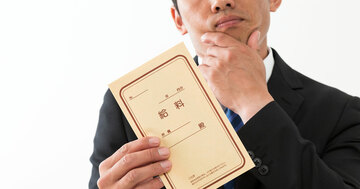
米中貿易摩擦は日米摩擦とは違い、覇権を求める大国を軸にした“貿易戦国時代”につながる可能性がある。日本が生き残る道は、米中との「連衡」でなく、覇権を求めず自由貿易の価値観を共有する国との「合従策」だ。

デフレとの戦いが泥沼状態に陥っているのは、政府が金融緩和圧力をかけ続ける思惑から「デフレ脱却」の定義を厳しくしたからだ。緩やかなデフレを受け入れ「2%物価目標」の運用を柔軟にすれば、デフレを「敵」とみなす必要もなくなる。
