
片桐あい
職場で感情をあらわにして涙を流すことは、社会人としてネガティブな行為だと認識されている。しかし現実には「職場で、人前でも泣く人」というのが存在する。泣かせたのが上司だとなれば、イマドキはその上司がセクハラだ、パワハラだと言われかねない。特に1対1のやりとりで部下が泣き出した場合、それは上司のハラスメントに当たるのだろうか?

最近遅刻が多い部下に対して、気遣ったつもりで声をかけたら、「プライベートに踏み込むのはセクハラです」と反論されてしまいました。このやりとり、あなたならどう感じますか?「遅刻に対して指摘することもできないのか」と頭を抱えてしまう人もいるかもしれません。遅刻や有給休暇の取得など部下の勤怠を管理するのは上司の責務ですが、時にこのようなトラブルになってりまうことがあります。上手に部下とコミュニケーションを取るポイントについて解説します。

ケアレスミスが多い部下に対して「作成した書類に誤字が多いから、確認してから提出してください」と指摘した上司。すると部下は「私だって一生懸命やっているんです!」と泣きながらトイレに駆け込んでしまいました。業務上のミスを指摘しただけで、部下に泣かれたらどう指導していいか分からない。もしかして「パワハラ」と呼ばれてしまうかもしれない……。こんなとき、上司は部下に対してどう接したらいいのでしょうか?

分析や批判はするものの、なかなか行動が伴わない…という人がいます。そんな人が部下だった場合、上司はどのように関わって、「実行し成果を出す」ことを促せばいいのでしょうか。

優秀だけど周囲と関わるのが苦手な人は少なくない。そんな部下こそ、上司の働きかけが肝心だ。能力を生かすも殺すも上司次第。どんな関わり方ができるのか考えてみよう。

2023年に入社した新人の育て方についてお伝えしてきた本連載も、最終回。今回は、今年の新人たちに実際に起きた出来事を2つ紹介し、先輩や上司が彼らとどう関わっていくべきかについて考えてみましょう。正解は1つではありませんが、これから紹介する事例が何かのヒントになればと思います。
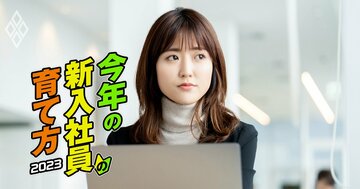
早いもので、もう12月です。新入社員が入社して8カ月ということになります。新人たちも多様な経験を積んできたでしょう。順調に成長している者もいれば、困難や人間関係の壁に直面し、仕事に影響が出ている者もいるかもしれません。今回は、配属が思い通りではなくへこんでいる、チームに溶け込めない、電話に出ない、商談などでうまく話せないといった新人たちに焦点を当て、どう向き合うべきかを考えます。

「新人(に限らず、若手社員全般かもしれません)があいさつをしない」という声をよく聞きます。しかし新人研修では、「あいさつ」の重要性を強調し、実際に練習も行います。元気にあいさつができるようになってから配属されたはずの新人が、なぜ職場ではあいさつをしなくなってしまうのか? どうしたら再びあいさつをするようになるのか? 今回は、ある企業の製造現場での実例を紹介します。
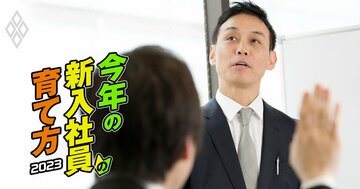
新人に業務を教えるために、上司や先輩が、具体的に仕事の一部をやってみせて、その後新人に同じようにやらせる、という方法を取っている会社は多いと思います。ようやく任せられるくらいにまで育ったと思ったら、その新人が「この会社を辞めようと思っています」と相談してくる……そんな悲劇は避けたいもの。今回は、新人に業務を教え、育成していく上で、「やらされ感」をなくし、能動的に関わっていく人になってもらうためにはどんな点に注意したら良いかをお伝えします。

新入社員が入社して、約半年。9月、10月は新人のフォローアップ研修のシーズンでもあります。少しずつ周囲が見えてきて、仕事に対する不満や不公平感などを抱えている新人もいると思いますが、「ポジティブシンキングが大切!」などと言われがちな昨今、ネガティブな感情を口にすることがはばかられるような環境の会社も多いのではないでしょうか。しかし、ネガティブな感情こそ、若手にとっては成長の機会なのです。不満を成長に変えるために、周囲はどう接したらよいのでしょうか?
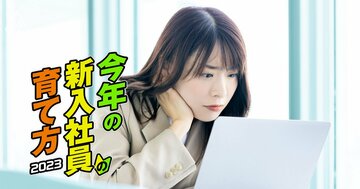
新入社員が入社してから約半年、これまでの振り返りのために、9月にフォローアップ研修を開催する企業も多いと思います。入社して半年というのは一つの目安。順調に育ってきている新人もいれば、現場の仕事を回せるようになるまでにはまだまだ時間がかかる、という人もいるでしょう。成長の速度は人それぞれ、期待より遅くても、上司や先輩がやる気をつむような言動は避けなくてはいけません。前向きに頑張ろうとしている新人に対してモチベーションを一気に下げる一言とはどんな言葉なのか、新人のタイプ別に解説します。

新入社員が入社して4カ月。ある程度職場や仕事に慣れて夏休みを取った後のタイミングは、新人が退職を申し出ることが多い時期です。「会社を辞めたい」と思う新人は何に悩んでいるのか。人事担当や現場の先輩・上司が気を付けるべきことはなにか、分かりやすく3つの実例で解説します。
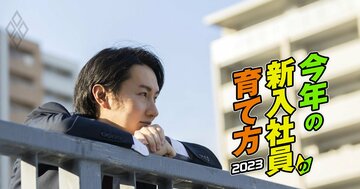
新入社員の配属のタイミングは各社の方針や職種によっても変わってきていますが、最近では人手不足という事情もあり、早めに現場配属になっている企業が多いようです。新人たちはそろそろ仕事にも慣れ、先輩の指導のもと、少しずつ仕事らしい仕事をさせてもらっている時期かもしれません。やるべき仕事がうまくいかなかったとき、新人に「なぜ、できないのかを考えて」とか、「なんで失敗したのか、振り返ってみて」などと声掛けしていませんか? しかし、新人に対して「なぜ?」と聞いても、いい結果にはなりません。新人の育成時に「なぜ」が効果的でない理由とは? 社内講師・社外講師として30年以上新人を見てきた筆者が解説します。

4月に入社した新入社員がそろそろ配属される時期です。新卒研修が終わったときにはやる気があった社員が、配属された職場で先輩や上司と一緒に働くようになったら、モチベーションが下がってしまう……という事態は、残念ながら珍しくありません。新入社員のモチベーションを下げてしまう、残念な上司・先輩の特徴とは?社内講師・社外講師として30年以上新人を見てきた筆者が解説します。

2023年度が始まりました。新人が職場に配属される、部下や後輩として付き合う、育てる、という立場の読者の方も多いと思います。今年の新人は、学生時代のラスト3年間をコロナ禍で不自由な思いをしながら過ごし、就職活動をしてきた世代。そんな社会背景もあって、特徴的な3つの力を備えています。戦力として成長してもらい、活躍してもらうためにはどのように付き合っていけば良いか、社内講師・社外講師として30年以上新人を見てきた筆者が、そのヒントをお伝えします。

テレワークが当たり前になった一方で、出社比率を上げる企業も増えてきました。これからはオンラインとオフライン、両方のメリットを組み合わせて人材育成計画を立てていく必要があります。早くからテレワークを導入している外資系企業のノウハウを踏まえ、後編では、オンライン・リアル研修両方の良さを生かしながら人材育成計画を立てるポイントや、オンライン研修で効果を上げるために知っておきたいコツをお伝えします。

「テレワークにもすっかり慣れたけれど、新人・若手社員の教育だけはどうしたものか……」という企業は多いのでは。外資系企業の事例を中心に、実際に効果を上げている新人・若手育成の秘訣(ひけつ)を2回に分けてお伝えします。前編は、新人を受け入れる育成担当側が知っておきたいことと心構え、そして、効果が出ている企業が、日々の業務に取り入れている育成コミュニケーションの実例を紹介します。

新人が入社した後、配属前まで行う研修。ここ数年はリアルで開催しにくく、しかしオンラインではなかなか成果が上がらないとお悩みの企業も多いのではないでしょうか。また、配属された後の受け入れ側も、新人たちが「あいさつ」「返事」もできないのでは、OJT(On the Job Training 実務を通した指導訓練)どころではないでしょう。今回は、入社したばかりの新人の育成・指導のポイント、入社2年目、3年目の若手社員への指導にも活用できるヒントを他社事例から解説します。

新年度が始まりました。異動や転職など、人の動きが活発になるこの時期、新しい人間関係を構築する機会も多いことでしょう。ビジネスの広がりやより満足度の高いキャリアのためにも、新しい縁やビジネスチャンスをつかみたいもの。今回の記事は、2022年度に仕事で大きな成果を出すために必要なポイントを三つお伝えします。

たとえ仕事の能力が変わらなくても、「一緒に仕事をしたくない人」「チームの士気を下げる困った人」の評価は、能力以下に下がってしまうものです。そういう“困った人”の特徴を3つのタイプで紹介します。自分がそうなっていないか、あるいはチームにそういう人がいる場合、どのように接するべきかのヒントにしていただければと思います。
