金山隆一
#3
トランプ米政権の相互関税を巡り、米アラスカ州のLNG(液化天然ガス)輸出事業が日米間の交渉カードに浮上してきた。ベッセント米財務長官が4月8日、日本との協議にあたり同事業を重視する姿勢を示した。ただ、同事業は7兆円近い巨額投資が必要になるとみられ、日本にとっては中東から輸入するLNGよりも割高になる可能性がある。同事業を巡る、日本のガス業界やプラント業界などが抱える懸念を明らかにするとともに、米国からのLNGの購入圧力の回避策を模索する。

トヨタ自動車グループの総合商社、豊田通商が全米最大級の自動車リサイクル企業を9億700万ドル(約1344億円)で買収する。トランプ米政権は鉄鋼とアルミに25%の関税を課し、4月にも自動車への関税率もアップすると表明しているが、これをバネに、トヨタのEV(電気自動車)シフトにも対応できる体制をいまから準備していく。ただ、買収する企業の市場の評価はPBR(株価純資産倍率)でわずか0.6倍。これに2倍のプレミアムを付けた価格で全株を買い取る。高値づかみではないのか。大手商社といえば世界で最も有名な投資家バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイが大手5商社の株を買い増していることが明らかになり、日本株全体の再評価につながったが、豊田通商は業績では6番目でバフェットには買われていない。トランプ大統領の懐に切り込む大型投資は吉と出るか、凶と出るか。

#16
脱炭素と中国の過剰投資で成長の未来が描けない化学事業。しかしレゾナック・ホールディングスからパーシャルスピンオフ(部分分離)という手法で独立を目指す化学会社クラサスケミカルは九州唯一の大分コンビナートを運営し、アジア大陸に近い立地と独自の川下誘導品を武器に2年後のIPO(新規株式公開)を目指している。内需の縮小でエチレンセンターの統廃合が進む国内の石油化学業界だが、大分の石油化学事業だけで100億円近い営業利益を稼ぎ出すクラサスはいまのところ単独での成長戦略を描く。成長の源泉は何か。今年1月1日に分社化したクラサスケミカルの福田浩嗣社長を直撃した。
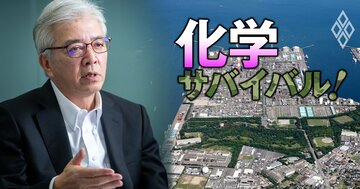
トランプ米大統領の登場で、化石燃料復活と高関税時代到来というチャンスとリスクを抱える資源貿易商社、三井物産の役員人事が発表された。つぶさに見ると「次期社長候補」として、ある人物が浮かび上がる。2年後に任期を終える堀健一社長の後任候補を探った。

#15
中国の化学品の過剰生産による市況低迷で低稼働率にあえぐ化学メーカーは、大胆な事業構造改革や伝統的な化学品事業からの撤退、半導体材料事業への経営資源シフト、脱炭素が必須のコンビナートのエチレン製造設備停止などに動いている。課題が山積する中で、問われているのが各社のリーダーの手腕だ。では、各社はどんなトップを起用してこの難局を乗り越えようとしているのか。主な化学メーカーのトップ人事の行方を占う。

トランプ米大統領の登場で、化石燃料復活と高関税時代到来というチャンスとリスクを抱える資源貿易商社、三井物産の役員人事が発表された。つぶさに見ると「次期社長候補」として、ある人物が浮かび上がる。2年後に任期を終える堀健一社長の後任候補を探った。

#10
信越化学工業が中国による化学品の過剰生産や脱炭素対策にあえぐ化学大手を横目に快進撃を続けている。塩化ビニール樹脂(塩ビ)と半導体材料の二大収益源を育て、信越化学を世界トップクラスの化学会社に押し上げた中興の祖、金川千尋会長が2023年に96歳で死去したものの、16年から社長を務める斉藤恭彦氏はこの8年で株価を3.5倍、連結純利益を3倍強に押し上げた。さらに、足元では半導体製造装置企業の買収や、中国への投資、56年ぶりの国内工場の新設といった金川時代にはなかった戦略を打ち出し、「信越2.0」のフェーズに入ったようにも見える。斉藤社長が率いる信越化学の今後の成長の可能性を探った。

#7
日本の製造業の基盤である石油化学コンビナートが大きな岐路に立たされている。エチレンプラント(ナフサ分解炉)から排出される二酸化炭素(CO2)の削減と中国の化学品の過剰生産の影響で低迷が続く稼働率の向上のために、国内に12あるエチレンセンターの能力削減が始まっているのだ。国内大手が合従連衡に動いているが、再編がさらに加速する可能性もある。日本のコンビナート再編の先行きを大胆に予想。生産を停止する可能性のあるコンビナートを挙げるとともに、大手首脳への取材を基にしたコンビナート再編の最終形も示す。

#6
2024年3月期に過去最大の最終赤字に沈んだ住友化学が事業構造改革を加速させている。サウジアラビアの大型石油化学事業「ペトロ・ラービグ」や医薬品事業の拡大を目指す、故米倉弘昌元社長の路線を修正し、事業の中心を農薬と半導体材料にシフトする。さらに、ラービグの再建策や医薬品子会社、住友ファーマの切り離し方針など大胆なリストラも相次ぎ打ち出している。ラービグのリストラの舞台裏を明かすほか、次なるリストラ候補も予想する。巨額赤字からのV字回復を目指す住友化学の次の一手とは。

#5
2024年3月期に過去最大の最終赤字に陥った住友化学が構造改革を加速させている。巨額赤字の要因となった石油化学と医薬品に代わり、祖業の農薬と半導体材料を事業の中核に据える。8月には経営の足かせとなってきたサウジアラビアの石油化学事業ペトロ・ラービグへの出資比率の引き下げを決めるなど大胆なリストラにも踏み切った。岩田圭一社長が、今後同社がどのように稼いでいくか、各事業が持つ強みを挙げながら明かす。一方、切り離しを検討している傘下の住友ファーマの行く末や、石油化学事業の再編についても語った。

伊藤忠商事が、成長投資に巨額の資金を投下し始めた。セブン&アイ・ホールディングスの創業家による買収(MBO)に伊藤忠が出資する方針が明らかになっているが、これに先行してデサントの完全子会社化に向けた追加TOB(株式公開買い付け)に1800億円、ブラジルの鉄鉱石権益の買い増しに1200億円、測量大手パスコを持ち分法適用会社にするために77億円のTOB、川崎重工業子会社のカワサキモータース20%資本参加に800億円――4件で約4000億円の投資を決めた。セブンのMBOはファミリーマートを子会社に持つ伊藤忠の資本参加が独占禁止法に抵触する可能性も指摘されているが、これが成立しなくとも2年後の連結純利益1兆円に向け、大手商社トップ奪還が射程に入っているようだ。
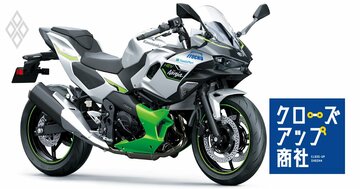
#6
BtoB(法人間取引)の原料供給が主流だった伊藤忠商事の食料カンパニーが、同社傘下のファミリーマートとの連携で新ブランドを作り、BtoC(消費者向け事業)に乗り出そうとしている。伊藤忠はこれを、連結純利益で1兆円カンパニーを目指すキーワード「利は川下にあり」の代表例にしようとしている。三菱商事、三井物産を超えるための、伊藤忠の秘策に迫る。

#3
変動が激しい再生可能エネルギーの有効活用策として蓄電池が脚光を浴びている。政府の補助金もあり、電力・ガス、石油元売り、情報通信、鉄道、不動産、商社、金融リース、新電力などの企業が日本各地で大型蓄電所の開発に乗り出した。伊藤忠商事も大型蓄電所や太陽光発電、秋田県沖での大型洋上風力発電を計画。パートナーはJERA、大阪ガス、関西電力、カネカ、東急不動産、東京都、グーグルと多岐にわたる。彼らは伊藤忠の何に期待しているのか。実は伊藤忠は1990年代から蓄電池の可能性を見越して事業を広げてきた。安部泰宏電力・環境ソリューション部門長に課題とリスクを聞いた。

#2
伊藤忠商事が買収した、旧ビッグモーター(現WECARS)の不正の根の深さが次々と明らかになっている。保険金の不正請求では約6万件超の水増しの疑いが発覚。事故車を修理歴がないと偽って販売していた問題も表面化した。こうした不祥事の再発リスクを抱えてでも、中古車ビジネスに挑戦する伊藤忠の狙いは何か。EV(電気自動車)時代を見据え、中古車ビジネスとエネルギー事業を掛け合わせる伊藤忠、WECARSの秘策に迫った。

三菱ケミカルグループ、住友化学、三井化学の財閥系大手化学3社の2024年3月期決算が出そろった。三菱ケミカル、住友化学は、ともに25年3月期の業績改善の見通しを発表したものの株価は下落、3社のなかで売り上げ規模が最も小さい三井化学だけが5月15日の決算会見当日に年初来高値を更新し、明暗が分かれた。株式市場は三井化学の何を評価し、住友化学と三菱ケミカルの何を評価しなかったのか。

住友化学が創業以来の危機を迎えている。2024年3月期に医薬品子会社とサウジアラビアの石油化学事業で巨額の減損損失を計上し、過去最大の3100億円の赤字に陥る見通し。4月30日に開かれた事業戦略説明会で、岩田圭一社長が国内外で約4000人の人員削減などのリストラ策を公表したが、市場は厳しい評価を変えていない。最高値から3分の1に落ち込んだ株価を反転させるきっかけはあるのか。

EV(電気自動車)や再生可能エネルギーの普及で需要の急拡大が見込まれる銅で、総額約44億ドル(6600億円)の大型鉱山拡張プロジェクトがチリで動き出す。銅市況は4月8日に9400ドル台と2023年1月以来の高値を付けた。非鉄商社の顔も持つ丸紅がチリに投じるリスクマネーは約800億円。同社がこの2年で投じた成長投資7400億円の約1割に過ぎないが、日本の消費量の1割に相当する高品位の銅が日本にもたらされる。なぜこの規模の投資で巨大な資源開発が可能になるのか。成功すれば脱炭素時代に日本が進める資源開発のひな型となるかもしれない。

保険金水増し請求の不正で問題になった中古車販売大手ビッグモーターの買収に伊藤忠商事が乗り出した。伊藤忠はグループでレンタカーや高級外車のヤナセなど自動車関連ビジネスを展開してきたため、この分野の延長戦にあるとみえるが、実は、主導しているのは住生活とエネルギー・化学品の社内カンパニーだ。伊藤忠がこれまでに打ってきた布石をつぶさに分析するとビッグモーター買収に隠された野望が見えてくる。買収金額の独自試算とともに、見えてきた3つの戦略を探った。

#11
住友化学が創業以来最大となる赤字に陥り、苦境に立たされている。株式市場が石油化学業界全体が抱える構造問題を解決する再編や、成長著しい半導体や蓄電池の部材供給といった成長事業への大胆なシフトを求める中、ヘッジファンドは赤字出血を止める事業の売却を巡りしたたかな計算をしている。

三井物産がパルプ世界最大手で森林メジャーともいわれるブラジル企業と提携し、パルプから出る残渣(ざんさ)物や植林資源を使い、バイオ燃料やバイオ化学品を生産する脱炭素ビジネスに乗り出す。同社がこれまで挑戦しては撤退を繰り返してきた植物由来のバイオ化学品事業と、どこが違うのか。担当者を直撃した。
