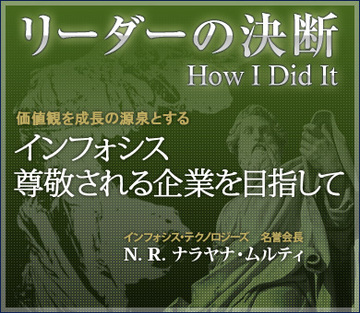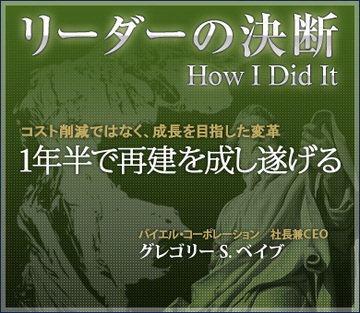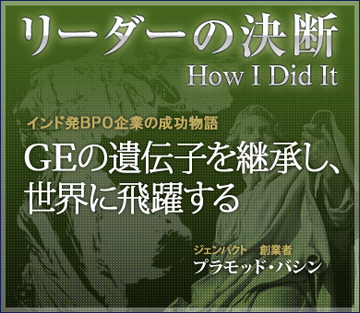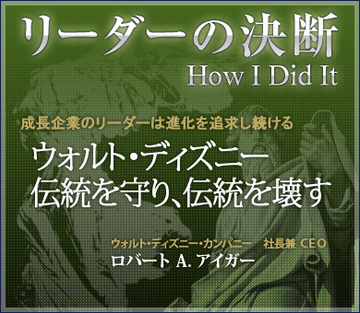2004年、グーグルが上場予定であることを発表すると、メディアのほとんどは、上場すれば会社は変貌し、グーグルらしさを失うと報道した。自社株の持ち分によって、「持つ者」と「持たざる者」とが仲間割れし、才能ある人材は株を売却してグーグルを辞めるだろうとも予想した。また、上場企業らしい体裁を整えれば、切れ味が鈍るだろうという批判が大半だった。だが、グーグルは変わらなかった。基本的に当時と同じ経営陣が、非上場企業だった頃と同じ価値観に基づいて、グーグルを経営している。
同社CEOのエリック・シュミットによれば、自分たちの価値観を貫くことができた理由の1つは、慣例にとらわれない上場手法を選んだことにあるという。同社はより透明でオープンな手法を求めた。大手機関投資家だけではなく、グーグル・ユーザーにもIPO(新規株式公開)への参加機会を与えたかったのだ。その結果、ダッチ・オークション方式のIPOの仕組みを構築し、それを決行した。本稿では、その一部始終を振り返る。
「グーグルらしい」IPOを目指して
もう6年前になるが、上場までの道のりは、いまも逐一覚えている。それは、いかにも「グーグルらしい」体験で、今日に至るグーグルの本質を如実に示した出来事だった。
Eric Schmidt
グーグル会長兼CEO。パロアルト研究所、ベル研究所、ザイログ等を経て、サン・マイクロシステムズに入社。Java の開発とインターネット戦略の立案を導き、後に最高技術責任者と執行役員を歴任。1997年からはノベルのCEOを務める。2001年3月にグーグルの会長に就任し、同年8月からCEOを兼任。以来、創業者のラリー・ペイジ、セルゲイ・ブリンらと共に、グーグルの経営を指揮している。
IPO(新規株式公開)は会社を変貌させる。メディアの多くは、上場すれば我々がグーグルらしさを失うと信じ込んでいるようだった。ニューズ・レター『サーチ・エンジン・ウォッチ』の編集者で、業界では有名なコメンテーターのダニー・サリバンは、「上場はグーグルにとって最悪の出来事の1つになるだろう」とコメントした。
自社株の持ち分によって、「持つ者」と「持たざる者」とがいきなり仲間割れすると世間は予想した。才能ある人材は株を売却してグーグルを辞めるだろう。そして、ウォール街を喜ばせることに目が向いて、グーグルの誇る客観性と独立性が失われるだろう。また、上場企業らしい体裁を整えれば、切れ味が鈍るだろう。
つまるところ、人々は、グーグルが前途洋々の若手ベンチャー企業から成熟した上場企業へと転換することで、グーグルを革新的企業にした「変わり者」の精神が失われると危惧したのである。
しかし、そうはならなかった。私は、かつてといまとでグーグルの本質に何の変わりもない──規模がかなり拡大しただけ──と心から信じている。1つの出来事に着目しすぎるのもよくないが、自分たちの価値観を貫くことができた理由の1つは、慣例にとらわれない上場手法を選んだことにある。
グーグルの創業者、ラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンは、IPOの目論見書に掲載した「創業者からの手紙」の冒頭で、「グーグルは慣例にとらわれない企業であり、今後もそのような企業になるつもりはありません」と綴っている。そして、彼らは未来の株主に向けて、グーグルはホームランにも大失敗にもなりうるようなリスクの高いプロジェクトに投資する可能性があると警告した。