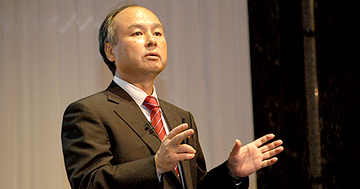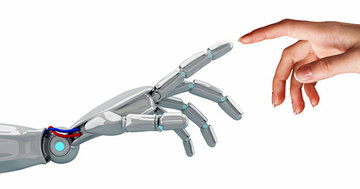東大発のベンチャーが作ったロボットが
予選では圧倒的に強かった
この大会の標準機は、前述したとおり、ボストン・ダイナミクス社の人型ロボット、「Atlas」です。これは、「Petman」と、当時別に開発されていた「Atlas」の二つを原型としたものです。
この大会用「Atlas」は、二足歩行のヒューマノイドで、油圧式アクチュエーターを持っています。一番の特徴はそのタフさです。これまで二足歩行のヒューマノイドというと、現場の感覚としては「確実に動く」という感じはありませんでしたが、「Petman」には信頼性が感じられました。そのため、大会標準機の原型に選ばれたのだと思います。
ロボティクスチャレンジは、目指したゴールのレベルが高かったため、実は、その1年半くらい前にトライアルという予選が開かれました。本選に類似した内容で、2013年12月に行われました。前述しましたが、予選では東京大学発のベンチャー「SCHAFT」(シャフト)が開発したロボットS―Oneが圧倒的な強さをみせました。「東大」として出場できなかったのは、DARPAを主催しているのが米国防総省だからです。
前回述べたように、軍事につながる研究を大学の名前ですることはできません。また、国内での資金調達も思うように進まず、資金難に陥っていたところ、そこに手を差し伸べたのがGoogleでした。けれど、SCHAFTは、予選でトップとなりつつも、結局、本戦には出場しませんでした。
SCHAFTが開発した技術とは?
SCHAFTのコア技術の一つは、「ウラタ・レッグ」と呼ばれる「蹴っても倒れない」技術でした。仕組みを簡単に言えば、モーターと冷却装置との組み合わせで、最大限に性能を生かせるようになった歩行の制御技術の一つです。
通常、モーターに大きな電流を流すと、一気に熱くなるため絶縁体が破壊され、ショートします。それを回避するために、冷却装置をうまく組み合わせ、モーターが熱くならないようにするのです。これまで培われてきた要素部品の技術に関して、独自のやり方で組み込んだのが「ウラタ・レッグ」でした。この方法でモーターの性能を今まで以上に引き出すことができるようになりました。
SCHAFTが出場しなかった2015年の本戦で、1位となったのは韓国チームのKAIST(カイスト)でした。日本でいう産業技術総合研究所にあたる国の研究機関です。アジアの中では、韓国、中国、台湾もロボットに力を入れています。
余談ですが、DARPAはこれまでも様々なプロジェクトを行っており、その中でも現在のロボティクスの発展に大きく貢献しているのが、自動運転プロジェクトである「DARPA グランドチャレンジ」(2004、2005)と「DARPA アーバンチャレンジ」(2007)です。アメリカの砂漠を自動運転するところから始まり、3回目となるアーバンチャレンジでは、市街地を想定したコースが使用されました。
2007年当時、自動運転はそれほど注目を浴びていませんでしたが、10年を経過した現在の盛り上がりを考えると、DARPAが仕掛けたプロジェクトの影響力を強く感じることができます。
例えば、2005年のグランドチャレンジで優勝したスタンフォード大学のチームリーダーSebastian Thrunが、Googleの自動運転車を開発をしたのです。
そういった意味において、被災施設というタフな環境で使用するロボットの開発・研究を目指して行われたロボティクスチャレンジの成果は、もしかすると数年後に、はっきりと見えてくるかもしれません。
日本ロボット学会理事、和歌山大学システム工学部システム工学科教授。1973年生まれ。東北大学大学院情報科学研究科応用情報科学専攻修了。2007年より千葉工業大学工学部未来ロボティクス学科准教授(2013-14年、カリフォルニア大学バークレー校 客員研究員)を経て現職。専門は知能機械学・機械システム(ロボティクス、メカトロニクス)、知能ロボティクス(知能ロボット、応用情報技術論)。2016年、スイスで第1回が行われた義手、義足などを使ったオリンピックである「サイバスロン2016」に「パワード車いす部門(Powered wheelchair)」で出場、世界4位。電気学会より第73回電気学術振興賞進歩賞(2017年)、在日ドイツ商工会議所よりGerman Innovation Award - Gottfried Wagener Prize(2017年)共著に『はじめてのメカトロニクス実践設計』(講談社)がある。