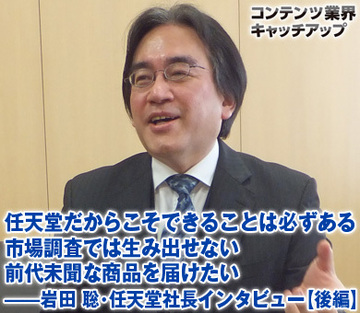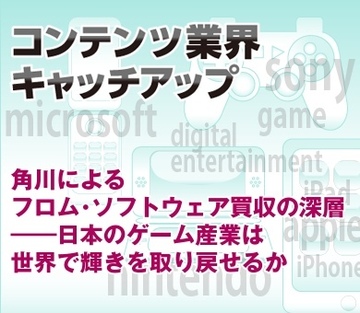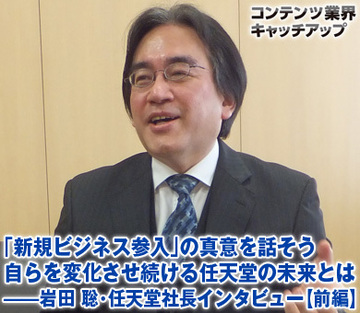ゲームコンテンツ関連企業の2012年3月第三四半期連結決算が出揃った。この決算状況からは、ソフトメーカー大手の”出口戦略”の強化が読み取れる。
それは、ゲームセンターなどの「業務用ゲーム」、任天堂、ソニー、マイクロソフトによる従来の「プラットフォーム型家庭用ゲーム」、ディー・エヌ・エーとグリーの2強が牽引する、いわゆる「ソーシャルゲーム(以下SNS系ゲーム)」に加えて、さらにはスマートフォン用アプリ、ブラウザゲームなどへのコンテンツ供給も軌道に乗り始めているということだ。
だが、各社の決算資料を見ると、この出口戦略を生かし切れているとは言いにくい。たとえばSNS系ゲームで利益が出ても、家庭用ゲームが不振でゲーム事業自体が不調なセガや、SNS系ゲームは低調だが家庭用ゲームは好調で、結果好決算となったコーエーテクモなど、現在は各社ともバランスを取ることに苦心している状態と言える。
その状況においてこのような出口戦略の多彩性を存分に活かし、営業利益予想を昨年比2倍増の315億円、かつ決算の上方修正という好決算を叩き出したのが、バンダイナムコホールディングスだ。石川祝男社長に、際立つ強さの秘訣を聞いた。
被災地の女児が「プリキュアなりきりスタジオ」で笑顔
コンテンツビジネスの社会的重要性を痛感
 いしかわ・しゅくお
いしかわ・しゅくお1955年山口県生まれ。関西大文学部卒。旧ナムコ(現バンダイナムコゲームス)一期生。2005年副社長を経て、2006年、ナムコとバンダイの経営統合で誕生したゲーム事業部門会社、バンダイナムコゲームス社長。2009年バンダイナムコホールディングス社長(現任)、2010年バンダイナムコゲームス社長。
石島(筆者):昨年は東日本大震災、円高、そして不況など暗いニュースを挙げたらきりがない大変な年でした。そんな状況においても、バンダイナムコHDが直近決算で、上方修正のおまけつき好業績を収めたことは、驚きを隠せません。
石川社長(以下石川):昨年は本当にいろいろなことがあった年でしたけれども、社員もよく頑張ってくれました。また、震災で被害を受けられた地域では、ご不便な生活で苦しまれておられる方もまだまだ多いと思います。
弊社も被災地に売上の一部を寄付する一方で、公益社団法人「セーブ・ザ・チルドレン」と連携し、「プラモデル教室」など、被災地のお子さんに対する具体的な支援を続けております。また今年3月末時点の株主の方から、株主優待を選択制とし、被災地への寄付も項目の1つとする予定です。被災地に少しでも早く笑顔が戻るよう、心からお祈りしています。