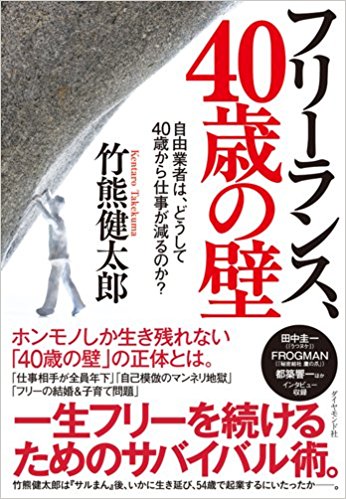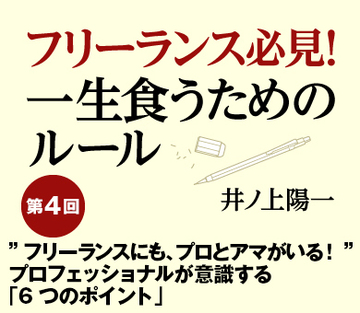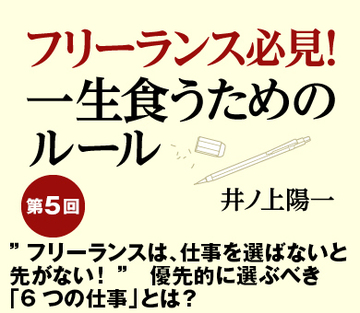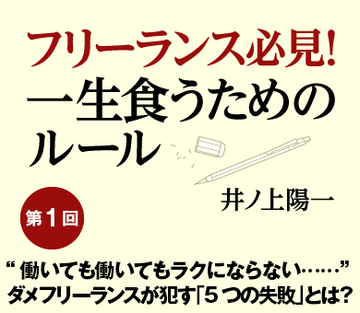自分の頭で考えないと駄目
氷川さんがフリーランスになった頃(2001年)は出版業界は陰りが差し始めたとはいえ、まだ比較的調子が良かった時期です。そこからどんどん凋落していくわけですが、その中で上手く生き残ってこられたのはなぜか、伺いました。
答えは「全方位性」。アニメに関しては、だいたい35通りくらいの切り口があると氷川さんは言います。たとえば美術・撮影・作画・特殊効果・演出など、技術だけをとっても多様な語り方がある。他人がいわないようなことまでカバーしてきたそうです。
「重力と空気って、ダイレクトに絵として描けないですよね。形がないものですから。絵に描けないことをアニメとして表現することが本質的にすごいのだ。そんなことを語ってきました。キャラクターと物語にしか触れないアニメ論評が多いと思いませんか? 仮にアニメ作品が消えて論評だけが残ったとき、それがアニメなのか小説なのか漫画なのか……何を扱った論評なのか分からなくなる文章が多い。それが古典的批評の限界です。アニメはアニメならではの表現により、成し得た地平がある。それを全く捉えきれていないと思うんです。
テーマだけで作品を語る人も多い。宮崎駿はエコロジーだから素晴らしい!とか。その場合、多くはテーマがどんな具体的な絵で表現されて、どう観る人に届いているか、プロセスを無視してしまう。だから表現論というか、アニメ固有の表現形式に着目することで、独自性を意識しています。それって実は、竹熊さんのお仕事(『マンガの読み方』)から学んだ部分も多くあるんですよ。」
ここで氷川さんの口から出た『マンガの読み方』は、1995年に宝島社から出たマンガ表現の本で、私と夏目房之介さんを中心にしたチームで書いた研究本です。チームの中心は夏目さんで、私はお手伝いをしただけですが、驚くべきことに、それまで「マンガ固有の表現」について解説した本がほとんどなかったのです。マンガは絵・言葉・コマで構成された表現ですが、「マンガの絵とは何か。一般の絵画とどこが違うのか?」「セリフが入る吹き出しにはどのような種類があるのか?」「コマの機能とは何か。コマとコマの間の空白をどう呼べばいいのか?」というような、小説でも映画でもない、マンガ固有の表現をどう考えればよいのかの研究会を発足し、2年がかりで解析した仕事でした。ここから現在のマンガ学の主流になっている「マンガ表現論」が始まったと言われていますが、何度も書きますがこれは夏目氏の功績だといえます。
「僕の運がよかったのは、「宇宙戦艦ヤマト」の現場を見て、資料をいただいた時点では、アニメ雑誌も何もなかったことです。書かれている専門用語を誰も教えてくれないから、結果、自分の頭で考えぬいて分析や解読をした。それがすべてのパワーの源です。今、若い人から「勉強になりました」とか言われると、「それより自分で考えなさい」という気持ちになります。勉強したら終わり。なぜなら他人の知識に従属してしまうから。まず自分の頭で考えないと駄目。
だってね。なんで自分はアニメを好きになったんだろう? みたいな本質的問いって、勉強だけで答えが出るわけがないでしょ? そこは自分の頭で徹底的に考える、一生涯かけて考えぬく覚悟とプロセスに意味があるんです。」
プラスαを乗せ続けること
氷川さんは今、明治大学大学院で客員教授(2018年4月より特任教授)として教鞭をとられています。講義は前期・後期に分かれ、前期はTVアニメを中心とする50年史。単に作家の歴史とかプロダクションの歴史ではなく、時代背景から含めた「アニメビジネス通史」と銘打っている講義です。
『鉄腕アトム』は1963年放映開始ですが、それ以前に週刊誌文化の形成があり、同時に東京オリンピックの前年という前後関係で位置づけると、戦後という時代の中でアニメ文化がどんな時代背景で誕生してきたかが、色々クリアになるそうです。どんなものにも時代の要請があり、TVの普及という背景があったからこそ「アトム」が成立したと思う、と氷川さんは言います。
「アトム放送開始当時の日本は加工貿易で高度成長期でした。当時、僕は(東京の)東中野在住でしたが、砂利道が急速にツルツルに舗道化されていく変化を目撃しています。そういう時代だからこそ、ツルツルの質感をアピールしたテレビアニメが人気になった。時代に求められて生まれた文化だったと思うのです。」
氷川さんは、1960年代には、お菓子と薬品のメーカーがアニメのスポンサーをやっていたことが重要だと言います。それもナショナルクライアントがスポンサーをやっている。お菓子以外にはケミカル、化学系のメーカーが多いと。これは日本の化学が先の戦争の頃から強かったということと、核家族化しつつある中で子どもの健康がとても重視されていたことの証左だと思う、と言いました。これが1970年代には玩具メーカーがスポンサーになるのです。
1970年代になると、子どもは健康ではなく玩具を欲するようになるわけです。日本全体で生活に余裕が出てきたので。更に進んで1980年代になるとOVA(オリジナル・ビデオ・アニメ)が出てきます。つまり「作品」そのものを売るようになるのです。化学メーカーがスポンサーしている頃は、子どもの健康を売るという第一次産業。1970年代はアニメを通じて玩具を売るので第二次産業、1980年代はアニメそのものを売るので第三次産業化といえるのではないか。というのが、氷川さんの説です。
「後期はアニメ表現がテーマです。技法への着目方法や、メイキングの知識基礎を教えています。日本のアニメ表現のどこが独特か、アナログとデジタルでどう変わったのか、おぼろげにしか語られていない部分を、逐一明らかにする講義にしたい。あまり興味関心を持たれていない領域ですが、伝えると、皆「なるほど!」と言ってくれる。やはり「仕事それ自体をつくる」のが最強だと思います。誰も気付かないところに需要があることを、開拓する姿勢です。」
誰もが気がついていないが、実は欲している「隠れた需要」を掘り起こすことはビジネスの要諦です。これは単にリサーチしただけとか、情報を集めただけでは見つからない、と氷川さんは言います。
「著作権法での著作物の定義とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」です。つまり世の中にある情報をただ集めてアッセンブルしただけでは、とても著作物とは呼べないでしょう。「思想又は感情」を極力排した「情報」を届ける「作業」だけでは著作権法で保護されない可能性だってありますし、長期的な価値も乏しくなると思うんです。独自の着眼点で整理や伝達の方法に先進性があれば、著作性も生まれるし、そこに「対価」と「注目」が集まるはずです。
これは僕が会社で働いている頃の経験ですが、「知財」のアウトソースをする際は、発注側が著作権を持ち、すべて具体的に「こういうものを作ってください」と仕様書で指示するのです。その仕様に従属して具体的に実現する「作業」が下請けの仕事。そうではなく、執筆するとき、著作物をつくる意識をもちつつ、「ライター」と呼ばれる以上の、何か創造的な仕事を付加したいと思っています。誌面構成ごとページをつくりたいという意識も、そのひとつですね」
これは私もよくわかります。特に駆け出し時代はコストパフォーマンスというか「加減」がよくわからないので、発注主が要求した以上の仕事を「やってしまう」傾向が私にもありました。プロとして実は褒められることではないのですが、見開き2ページの仕事に1週間もかけてしまったことがあります。取材・文章だけではなく、レイアウトのラフも切りましたし、図版も自分で集めてきました。氷川さんも全く同様だったようです。駆け出し時代は小さい版元や、創刊されたばかりの雑誌の仕事が多かったので、予算が少なく、レイアウトまでできるライターは重宝されたのです。
「仕事を頼んだ人が期待していることと、期待していないことってあると思うんですよ。僕は期待していない部分までやるようにしてみたい。それが付加価値になる。つまり「氷川に仕事を頼んでよかった」と思わせるポイントではないかと思うんです。その分の責任も持ちたいから、取材原稿でもなるべく署名してもらうようにお願いをしているんです。
やはりフリーランスは仕事、その内実が名刺代わりだと思います。仕事で提案して付加価値を生んでいく。それが次の仕事を呼んでくれる。今やインターネットがあるから、付加価値を生まない記事は誰でも書けるんです。常に自分の頭で考えて新しい価値を加えること。それを意識して仕事しています。」
60歳からでもアニメは創れる!
以前、氷川さんからアニメを作ってみたいというお考えを聞いたことがあります。PCが発達して、今や個人でも比較的容易にアニメが作れるようになっています。それは今でも変わっていないのでしょうか。
「もちろん、今でも変わっていないです。僕らの世代って、そろそろ還暦が間近です(注:2018年2月に60歳となりました)。1980年代はセルや8mmフィルムをどう扱うか、物理的制約が大きな壁としてありました。一度はあきらめたが、今なら作れる。そういう気持ちが、ものすごく強くあるんです。今やシニアの人が定年を迎え、子どもももう手が掛からないとなれば、かなりレベルの高いアニメを作れるんじゃないかと(笑)。60歳からのアニメ作り、です。2020年代には僕らアニメ第一世代が還暦を超える。専門学校は早くシニア向けコースを作るべきだとさえ思います。
もっとカジュアルに皆がアニメを作れればいいとも思うんです。意気込んで「作品」を作るというより。昔の短歌みたいな日常感覚の中から、もしかしたらすごい才能が生まれるかもしれない。かもしれない、って留保をつけているのは、新海誠監督が出てきたとき、これからの世代は皆、新海誠みたいな活躍の仕方をすると思ったら、全然そんなことはなかったから(笑)。」
2001年に新海誠さんたった一人で『ほしのこえ』を作ってヒットしたときには、後続が続々と出てくると思いました。しかし、それから数年間は新海さんだけでした。ちょっと作品レベルが高すぎました。
「だから、もっともっと日常感覚で、誰もがカジュアルにアニメを作れればいいと思うんです。インターネットは年齢も国境も超越するわけだから。
昔、大友克洋さんがアニメを始めるとき、「どうやって描くの?」と尋ねたらしい。ディズニーの有名な本を渡された大友さんは、その本をパラパラみながら、さっと描けたそうです。でも、これを教えてくれたアニメーターは、「アニメが好きな人は、それだけですでにアニメを描けるだけの観察力がある」という話として語ってくれた。こんなに勇気づけられることはなかったです。
だから、アニメを見て育った世代はアニメを描く素地はある。これは確信です(笑)。今はすぐ「このアニメは作画がダメ」とか言いますが、僕たちは金田伊功さんのすごい作画を見れば、すぐ自分でも描きたくなったのです。その受け手の多くがクリエイターになった。送り手・受け手が分離していないのもアニメ本来の姿だから、それを取りもどしたい。こうした認識が、老後一人ぼっちになりかねない方々への一つの救済になれば、なおいいですよね。」
(了)
※取材は2015年5月に実施されたものです