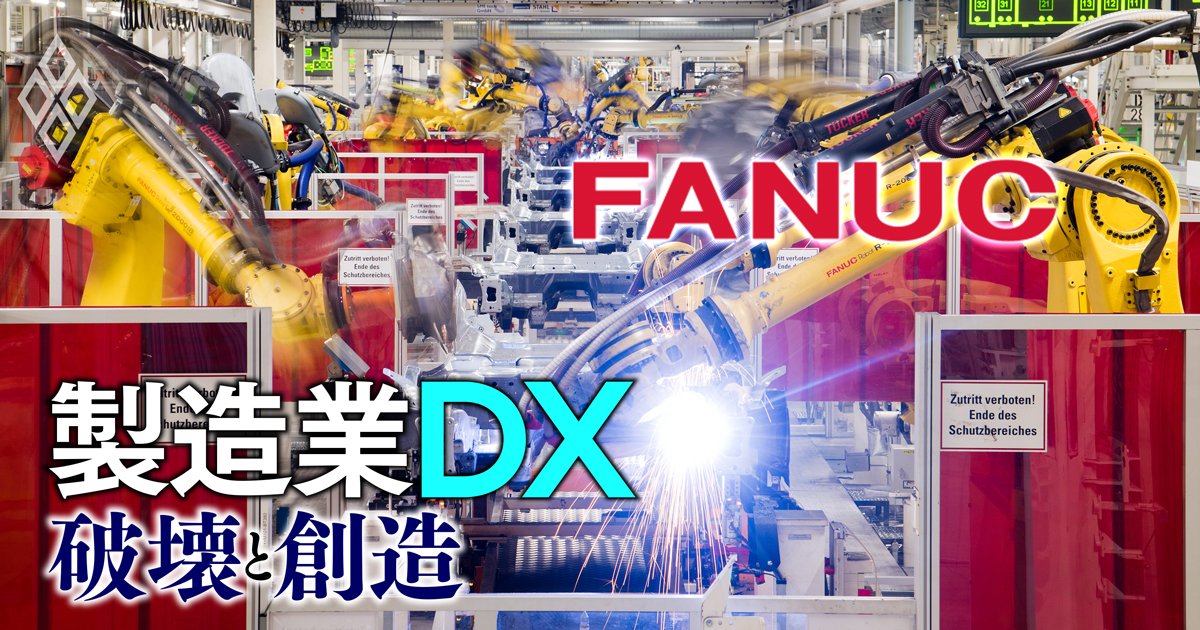まずは、世代別に月給(大学・大学院卒)を5年前と比べたものだ。ほぼ全ての世代でアップしているにもかかわらず(60~64歳を除く)、「35~39歳」と「40~44歳」では減っている。
とりわけ、「40~44歳」の月給が5年前のバブル世代と比べて、2万3300円も低いという結果には驚くしかない。
次に、物価変動を考慮した実質賃金を見てみよう。「40~44歳」の平均月給(大学・大学院卒)は45万円前後だが、10年前と比べて5万円以上も低くなっている。
アラフォーになっても満足に賃金が上がらない世代。それが大卒の就職氷河期世代なのだ。
時計の針を巻き戻すこと18年前。2000年に新卒社員として入社した人たちは、12年続いた氷河期の中でも最も厳しい就職難に見舞われた。
大卒の有効求人倍率(求職者数に対する求人数の構成比。1を切ると仕事を探している人の方が多い)は0.99倍。バブル末期の1991年2.86倍や最近の18年1.78倍と比べても、当時の厳冬ぶりが分かろうというものだ。
大卒の就職率は実に55.8%。大学まで進学しながら、半分近い学生が職にあぶれた事実は、後に日本社会の「ひずみ」となって表れることになる。
何を隠そう、記者自身が2000年入社組である。中堅の私立大学文系レベルでは、女子大生の就職は困難を極めていた。当時は気付かなかったが、振り返れば就職戦線は明らかに異様だった。
「リクナビとはがきを合わせて200社にエントリーした。目を瞑ってエントリーシートを記入できるレベル」
「(本社から子会社・下請けへと)受験する企業の名前がどんどん長くなっていく」
「50戦37敗。戦績を自虐的になぞるようになる」
「名前も知らない企業に就職するくらいなら、地元へ戻ってきなさいと親に諭された」──。
これらは、同期の間でよく交わされた会話の中身だ。もっとも、互いの戦況については根掘り葉掘り聞けない雰囲気もあった。結局、地元へ戻って就職した同期が多かったと記憶している。
ポスト、規模
勤続年数の三重苦が襲う氷河期世代
男子学生の進路は、大まかには2パターンに分かれていた。
一つ目のパターンは、離職率が高い企業の“使い捨て要員”。保険や住宅設備の営業職、外食チェーンなどのサービス業、そして、システムエンジニアである。いずれも知名度の高さの割には賃金が低い。はたから見ていて、企業の中核人材としてではなく使い捨てされやすい“体力人材”として採用されたのだと察しがついた。
不景気から採用を抑制する企業がほとんどだというのに、大量採用を続けている企業の真意について、学生も考えるべきだったのかもしれない。入社から1、2年で転職した同期も少なくなかった。
二つ目は、資格の取得や大学院進学へ走った人たちで、就職戦争への参戦を諦めたパターンだ。実質的には就職浪人の道を選んだようなもので、ここから非正規へ流れた連中もいた。
日本に新卒一括採用が根強く残っている限り、正社員になること=非正規・ニート(無業者)に転落しないことが中流を死守するための「初めの一歩」である。
しかし、現実的には、「氷河期世代はアンダークラスの主力部隊になってしまった」と橋本健二・早稲田大学教授は言う。
いちるの望みがあるとすれば、4月からスタートする有期雇用の無期転換ルールである。有期雇用を1人正社員にするたびに、助成金60万円が支給されることから、正社員化が急加速している。
とはいえ、「企業が非正規の正社員化を進めるときに、心理的な壁になるのが“35歳ライン”になっている」と橋本教授は指摘する。つまり、アラフォーの氷河期世代を、やすやすと正社員として登用することは考えにくい。
そして、氷河期世代にとって最大の理不尽は、「無事に正社員になれても不遇なこと」にある。三つの理由から、賃金が上がらない。
第一に、同じ組織には氷河期世代のすぐ上に、決まって大量採用されたバブル世代が居座り、昇格・昇進が遅れる。第二に、他の世代に比べて規模の小さな企業に就職している。第三に、会社・職種に不満がある氷河期世代は転職を繰り返し、年功賃金が残る日本企業では賃金が上がりにくい。