総世帯数における「標準世帯」の割合
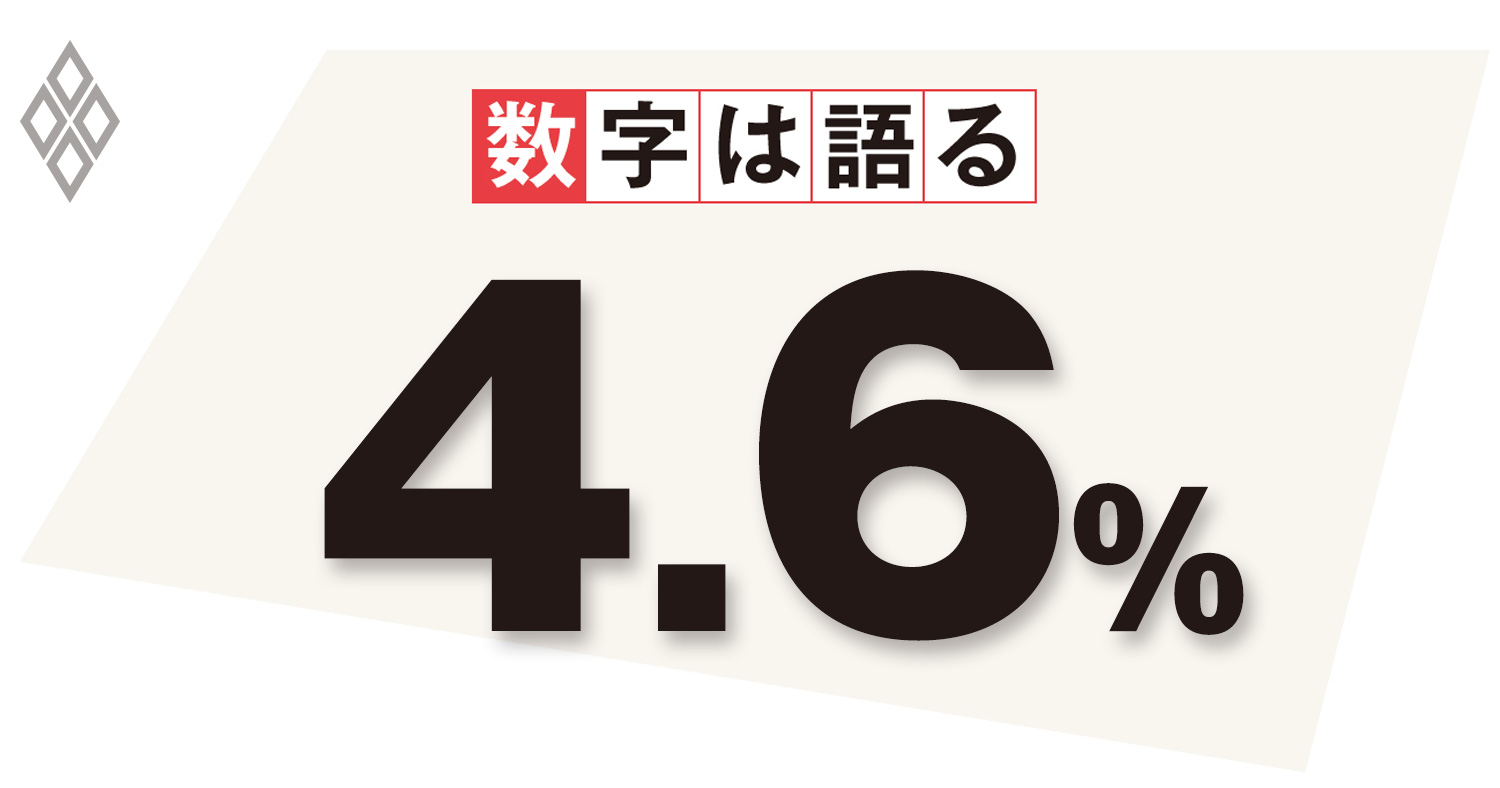 出所:「総世帯数の5%にも満たない『標準世帯』」大和総研金融調査部
出所:「総世帯数の5%にも満たない『標準世帯』」大和総研金融調査部
お父さんが働き、お母さんは専業主婦、子どもが2人の世帯は典型的な家族のイメージだ。しかし、現実は少し違うと多くの人が感じることだろう。実は、このような世帯(4人世帯・有業者1人)は総世帯数において4.6%しか占めておらず、20世帯に1世帯未満なのだ。
昭和49(1974)年には、このような世帯が14.6%と最も多く、まさに「標準世帯」であった。しかし、その後世帯構成は変化し、現在最も多いのが1人世帯・無業(17.0%)であり、次いで1人世帯・有業(15.7%)、2人世帯・無業(13.7%)と高齢者や単身者の多さが窺われる。また、4人世帯・有業者2人の世帯が6.8%と、専業主婦(主夫)よりも共働き世帯の方が多いようだ。
つまり「標準世帯」とは昭和を反映したものであり、現在ではとうに標準ではない。問題なのは、この標準世帯が国民生活全体の縮図として、社会保障や税などの制度設計で議論されることだ。
少子高齢化による人口構成の変化だけでなく、ライフスタイルの多様化、グローバル化や産業構造の変化などで世帯の様相はがらりと変わる。さらに今後、外国人労働者受け入れの影響も含め、社会の姿は逐次変化することだろう。これらの変化に国民が耐えられるよう、支援制度や財源の措置を公平・公正に考えていく必要がある。
その議論のベースとなるのがデータである。標準世帯という型にはめた議論ではなく、データに基づいて多様な世帯をシミュレーションし、多様な国民全てが安心・納得できる制度設計をしていかなくてはならない。
しかし、家計調査では今でも標準世帯という言葉が使われ、単身者や無業世帯などが正確なデータで把握できているとはいえない。国税庁では低所得者の所得が把握できていないため、給付付き税額控除など低所得者を支援する仕組みも実現できない。
政府はデータを利用した社会を目指すと宣言し、デジタルを前提に社会の仕組みを変えていくという。今こそデータを収集・活用して、誰もが納得できる制度設計を支援する環境を構築すべき時だ。
(富士通総研 経済研究所 主席研究員 榎並利博)







