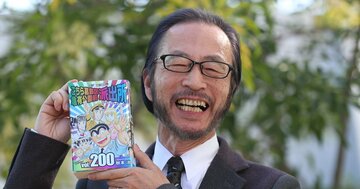いつまでもスタートアップのように生き生きとした組織であるためには? Photo:PIXTA
いつまでもスタートアップのように生き生きとした組織であるためには? Photo:PIXTA
視野を広げるきっかけとなる書籍をビジネスパーソン向けに厳選し、ダイジェストにして配信する「SERENDIP(セレンディップ)」。この連載では、経営層・管理層の新たな発想のきっかけになる書籍を、SERENDIP編集部のシニア・エディターである浅羽登志也氏がベンチャー起業やその後の経営者としての経験などからレビューします。
事業計画、就業規則、長期予算…
当たり前のルールが存在しない成長企業
最近、とあるスタートアップを手伝うことになった。3人の技術者が立ち上げたばかりの、企業に向けてITサービスを提供する会社だ。
創業者の3人は全員、取締役という肩書だ。私は非常勤監査役として加わった。今のところ他に社員はいない。
会社の運営は、すべてその3人が相談し、意思決定しながら進めている。お互い信頼し合い、生き生きと楽しそうに働いている感じが、はたで見ていて気持ちがいい。
ビジネスは、すこぶる順調だ。3人からは「そろそろ専任の営業担当を採用したい」といった声も上がる。
彼らの仕事ぶりを見ていると、20年以上前のスタートアップでの経験を思い出す。あの頃は、大変なこともたくさんあったが、楽しさの方が勝っていた。
だが、こうした楽しさも、会社の成長とともに社員の数が増えると、徐々に失われていくものだ。組織ができ上がってくると、ルールで縛らざるを得ないことも多くなってくるからだ。
それにもかかわらず、創業から60年以上がたち、社員が数千人規模になってもスタートアップのように社員が生き生きと働く会社が存在する。ブラジルのセムコ社(SEMCO Partners)だ。
1954年創業のセムコ社には現在3000人を超える社員がいる。日本ではあまり知られていないが、ブラジルで10社の事業会社を擁し、産業用工業機械やコンサルティング、不動産などを広く手がけるコングロマリット(複合企業)である。
その独特の経営スタイルが世界中で注目されており、ハーバード大学でも研究テーマに挙げられているそうだ。