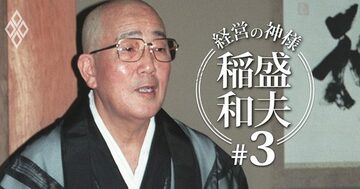Photo:kyodonews, Santiago Urquijo/gettyimages
Photo:kyodonews, Santiago Urquijo/gettyimages
1954年11月、創価学会の第2代会長の戸田城聖氏が「文化部」を設置し政治活動に乗り出してから、はや六十余年がたった。その間、池田大作氏が検挙された“大阪事件”などを経て、今や公明党は政権与党の座に就いている。特集『創価学会 90年目の9大危機』(全16回)の#15では、その知られざる政治史をジャーナリスト、高橋篤史氏が斬る。
1954年に創価学会が政治活動を開始
2年後の56年に参議院議員に当選
第2代会長・戸田城聖の下、創価学会が「文化部」を設置して政治活動に乗り出したのは1954年11月のことである。
当時、学会は「折伏大行進」をスローガンに信者数を急激に伸ばし始めていた。とはいえ、同年末の世帯数はまだ16万世帯。現在の公称世帯数の50分の1にすぎなかった。
翌55年4月、学会は早くも議会に足掛かりを得る。理事長としてナンバー2の座にあった小泉隆が東京都議会議員、財務部長の森田悌二が横浜市議会議員にそれぞれ当選。さらに56年7月には、青年部を率いた辻武寿ら3人が参議院議員に当選し国政への進出を果たした。
当時、学会は日蓮正宗の在家信徒団体の中でも最も急進的な勢力だった。他宗教・他宗派を「邪宗」と決め付け、道場破りまがいの攻撃に明け暮れていた。もともと日蓮正宗の宗祖である鎌倉時代の高僧、日蓮は「立正安国論」で知られるように政治への関与に積極的だった。仏教経典の一つ、法華経を基にした政治こそが国家安寧をもたらすと説いたのである。
そのため学会の政治進出は必然の流れであり、「広宣流布」、つまりは信者を獲得し日蓮正宗の教えを広めるための有力な手段と位置付けられた。目標としたのは「王仏冥合」の実現であり、その象徴となる「国立戒壇」の建立である。
前者は日蓮仏法が世俗の法律(=王法)の基礎となる政治体制の実現であり、後者は総本山、大石寺に安置され信仰の対象となってきた「弘安2年の大御本尊」(文字曼荼羅を板に彫刻したもの)を収める国立施設を造るものだ。
初期の頃、急進勢力である学会の選挙活動はたびたび警察沙汰となった。57年には当時、渉外部長兼参謀室長だった池田大作氏ら数十人が公職選挙法違反で大阪府警に検挙されている(大阪事件)。池田氏が保釈された日に開かれた集会の場で政治活動の意義を問われた戸田はこう明言していた。
「日蓮大聖人様が国立戒壇を作らにゃあならんとこう仰せられた。それを今実行しようとしているだけなんだ。何も政権なんかに関係ないよこっちは」(57年7月21日付「聖教新聞」)
大阪事件では数十人に有罪判決が下った一方、池田氏は無罪となった。このことはその後、同氏のカリスマ性を高めるまたとない逸話に転化していくことになる。