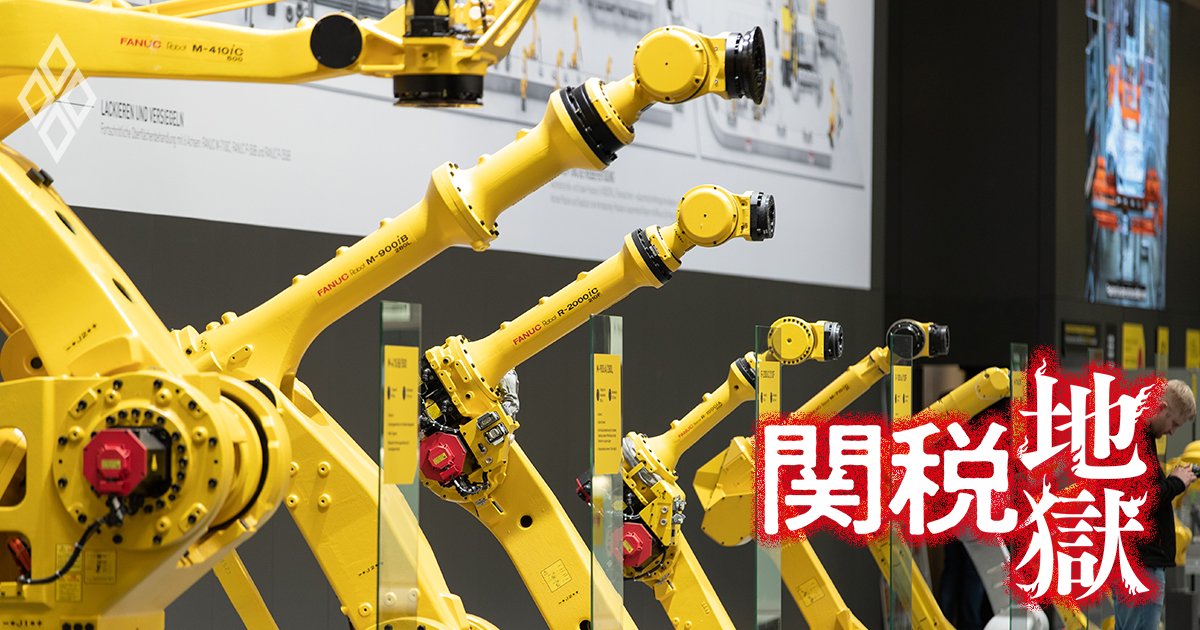写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
リモートワークは
コロナ後の「新たな日常」か
新型コロナウイルスの蔓延(まんえん)防止策として、リモートワークが推奨されている。
コロナ対策の中には、コロナ終息後も「ニューノーマル」の一環として定着するものもいくつかあるとされているが、リモートワークはその筆頭とも言われる。
だがその割には、リモートワークの定着が労働の形態や職場での上司や同僚との関係性、さらには労働生産性やライフスタイルにどのような変化をもたらすのか、掘り下げた議論はなかなか提起されない。
「同じ空間」で働くことにどういう意味があるのかも含めて、「リモート」と「同一空間」で働くことの違いを考えてみたい。
生産性を低下させる可能性も
「職場の創造性」が損なわれる懸念
リモ―トワークが、どういった仕事で、どの程度普及する可能性があるのか、その場合、どのような変化が考えられるのか。