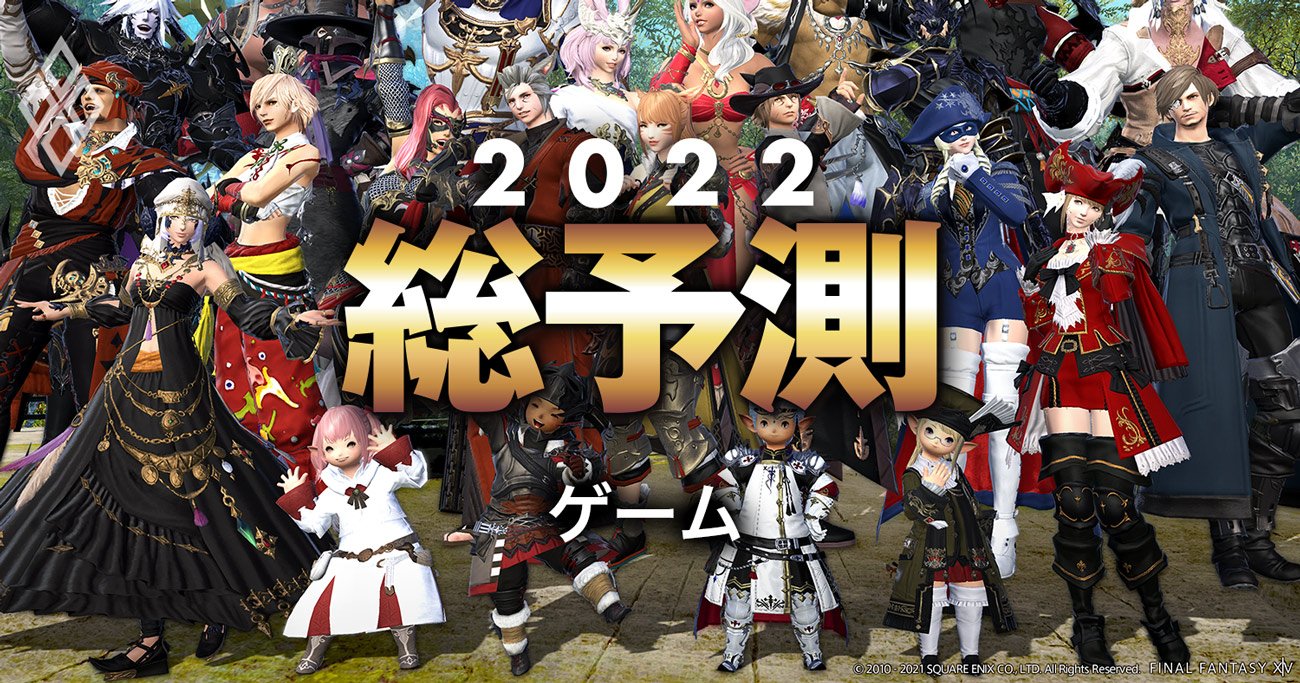
多くのMMORPG(大人数参加型オンラインRPG)がユーザー数維持に苦心する中、サービス開始11年経過した今もユーザー数を増やし続けている「ファイナルファンタジー14(FF14)」。特集『総予測2022』の本稿では、FF14成功の立役者であるゲームクリエイターの吉田直樹氏に、ゲーム業界の展望を聞いた。(聞き手/ダイヤモンド編集部 野村聖子)
プレイ時間の長さが価値を生んでいたMMO
復活の鍵は「ツマミ食いでも面白い」
――社会人でも最前線に追い付きやすくするなど、従来のMMOの常識からの脱却がFF14成功の要因といわれています。MMOに対する世間のニーズが変わってきたと感じたのはいつごろですか。
15年ほど前、携帯電話の各種機能が発達し、コミュニケーションが電話での同期型直接対話から、非同期となるテキストベースのショートメールへと移ったあたりですね。
携帯電話の普及との相乗効果で、「情報収集の速度と量」が飛躍的に伸びることになった結果、「誰もかれもが熱中する」といったブームがつくりにくくなり、マスメディアを通じたPRも、徐々に効果が薄れていきました。
僕自身、自分が接触するゲームや趣味が、それまでよりも多面的になると同時に、非同期コミュニケーションに時間を割かざるを得なくなりました。メールがたくさん来れば、その分返事をします。加えてSNSの発展で「コミュニケーションに使う時間」も増えました。時間は誰しも24時間しかない。気付かないうちに、「可処分時間が減っていた」というわけです。
こうなると「長時間遊ばないと面白さが伝わりにくい」「プレイ時間による積み上げが価値をつくる」といったタイプのゲームは、選択されにくくなるだろうと考えました。もちろん、こうしたゲームが「悪い」とか「面白くない」と言っているわけではありません。僕自身こうしたタイプのゲームに熱中し、育ってきたので、そこにしかない面白さがある、ということもよく知っています。
しかし、FF14というゲームが、一度大きく失敗してからの再起プロジェクトであることを踏まえると、「より多くの人に触れてもらう」ことを優先すべきと判断しました。「少しずつツマミ食いでも十分楽しい!」というゲームデザインですね。しかしながら、MMOのゲームデザインに対して、「先鋭化した世界の中でしか味わえない強烈な体験」というニーズは、また徐々に上昇してくると考えています。ニーズは時代で変わりますが、繰り返すものでもあるためです。
 2010年にサービスを開始した「FF14」。スクウェア・エニックスのMMORPG第2弾。しかし、状態が著しく不良で12年にいったんサービス終了。開発体制を一新、13年に再度サービスを開始した。4度の拡張を経て、21年12月には全世界でのユーザー数が2500万人を突破した
2010年にサービスを開始した「FF14」。スクウェア・エニックスのMMORPG第2弾。しかし、状態が著しく不良で12年にいったんサービス終了。開発体制を一新、13年に再度サービスを開始した。4度の拡張を経て、21年12月には全世界でのユーザー数が2500万人を突破した







