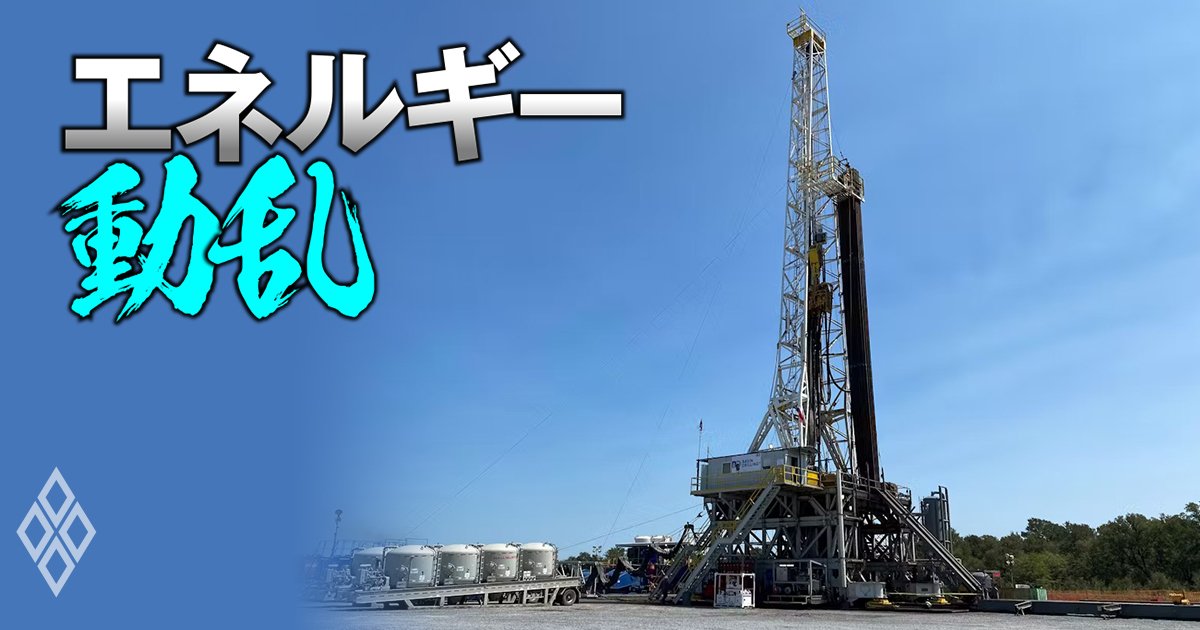2022年の主人公は、間違いなく習近平氏とジョー・バイデン氏だ。英・エコノミスト誌の別冊「世界はこうなる」シリーズの2022年版の表紙は、ウイルスの拡大写真、大小2つの風力発電機、激しく上下する折れ線グラフ、ミサイルにも見える注射器や原子力記号にも見える中央の赤い円とともに、両首脳の顔写真をレイアウトした。象徴的な画像と謎めいた図案で来年を予想することで知られている同誌のタイトルも「THE WORLD AHEAD 2022」(今回から「in」が「AHEAD」に変更されている)となり、多くの世界の読者に「2022年以降も対立が続く」と解釈させた。東西を分断する深い溝とは何か。(ジャーナリスト 姫田小夏)
「デカップリング」と言われながらも、対中投資が増加
2021年を振り返れば、世界は不安定さを増し分断が進んだ。
昨年4月、オーストラリアは巨大経済圏構想「一帯一路」の協力の覚書を破棄することを発表した。さらに、鳴り物入りで報道されたEUと中国との包括的投資協定の合意も昨年5月に審議が凍結された。また、9月には、米英豪による安全保障パートナーシップ「AUKUS」が発足し、この3カ国が協力し、オーストラリアの原子力潜水艦の導入を決めた。
バルト三国の一つであるリトアニアも中国封じ込めに加わり、11月18日に「台湾代表処」を正式に開設。12月に発足したドイツ新政権もメルケル政権とは打って変わって中国に距離を置く姿勢だ。そして、同月、カナダのトルドー首相は「中国は西側諸国を分断しようとしている。互いの対立を防ぐために共同戦線を張るべきだ」と発言した。
米国が主導する中国包囲網は着々と進んでいるが、一方で中国と米国の貿易額は増えている。もともと新型コロナウイルスの発生で、中国と米国の輸出入総額は2020年初頭に急減したが、下半期には回復し、前年の約5400億ドルを上回る5867億ドルに達した。2021年は1〜10月の輸出入総額だけでも6099億ドルで、好調に推移している。
2021年における中国への外国投資総額も前年比で2けた増となる可能性が報じられている。中国商務部は昨年11月、2021年1〜10月の中国の外国からの直接投資実行額は9431億5000万元(約1478億ドル)で、前年比17.8%増加したと発表した。デカップリング(分断)と言われながらも、「中国の米国商工会議所の調査では、会員企業の3分の2が2021年に対中投資を増やす計画」だと新華社は報じた。
2021年10月、筆者がベルギーで対談したカナダ籍のジャーナリストは「米中対立などショーにすぎず、水面下ではしっかりと商売を進めている」と話していた。彼はバイデン大統領と習近平国家主席のせめぎあいも茶番だと言っていたが、むしろ「東西の対立は宿命的で根深いもの」と捉えていた。