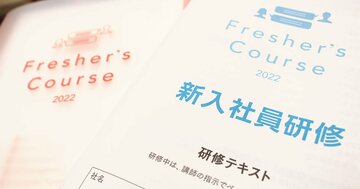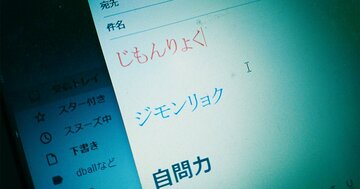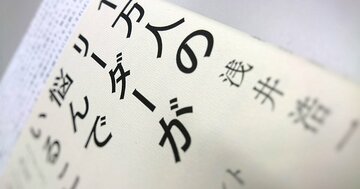“教えること”は、その人自身にとって貴重な機会
管理職や先輩社員を見て新人が育っていくことを考えると、教える側となるOJTトレーナーの果たす役割はとても大きい。管理職がどのような人物をOJTトレーナーに選出するか――その選択は、かなり重要だ。
関根 新人教育がうまくいっていない企業を見ていると、「教える側の適任者がいないから」「新人と年齢が近いから指名した」など、OJTトレーナーの選び方が曖昧なケースが多いです。逆にうまくいっているところは、「教える側としてはまだ若いけど、今後はチームリーダーになってほしいから選んだ」「後輩を指導する経験をしっかり積ませたいから選んだ」といったように、管理職が組織の先を見据えたうえで、OJTトレーナーの任命理由をはっきりさせています。
選ばれたOJTトレーナーはプレッシャーを感じてしまう場合もあるのですが、私たちは「皆さんは『いざなう人』なんですよ」とOJTトレーナーの研修でお伝えするようにしています。経験や人脈をまだ作ることのできない新人を「いざなって」あげれば、あとは新人本人が自在に学んでいきますから、プレッシャーに感じる必要はないのです。
先ほど、「教え上手は学び上手」と言いましたが、教えることがうまい人は、教わる側の新人からも学んでいることがあります。そういう意味でも、「OJTトレーナーは絶対的な存在ではない」と思っていただくとよいでしょう。
教える側と学ぶ側は主従関係にあるのではなく、「パートナー」のような間柄と言えるのかもしれない。教える側は、「いま、確実に教えなくてはいけない!」と肩肘を張らずに、学ぶ側を長い目で見守る意識も大切なようだ。
関根 当たり前ですが、相手は自分とは違う人ですから、思い描くとおりには育ってくれません。教える側としてできることは、新人が育ってくれる「環境」をつくることです。「環境」とは、つまり、「経験」と「人々」です。先ほどの「いざなう」にも通じますが、どんな経験を積ませて、どんな人たちとの関わりをつくってあげるか、です。育っていくかどうかは学ぶ側次第なところもありますし、成長するにも時間が必要です。1年目は分からなかったけれど、3年目でようやく分かったというケースもよくあるので、最初から「すべてを教えよう!」と気構えないほうがいいですね。
人に教えるということは、面倒だったり、イライラしたり、自分の感情に向き合うことでもあります。同じ内容を教えても、相手によってうまくいったりいかなかったりするので、「人はそれぞれ違う」ということに明確に気づく機会にもなります。自分の感情に向き合い、何かの気づきがあるというのは幸せなことです。「教えることは貴重な機会」と思えるといいですね。