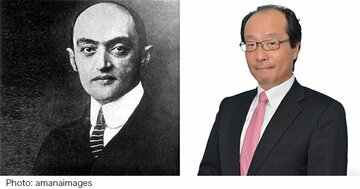円安は、輸出比率の高い製造業には追い風となる。決算の上方修正が続出するかもしれない。製造業を長年研究してきた藤本隆宏氏は、今こそ日本経済を「設備投資増→輸出再拡大・増産→価格・付加価値アップ→利益・賃金の同時アップ→人員確保と生産性向上で増産」の好循環軌道に戻すチャンスだという。長期視点で、日本の製造業の競争力を高める戦略を、3回の連載で詳しく伺った。3回目は、日本企業がどこの領域で戦っていけば良いのか、その見極め方を論じていただいた。(聞き手/ダイヤモンド社 ヴァーティカルメディア編集部 編集長 大坪亮、構成/嶺竜一)
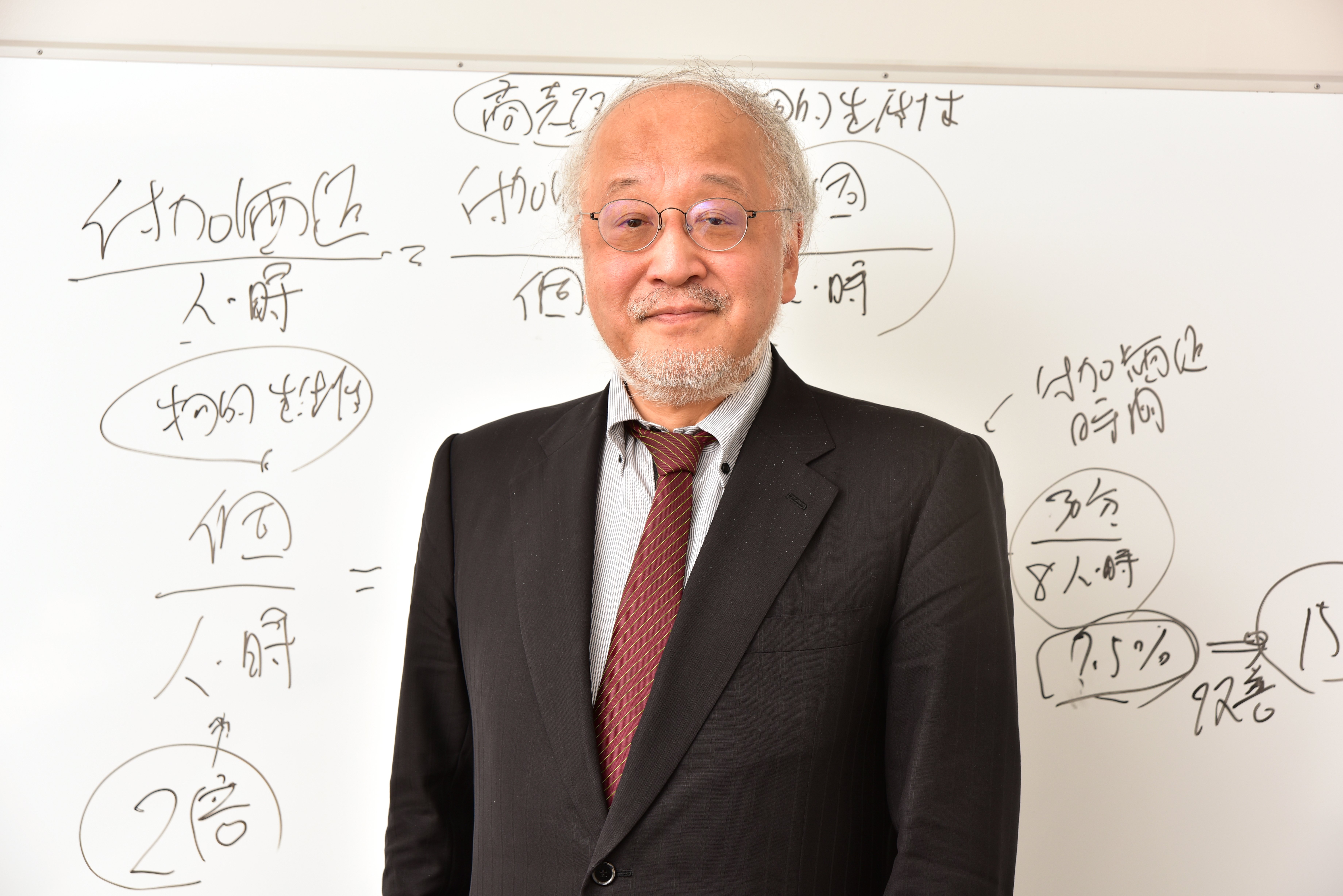 藤本隆宏(ふじもと・たかひろ)1955年生まれ。東京大学経済学部卒。ハーバード大学ビジネススクール博士(D.B.A.)。専攻は、技術管理論・生産管理論、進化経済学。東京大学大学院経済学研究科教授、同ものづくり経営研究センターセンター長等を経て、2021年より現職。『生産システムの進化論』(有斐閣)、『生産マネジメント入門〈Ⅰ〉〈Ⅱ〉』(日本経済新聞出版社)、『現場主義の競争戦略』(新潮社)など著書多数。
藤本隆宏(ふじもと・たかひろ)1955年生まれ。東京大学経済学部卒。ハーバード大学ビジネススクール博士(D.B.A.)。専攻は、技術管理論・生産管理論、進化経済学。東京大学大学院経済学研究科教授、同ものづくり経営研究センターセンター長等を経て、2021年より現職。『生産システムの進化論』(有斐閣)、『生産マネジメント入門〈Ⅰ〉〈Ⅱ〉』(日本経済新聞出版社)、『現場主義の競争戦略』(新潮社)など著書多数。Photo by Ryuichi Mine
――連載最後の今回、前回までのお話をまとめていただき、DX(デジタル・トランスフォーメーション)との関連についてお聞かせください。
前回は、デジタル化時代の上空、地上、低空戦略の例について見てきました。むろん、どの階層のどの戦略に注力するかは、産業や企業によって異なるでしょう。
とはいえ、この3階層の戦略の共通点は、当該企業が付加価値の良い流れ作り、すなわち「広義のものづくり」の能力構築を継続し、そこから自社標準の貫徹(上空戦略)、顧客データの共有(低空戦略)、高度な変種変量変流生産(地上戦略)へと向かうことだ、と私は考えます。
連載1回目で言いましたように、低成長・労働力不足・物価上昇・賃上げ圧力の時代には、「良い設計の良い流れ」の実現、つまり広義のものづくり革新による、付加価値生産性の向上、納期順守、高品質維持の重要性が増します。
デジタル化はそのための有力な手段ですが、あくまでも手段の一つです。こうした本質論を軽視し、流行手法を追うだけの「デジタル化のためのデジタル化」は、戦略論の理にかないませんからおそらく失敗します。
付加価値が流れている空間はあくまでも産業現場ですから、今のような時代の産業戦に必要な企業人材は、現場から遊離した戦略スタッフではなく、高高度の戦略思考も低高度でのオペレーション思考も同時にできる「軍師」タイプの人材でしょう。
産業経営学の現場サイドを担当する「ものづくり経営学」の中核概念は、「高付加価値を担う良い設計」の「淀みの少ない良い流れ(flow)」を重視することです。要約すれば、「良い設計の良い流れ」を作ること、さらには「流れを作る人」を作る人材育成だと考えます。
それはまた、元トヨタ自動車副社長の大野耐一氏のトヨタシステムにも、そこから学んだ欧米のリーンシステムにも、『ザ・ゴール』著者のエリヤフ・ゴールドラット博士のTOC(制約理論)にも、また日本発の全社的品質管理(TQC)や品質工学にも共通する「あるべき姿」だといえるでしょう。
いずれにせよ、今我々に必要なのは、流行追随ではなく、歴史観も現場観もしっかり持った上での理詰めの戦略構築です。
国の産業発展の歴史的経緯には違いがあり、従って、各国に偏在する産業現場の組織能力や、その組織能力に適合する比較優位製品の設計思想(アーキテクチャ)にも、国ごと地域ごとに違いがあります。
現在好調な海外のA国のやり方を参考にするのは当然としても、それをそのまままねしたのでは、当のA国には勝てない。これは戦略論の基本です。
「生産の比較優位」や「設計の比較優位」が存在しない形で、流行追随のデジタル化を推進しても、成果は乏しいわけです。
必要なのは、「横並びのデジタル化」「『いいから、とにかくやれ』のデジタル化」「怒られないためのデジタル化」などではなく、「良い設計の良い流れ」「設計の比較優位」などの基本原則に常に回帰した上で、強みを伸ばし弱みを補う、戦略的な「勝てるデジタル化」です。