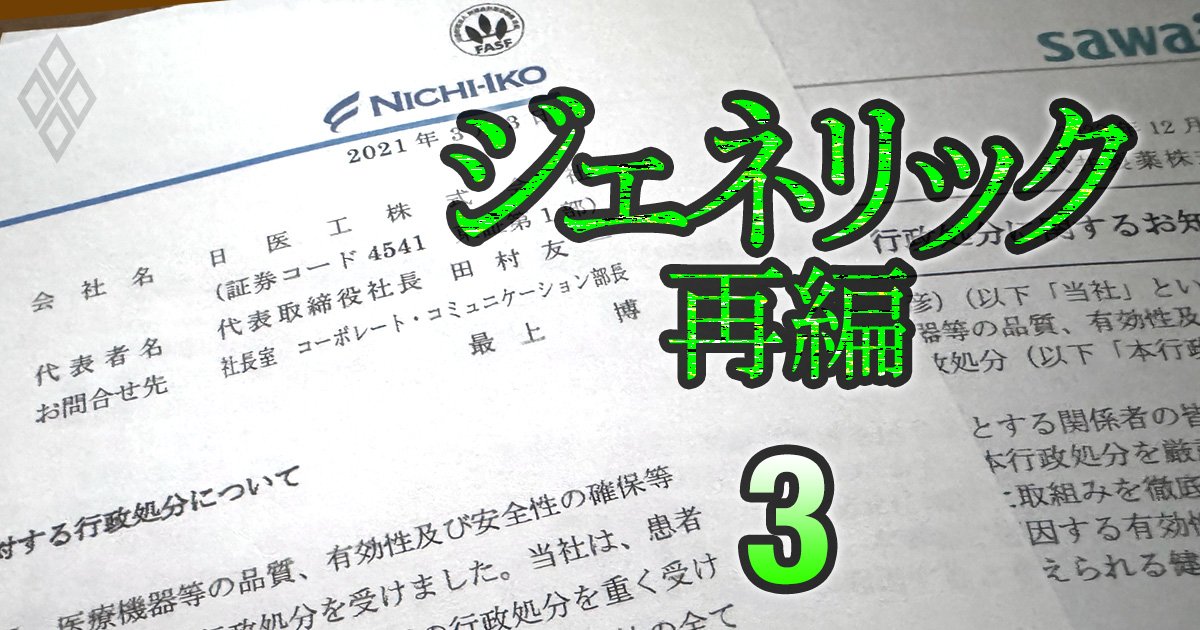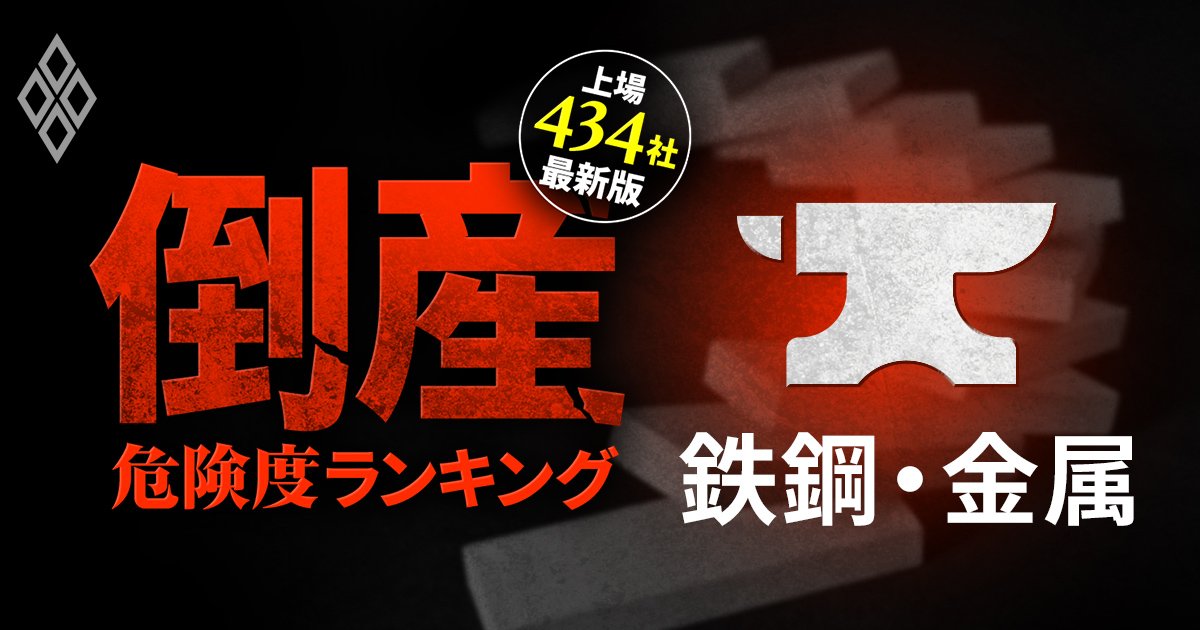まずは、長野電鉄の成り立ちを振り返りたい。同社は1926年、屋代~須坂~信州中野~木島間を運行していた河東鉄道と、権堂~須坂間を開業させた長野電気鉄道が合併して誕生した。
1927年に信州中野~湯田中間、1928年に権堂~長野間が開業し、現在の路線が形作られた。最盛期には約70キロの路線を有していたが、2002年に信州中野~木島間、2012年に屋代~須坂間が廃止され現在に至る。
長野~善光寺下間が地下化されたのは1981年のことであったが、1972年の業界誌『運輸と経済』で当時の長野電鉄取締役が語るところによれば、同区間の改築が浮上したのは1960年代前半のことだったという。
長野市が長野電鉄に
地下化を打診した理由
この頃、国鉄長野駅の貨物用地が払い下げられることになり、長野市は駅周辺11ヘクタールの区画整理事業を計画した。この区域に長野電鉄が含まれており、再開発のために線路を立体化できないかと打診があった。
長野市は歴史的に善光寺を中心に市街地が形成されたが、都市化の過程で市街地が長野電鉄の線路を越えて東側へと広がったために、鉄道が市街地を分断する形になってしまった。ある踏切では朝7時から夜7時までの12時間で計2時間しか開いていなかったというから交通渋滞が起こるのは当然だった。
長野市は1966年に篠ノ井市と更級郡、上水内郡、埴科郡、上高井郡の3町3村と合併して市域が拡大しており、都心アクセスの向上と都市機能の強化を図るため、連続立体交差化による踏切除却と市街地の分断解消を実現するとともに、立体化した長野電鉄に沿って南北縦貫道路を整備したいと考えていた。
しかし、長野電鉄は立体化を望んでいなかった。鉄道の立体化は基本的に道路側の都合で行われる事業であり、鉄道の乗客増には直結しない。都市部と異なり、地方私鉄の利用者は既に減少傾向にあり、費用を負担してまで得られるメリットはなかったからだ。
立体化には線路を上げるか下げるか、つまり高架化と地下化の選択肢がある。踏切除去を目的とした鉄道の連続立体交差事業は戦前から存在したが、本格化するのは1969年に建設省と運輸省で事業の費用負担に関する「建運協定」が結ばれてからのことだ。
近年こそ大都市部で地下化の事例がみられるが、ほとんどの事業は比較的安価な高架式で行われてきた。建運協定は高架化の費用負担割合は定めたものの、地下化については別途協議するとされており、補助制度の名称自体が「鉄道高架費補助」となっていた。
ところが長野市が目指したのは地下化だった。高架線は中央分離帯に橋脚を設ける必要があり、その分だけ街路は狭くなる。また景観も損なう。これらを解決する地下化を長野市は初期段階から腹案として温めていたようだが、長野電鉄に打診したのは1960年代末になってのことだった。