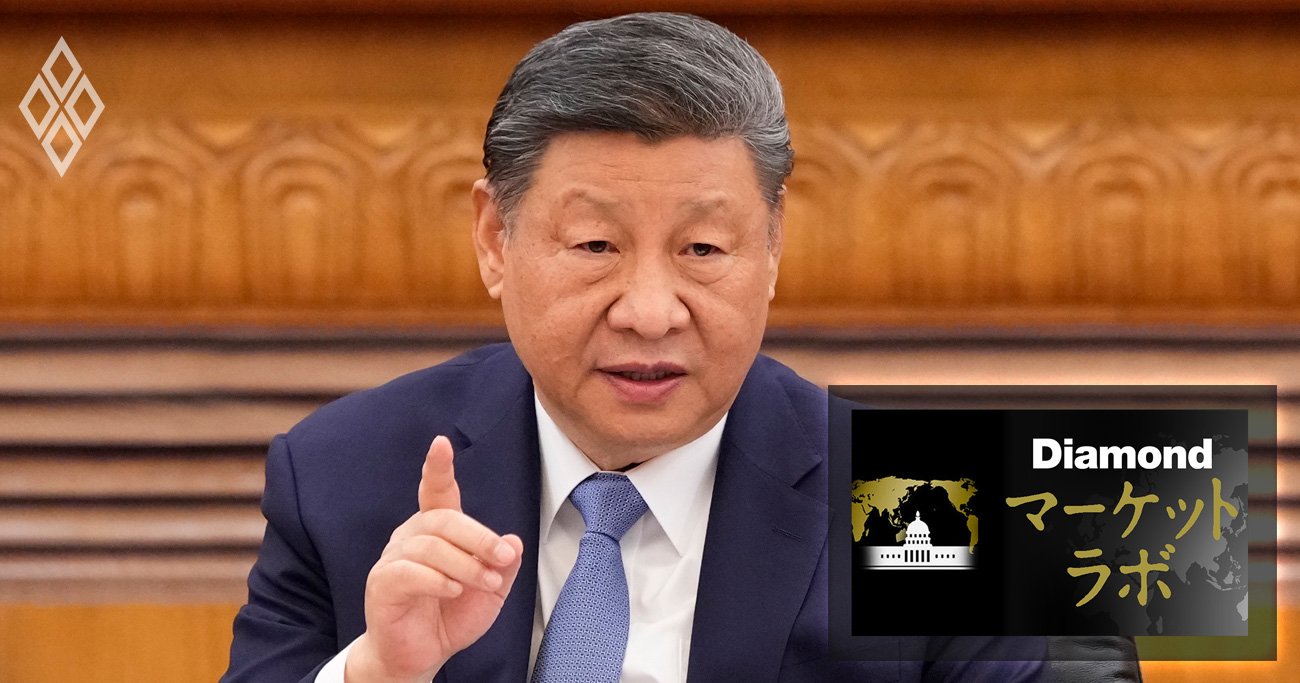社会主義に奪われた人々の身体
私にとって、工場の機械も生物の器官として理解できたが、やはり豚が生き物なのに対して、あの中の鉄塊が恐ろしいものの内臓としか見えなかった。
父は仕事服を着て、自慢げな顔でその化け物のような機械を紹介する。父はプロパガンダ映画に出ている若手エンジニアの像そのものだ。
工員の顔を見るのはとても好きだった。そこで働いていた人たちは父と同じ、田舎出身だった。つらかっただろう。川と森の代わりに機械を見守る毎日。社会主義国家に生まれ、完全に計画経済の子だったため、工場は彼らの身体を支配し続けた。父はよく頑張ったと思う。私はそのようにはなりたくなかったから、私の身体があらゆるものにたいして抵抗しつづけた。言葉を完全に失うまで。
毎晩、父が暴れるたびに、私の身体は動かなくなった。ひとたび傷つけられると、身体がまったく反応しなくなる。金縛りのような状態が何時間も続いた。ルネ・マグリットの絵に出てくる空に浮かぶ大きな石のように。意識があるけれど不思議に身体が動かせない。つらかったというより、今にしてみればある種の踊りにしかすぎなかった。傷つけられた身体で懸命に自然を探そうとしていた。